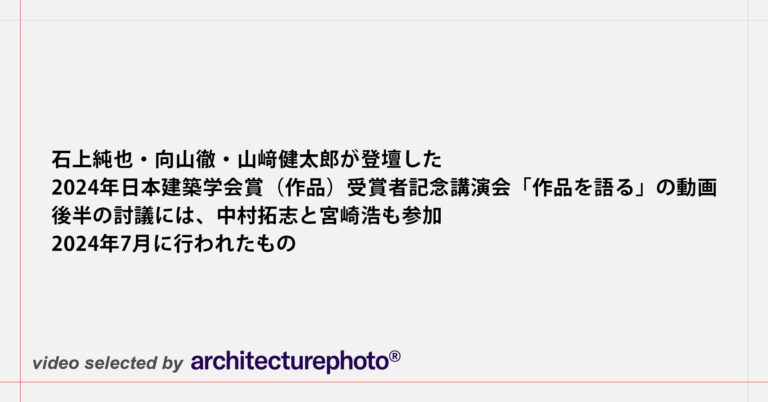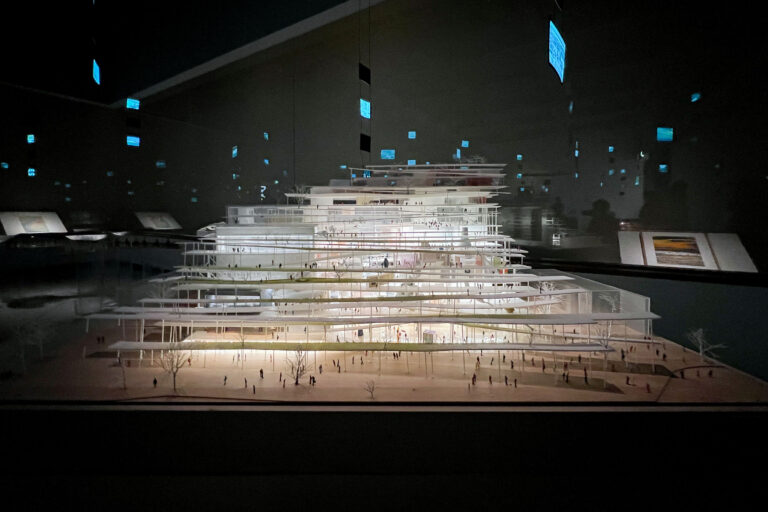architecture archive


東京都庭園美術館での展覧会「建物公開2024 あかり、ともるとき」の入場チケットを抽選でプレゼントいたします。
“照明”に焦点を当て“旧朝香宮邸”を公開する内容です。各室の照明に関する解説と資料を通して魅力を紹介します。また、会期中は通常非公開のエリアも見学でき写真撮影も可能になるとのこと。
会期は、2024年9月14日~2024年11月10日まで。展覧会の公式サイトはこちら。入場チケットプレゼント企画の応募締切は、2024年9月20日(金)13時まで(お申込みにはGoogleアカウントが必要になります)。こちらのフォームからご応募ください。
厳正な抽選を行い当選された方にはメールにてご連絡いたします(メール送付を当選発表にかえさせていただきます)。
見上げてときめく、多彩な灯りの世界
本展は、1933年(昭和8)に竣工した旧朝香宮邸(現・東京都庭園美術館本館)の建築としての魅力を存分にご堪能いただくため、年に一度開催している建物公開展です。これまで当館では毎回テーマを設定し、様々な角度から建物公開展に取り組んでまいりました。今回は、この建物のみどころの一つとも言える「照明」に焦点を当てます。
1920年代、滞在中のフランス・パリにて、当時全盛期だったアール・デコの様式美に触れ、魅せられた朝香宮夫妻。帰国後、最先端の技術と最高級の素材を用い、アール・デコの精華を積極的に取り入れた自邸を建設しました。フランスの装飾美術家アンリ・ラパンが主要な部屋の室内装飾を手がけ、宮内省内匠寮の技師らが全体の設計を担い、日仏のデザインが融合する形で完成した建築です。現在は美術館として活用していますが、竣工時からの改変はわずかで、当時の様子を良好な状態で伝えることから、国の重要文化財に指定されています。
天井や壁面に据えられた照明は、旧朝香宮邸の室内空間において特に印象的な要素です。こだわりの材質やディテールがあしらわれた照明器具の多くは、この邸宅のために制作されたもので、華やかさと独自性を高めています。本展では、各室の照明に関する解説、資料を通して旧朝香宮邸の魅力に迫るとともに、同時代のランプ類を展示します。また、本館の窓のカーテンを開け放ち、自然の光を感じる空間で、宮邸時代の家具や調度を用いた再現展示をお楽しみいただきます。
秋の季節、やわらかな光を放つ灯りのもと、心に染み入るひと時をご堪能ください。
以下に、詳細な情報を掲載します。




岡田良太+藤井田仁 / 岡藤石が設計した、東京・新宿区の「地中のトウキョーオフィス」です。
地下フロアでの計画です。建築家は、“face to faceの交流促進”も可能にする空間との要望に、“生々しい生命感のある地中の働く場”を志向しました。そして、“動植物の行動”を取入れ構想して様々な樹種や年代の素材を用いて作りました。
東京、飯田橋界隈の地下2階にあるオフィスの改修計画。
既存のオフィス空間は地下2階のため自然光が少なく、システム天井やOAフロアで構成された均質で白く明るい人工的な場所であった。
クライアントからの特徴的な要望は、face to faceのコミュニケーションが促進される場所を設けたいとのことだった。
そこで、多摩の製材所で使われなくなっていた地産の様々な樹種の保管材をふんだんに用いて地下階特有の個性を高め、生々しい生命感のある地中の働く場所を計画した。
そして、動植物の行動や成長を設計手法に取り入れ、地下階らしい静と動が共存する「動き出しそうな生々しい空間」を目指した。「貼る、建てる、設置する、剥がす、塗る」のような人が建築を作る言葉で計画するのではなく、「羽ばたく、生える、転がす、這う、崩れる」のように地中に潜む動植物の行動や成長、風化になぞらえて計画するとともに、風化した木材や家具、さまざまな年代の素材を取り入れ、地中性を空間に浸透させることを考えた。


“創造的な対応”と“誠実なモノづくり”を掲げ、設計・施工・家具制作を手掛ける「ヨシダインテリア」の、施工管理職と家具制作職 募集のお知らせです。詳しくは、ジョブボードの当該ページにてご確認ください。アーキテクチャーフォトジョブボードには、その他にも、色々な事務所の求人情報が掲載されています。
新規の求人の投稿はこちらからお気軽にお問い合わせください。
私たちヨシダインテリアは、商業施設や住宅施設の設計及び施工、特注家具製造の分野で“創造的な”対応力を持って「良いモノをつくる」をモットーとし、モノづくりに励んでいます。
今回、更なる事業拡大のため、施工管理職、家具職人を募集しています。
【ヨシダインテリアについて】
本社のある和歌山は昔から“紀(木)の国”と言われ、江戸時代から林業が盛んな地域です。紀伊山地の良質な材料と優れた職人が集い、和歌山城に献上する家具や建具が生産されていました。ヨシダインテリアの家具店としての始まりはそのような和歌山の歴史背景から始まっています。そこから発展し、現在では全国よりご依頼を頂きショップ、ホテル、オフィス等の内装工事を中心とし良い空間づくりを続けております。
特注家具の製造においては、今でも創業地である和歌山の自社工場を中心に職人達と共に地域に密着し、家具製作を行っています。
小さな組織ではありますが、社員ひとりひとりが誠実にモノづくりと向き合い、クリエイティブに挑戦し続けることを第一と考えており、今後も成長を続けていきたいと思っております。




橋村雄一 / Studio Hashimuraが設計した、佐賀市の「名尾手すき和紙工房」です。
土砂災害を受けての移転計画です。建築家は、製造工程で用いられる大量の水への対応を意図し、RC基礎を1.2mまで立ち上げる建築を考案しました。また、柱を基礎の側面に固定する構造として“周囲の美しい田園を望む連窓”も作り出しました。工房の公式サイトはこちら。
名尾手すき和紙は佐賀県名尾の山中で300年以上に渡って営まれていたが、2021年に豪雨による土砂災害に見舞われ、その再発リスクを避けるために麓の平地に移転することになった。この工房はその計画の第1期にあたり、第2期として店舗が隣接して新築される。
原料から紙になるまでのすべての工程がこの工房とその周辺で行われる。原料となる梶の木は近隣の畑で栽培され、大量に必要な清らかな水も地下から汲み上げられる。工房の約半分を占める屋外の作業スペースには原料を水に浸す水槽や蒸し釜があり、屋内では原料の粉砕、紙漉き、乾燥作業などを行う。
製造工程で大量に使用する水から建物を守るため、鉄筋コンクリートの基礎を1.2mまで立ち上げている。上部の木造の架構は、その高い基礎の側面に柱をボルトで固定することで水平力に応える構造である。水平耐力部材から自由になった壁面の上半分は周囲の美しい田園を望む連窓とした。
工房が完成して間もなく、和紙職人たちが先代から受け継ぎ使い馴れた道具を据えたとき、昔からそこに存在していたかのような風景が生まれた。更地に建てられた新しい建物が人と道具に刻まれた時間と融け合い、長い伝統とうまく繋がったことを確認できた。




安藤祐介建築空間研究所が設計した、愛媛・西条市の「異郷人の家 / 凹レンズハウス」です。
都心から移住する家族の為に既存民家を改修する計画です。建築家は、改修の選択を施主がポジティブに捉えられるよう、住まいを“家族を乗せた宇宙船”に見立てる“ナラティブな設計手法”を考案しました。そして、構成や素材もストーリーに基づき決定しました。
都心部から地方へ移住する家族のため、築32年の平屋建て木造住宅の全面改修を行った。
本計画は当初、分譲地への新築か、中古民家の改修か、土地や物件探しからスタートをした。候補となった中古民家は、正方形プランに方形屋根が大きく架かった一塊に見える特徴的な形をしており、天井裏には室内からは見ることができなかった小屋組みと広大な空間が広がっていた。
移住者である家族と既存家屋の特徴を重ね、住まいを「家族を乗せた宇宙船」と解釈し、「遠い場所から移動を終えこの地に降り、既存空き家に取り付き新しい生活を展開する」というストーリーを立て、空間構成やマテリアルの選定を行うこととした。このストーリー仕立ての設計により、「新築よりも面白いものができるはず」と、中古民家の改修をよりポジティブに選択してもらえるようになった。
既存家屋の外周軒下部分を増床し外壁を700mmほど屋外側に移動させ、収納やカウンターテーブル、家電スペースなど機能的な役割を配している。既存基礎の構造詳細が不明であったことから、増築部分の一部の新設基礎と外壁が、家全体を補強する構造計画とし、残りの部分は元の外壁からセットバックすることで無柱の水平開口を実現させた。L字に広がる水平連続窓には船のコクピットをイメージしたカウンターテーブルを設け、着陸後は田園風景を望む眺望窓となっている。
また、航行中に船外を魚眼のように広く確認するための凹レンズ窓が複数埋め込まれており、着陸後は凹レンズの特性が外光を広げる採光用トップライトとして機能している。外観にも複数の丸い天窓が宇宙船をアイコニックに表す。




浅井正憲+浅井百合 / 浅井アーキテクツが設計した、東京・足立区の「丸井スズキ足立事業本部新社屋」です。
菓子専門商社の施設の建替の計画です。建築家は、“部署間の連携強化”を目指し、分棟だった事務所と物流倉庫の一体化に加えてオフィスをワンフロアに収める構成を考案しました。また、複雑な関係を視覚化して働く人が“協働”を意識できる建築を造ることも意図されました。
明治28年創業の菓子専門商社、株式会社丸井スズキの事業本部の東京都足立区南花畑での建替えプロジェクトです。
分棟であった事務棟と倉庫物流センターを上下に重ね、メインオフィスをワンフロアに収めることによって部署間の連携強化を図り、社内の一体的な活動を促す構成としました。
1階はプロセスセンター(流通加工部門)、2階はメインオフィス、3階はプレゼンテーションの場と社内コミュニケーションの場、キッチンスタジオや品質検査室などの専門室で構成されています。企画、商品開発、品質管理、営業、バックオフィスチーム、物流センターなど社内の多岐にわたる業務それぞれに携わるワーカーが一体感をもてるよう、業務の流れをひとつの矩形の建築に集め、複雑な関係性が視覚的、空間的に現れることで「協働」を意識することができる、ひとつの街のようなオフィスを目指しました。
2階のメインオフィスがプロセスセンターのトラックヤードの庇代わりに張り出しているので、東面のカーテンウォールを介してオフィスから出庫するトラックが見える、トラックも入ってくるときオフィスの下階へ入り込んでいくような動線とするなどお互いの動きを感じることができます。
建物の奥行が物流倉庫に合わせて深いため、2階メインオフィス中央には3階と視線がつながる光が入り込んでくる吹き抜けがあり、3階部分で外気に面することで中間期には重力換気に用いることもできます。また、3階のコミュニケーションコーナーや企業フェアなどを行うプレゼンテーションスペース、ライブラリースペースともつながり、メインオフィス内の活動が社外の様々な事業につながっていくイメージを感じられるよう意図しました。




小嶋伸也+小嶋綾香 / 小大建築設計事務所が設計した、中国・安康市の宿泊施設「鹿柴山集 Luzhai cottage」です。
自然環境に恵まれたエリアの階段状の敷地での計画です。建築家は、風景との調和と建設負荷の軽減を目指し、地元産建材と地域の建設工法でつくる建築を考案しました。また、客室の間に“隙間空間”を設けて周辺民家のスケール感とも呼応させることも意図されました。
中国陝西省安康市内に存在する集落、漁湾村に計画されたホテルプロジェクト。
計画地は朱鷺が生息しているほどの美しい自然環境に恵まれ、山の斜面に石垣を積み上げて作られた階段状の畑地の中にあり、前面二面に棚田がパノラマ状が広がる景観が印象的な敷地だった。
生態系へのダメージを最小限に抑えることを念頭に、コテージ群を数期に渡り発展させていく今プロジェクトでは、新築による負荷を減らす工夫と共に、ランドスケープに馴染むデザインを目指した。そこで、地元で調達できる建材を最大限使い、この土地で長く親しまれてきた建設工法を可能な限り取り入れて計画をした。
棚田に向かって存在するL型形状で高低差のある敷地に、2階建の建築が連なるかのような大らかな一棟の建築を計画した。
1階部分は目の前に広がる田畑と目線が揃うようにデザインし、外壁には現地で調達可能な馴染みのある石垣で仕上げた。2階のテラス、屋根の部分には現地の建築同様、垂木部分を丸太にすることによって、周辺の建築との連続性を新築ながら感じられるようなディテールを施した。この施設では、客室と客室との間にエントランス機能を持つ、専用庭のような“隙間”空間を挿入し、周辺の平屋の民家とのスケールや景観としての調和を図った。ゲストはレセプションから各客室に向かう際、雄大な田畑を眺めながら、2階部分の“隙間”空間より客室にアプローチする。



保坂裕信 / haが設計した、神奈川・横浜市の「8つの光庭のある家」です。
往来のある道に面した敷地での計画です。建築家は、外の視線から保護しつつ“光が溢れる住環境”を実現する為に、天窓や高窓から採光する“光庭”を平面に散在させる構成を考案しました。また、施主の望む“ミニマル”も二重壁等を用いて木造で実現しています。
クライアントと土地探しから協働し、土地を決めて建築を建てる順番ではなく、希望の建築が建つ土地を探しました。
購入した土地は、前面道路が敷地の北西側で幅が約6.5m、道路斜線規制は緩い条件ですが、北西側に小学校が位置し児童の行き来なども多いため、建築内部のプライバシーを守りつつ、光が溢れる豊かな住環境の設計を求められました。
クライアントは、デザインに深く興味のある方で、線の少ない繊細なディテールでミニマルなデザインを希望していました。構造体は、計画当初はRCを希望していました。予算の都合で在来木造になりましたが、いわゆる「木造感」を極力消して、端正な佇まいの建築を求められました。
「構造」に関しては、二層吹き抜けと三層吹き抜けがズレながら重なっているダイナミックな空間構成を現実にするために、在来木造を基準に必要箇所に鉄骨梁を使用する事で成立させました。「光を導く開口部」は、線の少ない繊細なディテールを実現するために、サッシ枠を全てスチールの折り曲げとし、袖壁や垂れ壁を排除する事で室内に光と影の陰影をデザインしました。
「8個の光庭」は、敷地のポテンシャルを最大限に引き出す意図で敷地内に散在させると共に、隣接する内部空間に必要な光量を導くように配慮しました。「木造感」は、壁の厚みに着目し、要所要所で「W壁」を採用する事、その「W壁」に開口部をデザインし枠に奥行き感を作り出す事で、「木造感」を消す事に成功しています。




トラフ建築設計事務所と園田慎二建築設計事務所が設計した、神奈川・箱根町の「彫刻の森美術館 森の足湯」です。
“アートと自然が共存する屋外空間”の足湯の改修計画です。建築家は、環境にふさわしい存在を目指し、“美しい山の風景”を望みながら浸かれる空間を考案しました。また、15種の“多様な表情の石種”を組合わせた造形で彫刻群との調和も意図されました。施設の公式サイトはこちら。
日本初の屋外型美術館である彫刻の森美術館の開館55周年を機に、敷地から湧き出る源泉を活用した人気の足湯エリアの改修を行った。日差しを遮る工夫や、混雑の緩和、車椅子での利用や休憩スペースとしての機能を持たせつつ、アートと自然が共存する屋外空間にふさわしい新たな足湯施設が求められた。
彫刻の森美術館の特徴の一つでもある、美しい箱根の山の風景を望みながら足湯に浸かれるよう、以前は芝生広場を向いていた座席を、山側に向けて180度反転することを提案した。湯面には周囲の木々が写り込み、リゾートホテルのような特別な体験ができる。
足湯は、切り出された原石のような量塊感と存在感を持つ、15種の多様な表情の石種を組み合わせた造形で、庭園内の彫刻作品と調和する。美しいストライプを描く大理石「グリーンウェーブ」、自然にできたテラゾーのような花崗岩「ブラックマリナーチェ」など、利用者は好きな石や居場所を発見する楽しさを感じられる。また、足湯と共に手湯も設置し、気軽に楽しめる配慮をした。
石材による足湯の硬質感とは対比的に、大樹の木陰やパラソルが日差しの強い日も利用者の居場所をつくり出し、丸みを帯びたヒバの集成材による座面が、石材との美しいコントラストを成す。また、周辺敷地の造成で地盤面をフラットにし、隣接するカフェや2020年に手掛けた丸太広場キトキとの行き来のしやすさを改善している。



MVRDVが設計した、中国・香港の「Sotheby’s Maison」です。
世界的なオークションハウス“サザビーズ”の新店舗の計画です。建築家は、伝統宗教“道教”の“二元性”に影響を受けて、上下階で空間の性質を対比させる構成を考案しました。そして、上階は開かれた活気ある場とし、下階は思索的で親密な空間としました。
こちらはリリーステキストの翻訳です
新しいサザビーズメゾンのインテリアデザインにより、香港に世界屈指のパブリックアートと文化の拠点が誕生
MVRDVは、香港の高級ショッピングスポットであるランドマーク・チャーターの賑やかな一角を一変させ、世界屈指のオークションハウスであるサザビーズの新しい店舗をデザインしました。道教の二元性とダイナミックな変化の原理から影響を受けたインテリアデザインのメゾンには、2つの明確な雰囲気が存在します。明るく開放的な上層階はギャラリースペースとなっており、サザビーズがキュレーションした商品体験で、アート作品や高級品をゆっくりとご覧いただけます。一方、下層階には、没入型の体験とアート作品との親密な出会いを楽しむためのドラマチックな空間が設けられています。
新しいサザビーズのメゾンは、香港の中心部、チャーター・ロードとペダー・ストリートの角に位置しています。香港の階層的な歩行者環境のおかげで、ランドマーク・チャーターのこのエリアを訪れる月間130万人の来客の大半は、通りからスカイブリッジやエスカレーターを使って2階から入店します。
ここでは、デザインによって、かつては7つの個別の小売店舗であったものを5つの「サロン」という一連のまとまったものに統合し、アート作品や高級品を即座に購入できる状態で展示しています。各サロンはそれぞれ異なるテーマに焦点を当てています。さらに、サザビーズの食品および飲料体験ができる店舗が1階に間もなくオープンし、サザビーズ・メゾンがより幅広い一般の人々にとってさらに利用しやすいことを確かなものにします。
サロンの柔軟な白いスペースはサザビーズのDNAからインスピレーションを得た素材パレットによって引き立てられています。ウォールナットや大理石などの自然で高貴な素材を使用し、シャンパンカラーのスティールやサザビーズの青みがかった色調がアクセントとして加えられています。このメゾンのフロアは、できる限り全体を自由に探検できるように、途切れのないバリアフリー空間を提供しています。このようにして、このデザインは、販売スペース内に一種のウォークスルー形式のギャラリーを形成し、メゾンを世界でも有数の公共のアートと文化の中心地のひとつにしています。
「私たちのサザビーズ・メゾンは長い時間をかけて作り上げてきました」と、サザビーズ・アジアのマネージング・ディレクター、ネイサン・ドラヒは語ります。「香港にあるこの最先端のスペースに対する私たちの目標は、世界中の訪問者にとって文化の中心地となることです。ここは、アートと文化を愛する多くの世代の人々が集まり、素晴らしい作品や体験に触れ、インスピレーションを受ける場所です。皆さまを香港の中心にあるサザビーズで、別世界へとご案内します」
「私たちは、有名なオークションハウスを、一般の人が訪れるような場所ではない、ある種『エリート』な空間だと考えることに慣れているかもしれません」と、MVRDVの共同設立者であるヤコブ・ファン・ライスは語ります。「私たちは、一般の人々と貴重なアートコレクションとの間の障壁が再び想像され、アートが新しく大胆な形でアクセス可能になる空間を構想しました。2階は、常に変化するショーケースとなり、一般公開される唯一の期間に、個人コレクションに保管されている貴重な品々を鑑賞する機会を提供します。一方、1階の落ち着いた思索的な雰囲気は、サザビーズのキュレーションにより厳選されたアート作品と来館者が1対1で向き合う体験ができる場所であり、2階の活気あふれる雰囲気とは完全な対照をなしています」

アーキテクチャーフォトで、先週(期間:2024/8/12-8/18)注目を集めたトピックスをまとめてご紹介します。リアルタイムでの一週間の集計は、トップページの「Weekly Top Topics」よりご覧いただけます。
- 迫慶一郎 / SAKO建築設計工社による、福岡市の集合住宅「福岡モノクローム」。中高層建築の密集地での計画。現代の“バルコニーの空間的役割”を主題とし、開放率と量塊の操作でバルコニーを“半室内化”して“内部空間の延長”として使える建築を考案。白と黒の配色で立面に“抽象性”も付与
- 岩岡竜夫+森昌樹+横尾真による、長野の「松本三の丸スクエア」。 城下町の中心部での診療所付き戸建住宅の建替。用途に応じて“診療棟・住居棟・倉庫棟”の3つの建物に分け、相互隣接する配置として“街中のコア”となる“小広場”を創出。既存庭のランドスケープも継承して造る
- 藤原・室 建築設計事務所による、静岡・湖西市の「湖西の家」。住宅街に建つ四人家族の為の住まい。“視覚的に奥行きが感じられる空間”を目指し、各個室をずらして積み重ねた上に“大屋根”を被せる構成を考案。其々の間に生まれる隙間が繋がり“気配”の感受も可能にする
- BIG+ARTS Group+Frontによる、中国の「蘇州現代美術館」。2025年の完成に向け建設が進められる施設。地域の豊かな庭園遺産への“トリビュート”を意図し、伝統要素“廊”を参照して小路からパヴィリオンに連続する構成を考案。展示内容に応じて柔軟に経路の変更も可能
- 佐々木翔 / INTERMEDIAによる、福岡・那珂川市の「福岡ピノキオこども園」。人口増加が進む地域での定員数が多めの施設の計画。クラスの異なる園児同士の交流促進を意図し、教室間に“公共空間”の様な“ランチルーム”を設ける構成を考案。中庭ではレベル差を操作して上下階の連続性も作る
- +ft+ / 髙濱史子建築設計事務所による、東京・千代田区の「ジンズホールディングス東京本社」。解体が予定されるビル全体を改修した社屋。“ベンチャー魂”を取戻す存在を目指し、“壊しながら、つくる”と“美術館×オフィス”を理念とする設計を志向。働く人に参加を促すと共に感性を刺激する空間を作る
- 小嶋伸也+小嶋綾香 / 小大建築設計事務所による、東京・渋谷区の店舗「ORCIVAL」。フランス発祥ブランドの日本旗艦店。製品特長の“心地良い世界観”に来訪者の気持ちを誘う為、天然木の風合いもある“波が打った様な形状”の天井を備えた空間を考案。30mm幅の木板を用いて職人の手仕事で作る
- 池田隆志+池田貴子 / design itによる、京都市の「金閣寺東の町家」。京町家を在宅勤務の施主の為に改修。かつての“職住一体の豊かさ”も継承する為、既存空間の“役割”を可能な限り残す設計を志向。原型を留めない土間だけは新たな場として“モルタルで包まれた”リビングとする
- office one sensesによる、台湾・台北市の、仮設パヴィリオン「林木林」。美術館の屋外広場での計画。“強い日差し”と“シンプルな空間秩序”が特徴の広場に対し、25本の“木のような柱”と“軽やかな覆い”で作る建築を考案。訪問者に“広い日陰”と“精神的な内省を促す体験”を提供
- 平田晃久の練馬区立美術館での建築展「平田晃久―人間の波打ちぎわ」の会場写真。模型・スケッチ・インスタレーションを通して、平田建築を包括する新しい言葉“波打ちぎわ”を体験的に理解できる空間を提示
- 土浦亀城邸の復原と移築が完了。東京都指定有形文化財に指定された住宅。安田アトリエが建築と監理を手掛け、東京の“ポーラ青山ビルディング”の敷地の一角に移築。綿密な調査により“色彩の再現”と“家具の復刻”も実施
- 八木敦之 / アトリエMEMEによる、神奈川・横須賀市の「KDU キャンパスセンター」。大学構内の事務機能と学生の居場所を複合した施設。“広場のような空間”を目指し、“柔らかな雲の様な屋根”の下に“様々な憩いの場”が存在する建築を考案。周辺と融合する外構計画で“迎え入れる”空気感も作る
- 吉田昌弘 / KAMITOPENによる、大阪市の店舗「parlor_hana bySN 大丸梅田店」。有機栽培の果物等を使うスイーツの店。サステイナブルとブランドイメージの両立を求め、生花ではなく“リサイクル可能”な“紙素材のフラワーアート”を用いた什器を考案。アーティストの福田紗由美と協働して作る
- 中西昭太建築事務所による、石川・金沢市の「House in Wakakusa」。年間を通して天候不順の多い地域での計画。脱炭素時代の“自然密接型住宅”の実例を目指し、“三層吹抜けの最上部”に“採光窓を集中的に配置”する構成を考案。高い断熱性能に加えて光や風と共にある生活を実現
- 石上純也建築設計事務所による、山口の「House & Restaurant」。旧知の友人の為の住宅兼店舗。“時間と共にその重みを増していく”空間の要望に、地面に穴を掘りコンクリートを流して土の中の躯体を掘り起こしガラスを嵌める建築を考案。不確定要素を許容し使い方の発見更新を繰り返して作る
- アーティスト塩田千春の、大阪中之島美術館での展覧会「塩田千春 つながる私(アイ)」の入場チケットをプレゼント。新作のインスタレーションを中心に絵画・ドローイング・映像なども展示。出身地大阪での16年ぶりの大規模個展
- 最も注目を集めたトピックス[期間:2024/8/5-8/11]
- 隈研吾が、自転車の廃材を利用してファサードを構成した、東京・武蔵野市の飲食店「ハモニカ横丁 三鷹」の写真
- へザウィック・スタジオによる、韓国・ソウルの商業施設「ハンファ・ギャラリア」。従来の百貨店の概念に挑戦もする計画。歴史的に“内向的”になる用途の傾向に対し、建物周辺や中間階に“公共スペース”を備える建築を考案。“波打つ砂時計”の様な形は地域のゲートウェイとしての存在感も意識
- 藤本壮介へのインタビュー動画。建築家になる前のモラトリアム時代を語る内容。2024年8月に公開されたもの
平田晃久が、練馬区立美術館での自身の展覧会「平田晃久―人間の波打ちぎわ」を解説している動画です。2024年8月に公開されたもの。展示空間に合わせて4つの動画が公開されています。また、アーキテクチャーフォトではこの展覧会の様子を特集記事として公開しています。展覧会の会期は2024年9月23日まで。
以下にその他の3つの動画も掲載します。


都市も地方も、働くも暮らすも“オモシロく”する「株式会社ヒトカラメディア」の、空間デザイナー・設計スタッフ・CADオペレーター募集のお知らせです。詳しくは、ジョブボードの当該ページにてご確認ください。アーキテクチャーフォトジョブボードには、その他にも、色々な事務所の求人情報が掲載されています。
新規の求人の投稿はこちらからお気軽にお問い合わせください。
トカラメディアは「『都市』も『地方』も『働く』も「暮らす』も もっとオモシロくできる!」というビジョン、そして「熱源を、ともにつくる」というバリューを掲げ、場づくりを中心として、クライアントの「実現したい状況づくり」に伴走する共創カンパニーです。
「みんながいきいきと働けるオフィス移転をしたい」「新しいまちづくりのアプローチを仕掛けたい」「地域に若い企業のコミュニティを作りたい」など、様々な要望を起点として、物件選定・提案から空間デザインや内装施工、その後の施設のコミュニティ醸成や管理など、トータルでプロデュース・マネジメントを手掛けており、様々な“最良の働く場”を実現しています。
【プロジェクト事例】
・フルリモートからハイブリッドへ。働き方を選べるオフィス
・誰かの“やってみたい”が街とつながるワークプレイス『SYCL by KEIO』
・“働く”を加速させるレンタルスペース+オフィススペース『新宿ワープ』
・すこやかに働くためのシェアオフィス『Kant. co-office』
・ゼロからの繋がり・広がりを築ける会員制シェアオフィス『WAW 赤坂第35興和ビル』
・「アクセントになる居場所」がコンセプトの商業施設『OTOWA FOOD HALL SHiiiTO』あなたも色々な最良の“働く場”や“暮らす場”を、私たちと一緒につくり上げていきませんか?



藤原・室 建築設計事務所が設計した、静岡・湖西市の「湖西の家」です。
住宅街に建つ四人家族の為の住まいの計画です。建築家は、“視覚的に奥行きが感じられる空間”を目指し、各個室をずらして積み重ねた上に“大屋根”を被せる構成を考案しました。また、其々の間に生まれる隙間が繋がり“気配”の感受も可能にしています。
静岡県湖西市の住宅街に建つ、夫婦と子供2人の家族の住まいです。
部屋は小さいながらも各スペースがどこかでつながり、それぞれが見え隠れし先を想像させるところに住みたい、という希望でした。その他、木彫りの熊が飾れるような家にしたい、ファサード部分もある程度は道路側に開けてほしい、キッチンは閉じつつも家の中心で家族の気配を感じるようにしたい、家の中をぐるっとまわれる、傾斜屋根のある外観、という希望もありました。
そのような条件から、内部にズレを発生させることによって立体感が発生し、時間帯によって光のあたり方が変化してくことで、視覚的に奥行き感が感じられる空間をイメージしました。
実際は、個室のボリュームをそれぞれずらしながら積み重ねて配置し、そこに大屋根と外皮壁を被せることで、個室と屋根の間、個室と外皮の間に隙間を発生させています。各スペースそれぞれに開口部も加わり、こじんまりとしつつも、他の空間とはどこかでつながりあい、家の中に空間的な広がりや、見えないスペースの気配を感じるように考えています。


東京とドバイを拠点とし、国内外で様々な建築を手掛ける「waiwai」の、設計スタッフ(既卒・経験者・2025年新卒)募集のお知らせです。詳しくは、ジョブボードの当該ページにてご確認ください。アーキテクチャーフォトジョブボードには、その他にも、色々な事務所の求人情報が掲載されています。
新規の求人の投稿はこちらからお気軽にお問い合わせください。
waiwaiは、山雄和真とWael Al Awarの2人のパートナーが率いる、東京とドバイを拠点とする建築設計事務所です。
東京とドバイを拠点としながら、日本国内をはじめ、中東・アジア・アフリカの様々な国や地域において幅広い設計・デザイン業務を手がけています。ベネチア・ビエンナーレ国際建築展で金獅子賞を受賞したUAEを中心とした新素材および空間モデル開発、北海道ニセコでの継続的なまちづくりなど、建築を軸とした国内外の各地域における真にサステナブルな文化の創造と継承を目指し、建築家のひとりよがりではなくプロジェクトに関わる全ての人にとっての作品となる建築づくりを目指しています。
ひとつひとつのプロジェクトが真に求めているものを様々な角度から分析し、「そこにしかない物語」を構築することによって、関係者全員の意思共有を図るとともに、その都度全く異なったデザインを行うことを信条としています。
現在進行中のプロジェクトに、数万㎡規模の美術館・アートギャラリーやホテル、大規模住宅地開発、数千㎡規模のホテル・ヴィラ/別荘・商業施設・福祉施設等々、多種多様なプロジェクトが動いています。クライアントや協働する関係者も国内外多様な人々と日々関わっており、チームメンバー全員が前線に立ちますので、弊社だからこそ得られる経験があるはずです。
昨年度より、会社規模の一層の発展を目指した組織改編を行っています。中東地域を中心とする海外プロジェクトにおいても日本チームとドバイチーム双方で携わり、すべてのチームメンバーが、国内外双方のプロジェクトに関わる機会があります。本年度よりランドスケープとインテリアデザインの部門を設立し、建築を軸にした、建築プロジェクト全般を手掛ける総合デザインファームとしての展開を目指しています。
今年度は特に組織力強化のため、プロジェクトチームを引っ張っていってくれる建築実務経験者を主とするメンバーを募集します。私たちwaiwaiでしか得ることのできない経験を元に、他にないチームを共に作り上げていく仲間を募集します。
大きな視点で様々なプロジェクトに共に挑戦してくれる方の応募をお待ちしています。