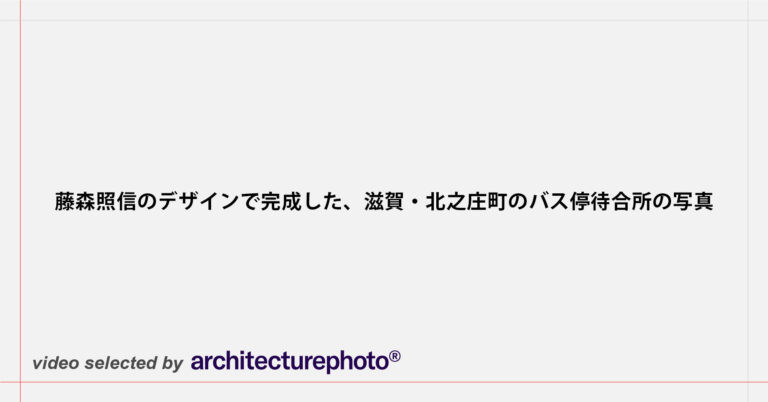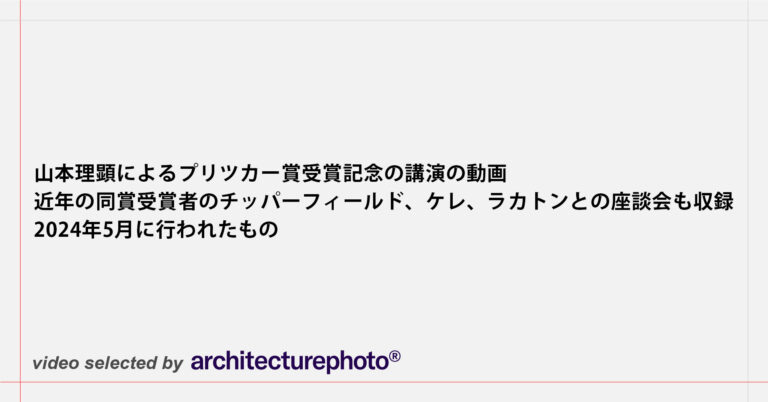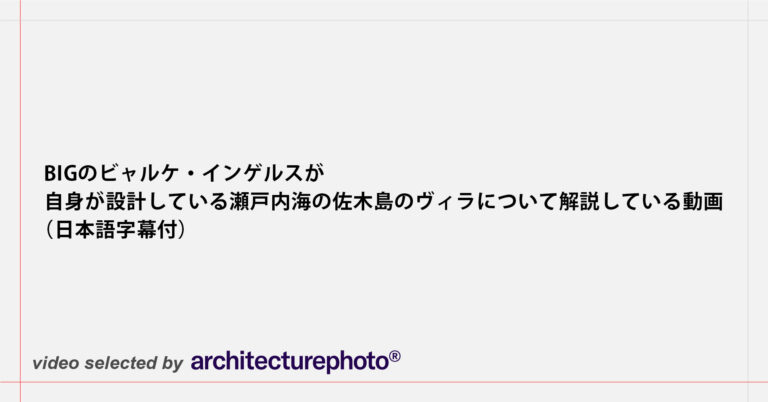藤森照信のデザインで完成した、滋賀・北之庄町のバス停待合所の写真が5枚、滋賀県のサイトに掲載されています。藤森による建築があるラ コリーナ近江八幡の最寄りのバス停の様です。
architecture archive




アリソン理恵 / ARAが設計した、東京・渋谷区の「奥の住まい」です。
路地の“更に奥の路地”の先に建つ住宅の改修です。建築家は、暮らしの様々な出来事の“受け皿”として、日当たりや風通しが良く“家族や暮らしのかたち”と共に変化できる空間を志向しました。また、住人自身での改変の容易さも予め考慮されました。
商店街を抜けて、舗装されていない路地のさらに奥の路地を入った奥の方に建つ住宅の改修。
既存の敷地や、木造の架構をめいっぱいつかって、日当たりと風通しがちょっとよくなるように手を入れ、構造と断熱の補強をして、設備を入れ替え、暮らしにまつわる様々な出来事を受け止める受け皿としての住まいを整えた。
町に住むということは、寝て起きて食べるという最低限の行為をこえて、仕事したり遊んだり、家事をしたり、物の手入れをしたり、庭仕事したり、人をよんだり、様々な営みの総体であり、住まいもそういった様々な場面を実現するしつらえをもつべきだと思う。
常に変化する家族のかたちや暮らしのかたちと共に変化していけるよう、一階にはテントの庇のある明るい外室と、広間と水廻り、回遊性のあるワーキングスペース、二階にはいくつかのポケットのような、小さな居場所となるアルコーブと大広間というわかりやすい間取りとした。




長岡勉 / POINTと山本稜 / Spicy Architectsのデザイン監修による、埼玉・本庄市の「埼玉グランドホテル本庄」です。
バブル期の宿泊施設の改修計画です。建築家は、個性ある仕上げ同士が“魅力を打ち消し合う”現状に対し、其々の関係を整理し“新たに定義”する設計を志向しました。そして、床から2.1m以上を“マット”仕上げとして既存の“ピカピカ”を引立てることが意図されました。施設の公式サイトはこちら。
二つ以上のモノごとの関係を新たに定義すること。突き詰めると空間設計とはこのことの連続であると思う。
80年代のいわゆるバブルの時代に建てられたホテルのリノベーションのデザイン監修と家具の設計を行った。
既存の建物の仕上げは、石が貼られ、シャンデリアが吊られ、金色のメッキがされた派手な天井など、80年代という時代背景を反映した設えをしていた。それらは、単体では手間をかけられ個性があるのだが、それらが全て現れると、その個性がぶつかりあい、魅力を打ち消しあっていると感じた。なのでそれらを整えることで、魅力ある個性を引き出すことにした。
基本的な内装仕上げは磨かれている。石も磨かれているし、金属も磨かれている。それらピカピカに磨かれたアイテム同士が喧嘩してる状態を調和するように、床から2100mm以上の壁と天井を全てマットでの吹き付け仕上げとした。ピカピカを引き立てるザラザラ。
こうすることで、2つの質が調和した心地よい空間の背景が出来上がった。そこに、古いモノと新たに加えられるモノとの関係を、時には対比的に時には韻を踏むように同調させながら、お互いの関係が魅力的に引き立て合うように、家具や仕上げを決定して行った。具体的には以下となる。




中村拓志&NAP建築設計事務所が設計した、千葉・木更津市の「地中図書館」です。
農業生産法人が運営する施設内での計画です。建築家は、植物や微生物の反映の下にある“慎ましい”存在を求め、大地の下に“やすらかな居場所”を志向しました。施設の公式サイトはこちら。
晴れた日には畑を耕し、雨の日には読書をする。「地中図書館」はそんな人のためにある。
敷地は農業生産法人が運営するKURKKU FIELDSの一角にある。その平坦で乾いた土地は、建設残土で埋め立てられた谷の上にあった。
われわれは、農夫たちがマザーポンドと呼ぶ池に至る、緑豊かな谷筋を復活させること、そして建築は作土層を占有するのではなく、植物と土中微生物たちの繁栄の下に慎ましく存在するべきだと考えた。大地はあらゆる生命の源、母性の象徴として捉えられてきた。その大地に割け目を設けて、そこに耕す人の休息にふさわしい、やすらかな居場所をつくりたいと考えた。
その割け目は上空から見ると雫のような形をしている。歩いているうちにいつの間にか迷いこむようなアプローチを抜けて作土層をくぐると、本棚のコリドーがある。梁や柱といった建築的要素が排除され、外周部の土留め壁と袖壁からコンクリートボイドスラブが片持ちで跳ね出している。
床と壁、天井は土仕上げでなめらかに繋がり、スラブ小口の鉛直面まで植え込まれた芝がモサモサと下垂し、空間に湿り気を与えている。これは灌水と保水のバランスを季節によって調節可能なディテールとなっている。
内部の天井高は大地の傾斜に応じて決まるため、子どもしか入ることのできない天井の低い場所や小さな隠れ部屋がある。最深部には、読み聞かせのためのホールがある。芝の大地を大きく孕ませた子宮的空間には、階段状の席を本棚の襞が取り囲み、農園で働く人たちの蔵書や子どものための本が並ぶ。

ル・コルビュジエの“美術作品”に焦点をあてる展覧会「もうひとりのル・コルビュジエ ~絵画をめぐって~」の入場チケットを抽選でプレゼントいたします。
近代建築を代表する建築家の油彩・素描・版画・タピスリー・彫刻など約130点の作品が展示されます。創作活動の根底にあった絵画への情熱を紹介する内容です。また、まとまった作品群の公開は約30年ぶりとのこと。
会期中には、古谷誠章、藤井由理、青木淳、加藤道夫、中村研一、隈研吾が其々に参加する講演会も企画されています。加えて、ギャルリー・タイセイ林美佐によるギャラリートークも計4回行われます。
会期は、2024年6月25日~2024年8月12日。会場となる大倉集古館の公式サイトはこちら。入場チケットプレゼント企画の応募締切は、2024年6月17日(月)13時まで(お申込みにはGoogleアカウントが必要になります)。こちらのフォームからご応募ください。厳正な抽選を行い当選された方にはメールにてご連絡いたします(メール送付を当選発表にかえさせていただきます)。
「私の探求や知的生産の根底の秘密は、絶え間ない絵画実践のなかにあるのです。」※
フランスを拠点に活動した建築家ル・コルビュジエ(1887~1965)は、7か国にある17資産がユネスコの世界文化遺産に登録されるなど、20世紀を代表する重要な建築家として高く評価されていますが、同時に数多くの美術作品を残したアーティストとしても知られています。
本展では、世界有数の所蔵作品をもつ大成建設ル・コルビュジエ・コレクションの中から約130点の作品を展示することで、ル・コルビュジエの美術作家としての側面をご紹介いたします。
本コレクションの素描やパピエ・コレ作品がまとまって公開されるのはおよそ30年ぶりのことです。本展をご覧いただくことで、建築を含めたル・コルビュジエのすべての創作活動の根底にあった、彼の絵画への情熱に気づいていただけることと思います。
※(“Le Corbusier Lui Meme”(『ル・コルビュジエ みずから語る生涯』 P250)
以下に、写真と詳細な情報を掲載します。




玉木浩太+ジュリア・リ・カ・イー+林盛 / HUNE Architectsが、共用部の内装設計を手掛けた、東京・北区の集合住宅「HAUN TABATA」です。建物自体の設計は一級建築士事務所エスが担当しています(詳細なクレジットは末尾に掲載)。
居住と作業空間を併せ持つ“コリビング賃貸”の計画です。建築家は、様々な行為が重なる場として、箇所毎に異なる役割を果たす“センターテーブル”を据えた空間を考案しました。また、再生材料の特徴を活かして家具類に“鉱物”の様な質感も与えました。施設の公式サイトはこちら。
現代社会では「住む」ことの多様化によりホテルやシェアハウス、マンスリー賃貸、サービスアパートメントなど住むための形やサービスも多様化しています。
その中で、「コリビング賃貸」は、家具を設けた専有部と、リビングとワーキングスペースが一体となった共用部からなるサービス賃貸の形式です。住まうためのレジデンスと仕事や作業をするためのワークスペースの二つの特徴を併せ持った住居形態として、コロナ以降、自宅で仕事をする機会が増えた人たちに注目されています。
田端のコリビングは、各約15㎡・61住戸の専有個室と共用のリビング「コリビング空間」、ランドリー、パントリー、1階共用部からなります。備え付けのベッド、デスク、洗面カウンター、シャワーユニットが備え付けられた専有部個室の面積を最小限に抑え、キッチンとリビング、ワーキングスペースからなるコリビング空間を充実させることが施設のコンセプトになっています。
4階建ての建築を10mの高さ制限に収めるため、1階のコリビング空間は地盤面よりやや下がっています。
リビングの入り口から少し下がることで、落ち着いた場所性が生まれると考え、この高低差を生かした計画にしたいと考えました。限られたスペースの中で、南側に開いた間取りであることと、様々なアクティビティが共存することを活かすために、できるだけ共用部を区切ることのない1室空間としています。このシンプルで小さな一室空間の中で、リラックスできる場所、料理を作る場所、くつろぐ場所、明るく話が弾む場所、集中する場所、様々な行為が重なる場所を作りました。
西側をくつろぐための小上がり空間とし、東側を4か所同時に使えるキッチンカウンターとして、これらの二つの場所をつなぐように空間の中央にセンターテーブルを配置しました。センターテーブルは小上がりのローテーブルとなり、中央ではダイニングテーブルであり、キッチンのための作業台でもあります。様々な行為が同時多発的に発生する場所です。
空間の中心となるセンターテーブルや、窓際のワーキングデスク、プランター等の家具は、産廃パーチクルボードを使用して製作しました。パーチクルボードは使用済みのパレット、廃棄される梱包用資材、型枠合板などの木質系の素材を、木片やカンナくずにまで砕き、接着剤によって固めることでボードとする再生材料です。建築の現場では家具や建築用の床などの下地材として広く使われており、廃棄木材から作られていることから建設業における資材の再資源化にも大きく貢献しています。



杉中俊介+杉中瑞季 / 多和良屋と清水良太構造デザインスタジオが設計した、東京・世田谷区の「上馬の家」です。
構造家の自邸兼仕事場の計画です。建築家は、住宅密集地に建つ住宅として、シンプルな“外殻の中”に“ひだ”の様に諸室を“折り重ねる”構成を考案しました。そして、周辺環境との関係構築も意図してバルコニー等から内部の雰囲気を滲み出させています。
住宅密集地のなかに建つ、構造家の自邸兼仕事場。
斜線規制を可視化するように立ち上げた単純な外殻のなかに、襞のように室を折り重ねている。それらを縫うように開口を穿ち、空間を繋ぐことで、光と風が通り抜け、空気を共有し、奥深さと明るさを両立している。
決して広くはない床面積のなかで、段差を上下する動きや異素材による触感の違い、視線の移動や明暗の変化など、細やかな差異とそれを潜り抜ける反復を通して日常の生活を構築していくことを意図している。
T字路に面するという敷地条件のもと、ピロティやバルコニー、ルーフテラスにより、外殻を刳り貫くことで外の風景を引き込み、道路面でそれぞれの室の雰囲気を滲み出させることで、周辺環境との関係を結んでいる。




山口誠デザインが設計した、東京・台東区のオフィスビル「MONOSPINAL」です。
ゲーム制作会社の本社として計画されました。建築家は、従業員の“集中力”と“リラックス”のバランス確保を目指し、環境要素も向上をさせる“斜壁”を持つ建築を考案しました。また、小スケールの素材を集積をさせる仕上げで“あらたな風景”を作る事も意図されました。
アーキテクチャーフォトでは、2023年1月に建設中の状態でも本作品を紹介しています(本記事は竣工写真を用いて新たに構成されています)。また、本建築をテーマとした展覧会が2024年5月25日まで開催されています(記事の末尾に情報を掲載します)。
東京に本社を置くゲーム制作会社の本社ビル移転計画である。
世界中のファンを魅了している最高レベルのクリエイションを、これからも生み出し、ゲーム制作の根幹を支え続ける場所となることを目的に計画された。
ほぼ全ての社員がクリエイション業務に専ら携わっているため、彼らの集中力とリラックスのバランスを確保し、煩わしい運用業務の負担を著しく軽減させたいと考え、計画の重点をそこに置いた。外観を特徴づける建物周囲にめぐらされた斜壁と、セキュリティを含めて全ての設備をタブレットで制御できるシステムを導入することで、それを実現しようとしている。
なお外構・内外装仕上げ・備品などは、ゲーム作品の設定(時代・地域・登場人物・アイテムなど)をメタファーとして取り込んでいる。それらは作品をよく知っていれば読み解くことが可能であり、この本社ビル自体がゲームでできているとも言える。
計画地の正面には高架線路が走り、上下線合わせれば平均1.5分おきに電車が通過している。また、多種多様なテナントの入った小規模な雑居ビルに取り囲まれた場所である。斜壁は光・風・音の環境要素を向上させているが、その高さは階ごとに変わる用途に合わせて適正化させている。

アーキテクチャーフォトで、先週(期間:2024/5/13-5/19)注目を集めたトピックスをまとめてご紹介します。リアルタイムでの一週間の集計は、トップページの「Weekly Top Topics」よりご覧いただけます。
- 熊谷・石上純也・IAO竹田・アクト環境・ピーエス三菱・野村建設JVによる「徳島文化芸術ホール(仮称)」の実施設計概要
- SALHAUSの提案が最優秀賞作品に選ばれた、共愛学園前橋国際大学の「6号館設計者選定プロポーザル」の提案書が公開
- 木村智彦 / グラムデザインによる、島根・松江市の「雑賀の家」。家族四人と猫の為の計画。着心地の良い“衣服の延長”の様な住宅を目指し、自然環境に従って光と風を取込む“適切な熱環境の生活の場”を志向。家族の気配を常に感じ取れるように“距離感”と“設え”にも注力
- 山下貴成建築設計事務所による、静岡・御殿場市の「高嶺の森のこども園」。森の中の起伏に富む地形の敷地。各年齢の子供達の生活が“同時に満たされる”在り方を求め、周辺環境に応じて8つの部屋を“円環状”に配置する構成を考案。地形と呼応し“湾曲する”屋根で全体を緩やかにまとめる
- ザハ・ハディド・アーキテクツによる、ラトビア・リガの交通施設「Riga Ropax Terminal」。既存の船舶倉庫を改修増築して船舶のターミナルにする計画。未来に渡る市民の憩いの場として、最上部に一層を追加して作る“パブリックテラス”などを構想。歴史に敬意を表して現地生産のタイルなども外観に用いる
- 岸本貴信 / CONTAINER DESIGNによる兵庫県高砂市の住宅「プラットホーム」
- VUILDによる、香川の「小豆島 The GATE LOUNGE」。オリーヴを用いた商品の購入や体験ができる施設。木造建築の“新しい建造の在り方”の提案として、島内の木材を資源として活かす仕組みから構築。デジファブ技術を用いて熟練大工に頼らない施工体制も追求
- 石上純也建築設計事務所による、山口の「House & Restaurant」。旧知の友人の為の住宅兼店舗。“時間と共にその重みを増していく”空間の要望に、地面に穴を掘りコンクリートを流して土の中の躯体を掘り起こしガラスを嵌める建築を考案。不確定要素を許容し使い方の発見更新を繰り返して作る
- パナソニック汐留美術館での「ポール・ケアホルム展 時代を超えたミニマリズム」の入場チケットをプレゼント。“ミニマルで清潔な造形”を特徴とする家具デザイナーの作品群を紹介。日本の美術館では初めてとなる“主要作品を網羅”した展覧会。会場構成は建築家の“田根剛”が手掛ける
- 藤本壮介・永山祐子・成瀬友梨が審査する、ケイミュー主催のアワード「ARCHITECTURAL DESIGN AWARD 2024」が応募作品を募集中。ケイミュー商品使用物件を対象に“未来に残していきたい外装デザイン”を選定し表彰。受賞者には永山作品の“東急歌舞伎町タワー”での表彰式と“総額185万”の商品券を用意
- 伊瀬和裕 / テトラワークスによる、広島・百島の、宿泊施設「瀬戸内隠れ家リゾート AMERI」。離島の海辺近くに建つ“一棟貸しの宿”。風景への眺望の最大化を意図し、床レベルを上げた“眺望室”を備えた建築を考案。本体から跳ね出した眺望室は外観を“アイコニック”にする役割も担う
- 佐藤文+鹿嶌信哉 / K+Sアーキテクツによる、栃木の「足利の家」。史跡の残る街の長閑な住宅街の敷地。繋がりながらも間仕切れる状態を求め、施主が求める“断片的な居場所”を環境に合わせながら繋げていく平面構成を考案。周囲への開き方も意識して街と繋がる庭を設ける
- 廣部剛司建築研究所による、千葉・南房総市の「VILLA MKZ」。岩盤の露出等がある“複雑な条件”の土地。条件の間を“縫うような”計画を行う為、三角形を連続させた平面をベースとした“可変の余地を内包する”方法論で設計。海を向く諸室が“折れ曲がり”連続する空間を作る
- あとりえ・楠本構造設計・Awwによる、茨城・つくば市の「茗溪学園 トレーニング・部室棟」。教育機関のキャンパス内での計画。海外の来客や留学生も多い学校の特徴を考慮し、日本の代表的工法“木造”でつくる大空間の建築を志向。校舎と運動場の間という立地も考慮して“視線が抜ける”形態とする
- 岸和郎+K.ASSOCIATES/Architectsによる「HOUSE WITH THREE COURTYARDS」の写真。2023年3月竣工の建築
- 岡田宰 / 2id Architectsによる、静岡・浜松市の店舗「PAO」。飲食店と物販店からなる計画。人・地域・文化を包む拠点を求め、ホールを中心に全ての店舗を配した“新たな出会いへと繋がる”空間を志向。其々のカウンターには街の“レトロさ”と呼応する“タイル”を用いる
- 妹島和世の監修によるパヴィリオンが造られた「PERPETUAL MOMENT − 自然の中の時間」。東京都庭園美術館を会場とし日本ロレックスの主催で開催。名和晃平・目・小牟田悠介の作品も展示
- 隈研吾が出演したテレビ番組「情熱大陸」が、期間限定で無料オンライン配信中
- 藤森照信による講演「村野藤吾と八ヶ岳美術館」の動画。2024年4月に行われたもの
- スノヘッタによる、東京・原宿の店舗「Tokyo Burnside」
山本理顕によるプリツカー賞受賞記念の講演の動画です。近年の同賞受賞者のデイヴィッド・チッパーフィールド、フランシス・ケレ、アンヌ・ラカトンとの座談会も収録されています。2024年5月17日に、イリノイ工科大学のミース設計のクラウンホール行われたものです。
BIGのビャルケ・インゲルスが、自身が設計している瀬戸内海(広島県)の佐木島のヴィラについて解説している動画です。NOT A HOTELの為に設計している建築です。
世界的建築家ビャルケ・インゲルス率いるBIGが瀬戸内海に浮かぶ離島・佐木島を舞台にデザインするのは、日本の風土と伝統建築、そして“角度”にインスパイアされた3つのヴィラ。



熊谷・石上純也・IAO竹田・アクト環境・ピーエス三菱・野村建設JVによる「徳島文化芸術ホール(仮称)」の実施設計概要です。
2024年4月26日に公開された内容を許可を得て掲載します。
旧徳島市立文化センター跡地等を計画地とする「徳島文化芸術ホール(仮称)」について、実施設計の成果を概要版としてとりまとめました。内容は、施設構成、平面図、立面図、パース図などとなっています。
以下に図面等も掲載します。


地域や都市に繋がる建築を志向し、暮らしや社会に新しい価値をつくる「須藤剛建築設計事務所」の、設計スタッフ(2024年新卒・既卒・経験者)募集のお知らせです。詳しくは、ジョブボードの当該ページにてご確認ください。アーキテクチャーフォトジョブボードには、その他にも、色々な事務所の求人情報が掲載されています。
新規の求人の投稿はこちらからお気軽にお問い合わせください。
株式会社須藤剛建築設計事務所は、設計スタッフを募集しています。
【私たちの事務所について】
私たちは、地域文化を大切にし、暮らしや社会に新しい価値をつくることを目指して建築設計を行っています。
建築の企画や事業計画など、建築の枠組みや建築設計の前後にかかわることで、能動的に設計活動に取り組むことを大切にしており、多くの建築雑誌やwebなどメディアでもその取り組みについて取り上げられています。また昨年末に事務所を移転し、事務所に併設して、設計活動を通して関わってきた人や店舗のつながりを活かした「店舗や飲食店やコーヒースタンドやギャラリーなどを集約した小さな地域拠点施設CaD」をこの春にオープンしました。
自社施設の企画や運営を通し、更に関係人口を増やし、都市に能動的にアクションを起こしながら建築設計を行っていきます。現在のプロジェクトは住宅、集合住宅、地域拠点施設、宿泊施設、商業施設(飲食店、複合施設など)など、多岐に渡っています。設計する建築の用途や、既製の概念にとらわれない多様な使い方やスケールの建築の設計を新築・改修を問わず行っています。様々な分野とチームを組みながら設計を行うことで、実績が増え、建築の規模も大きくなる一方、住宅や小規模な店舗なども深く取り組める体制を整えています。




VUILDが設計した、香川・小豆郡の「小豆島 The GATE LOUNGE」です。
オリーヴを用いた商品の購入や体験ができる施設の計画です。建築家は、木造建築の“新しい建造の在り方”の提案として、島内の木材を資源として活かす仕組みから構築しました。また、デジファブ技術を用いて熟練大工に頼らない施工体制も追求しました。施設の場所はこちら(Google Map)。
「小豆島 the GATE LOUNGE」が、香川県の小豆島に竣工し、オリーヴの栽培・研究開発・製造・販売を行う、店舗兼施設としてオープンした。
同施設は、製品やサービスの体験だけでなく、オリーブの栽培・搾油過程を見学し、滞在を通してオリーヴを育んだ気候・風土を五感で楽しむことができる、そんな体験に誘うはじまりの場所としてのゲートの機能と、ホストとゲスト、ゲスト同士が気兼ねなく交流できるラウンジ機能を備えている。
本プロジェクトは、設計者とクライアントが共に木造建築を作り上げる新しい建造の在り方を提案すると共に、島の資源を最大限に生かすことはもちろん、デジタルファブリケーション技術を駆使することで施工・デザインのクオリティを維持している点を特徴にしている。
小豆島は大阪から西へ180km、西日本に位置する離島である。この島で木造建築をつくる場合、島内に木材の乾燥機や加工施設がないため島内の木材は活用できず、本州から輸送しなければならないため、通常に比べコストも時間もかかるという課題がある。 そこでわたしたちは、簡易的な木材乾燥機をつくり、小型のCNC加工機を設置することで、島に現存するヒノキを資源として生かす試みから着手した。
このプロジェクトのチャレンジは、使い手のための空間のデザインや環境的なデザインをするということだけでなく、構造や壁を組み立てるための部材を、CNCマシンで加工するための切削データを正確に作成することであった。このような複雑な製作は、以前は熟練した大工のみが行っていたが、デジタルファブリケーション技術により、誰でも加工できるようになった。
基礎にはコンクリートではなく、この地方で採れる花崗岩の巨石を使用し、構造躯体に使用される700本のヒノキの丸太も、すべてこの地域で伐採されたものである。


小さなオブジェから数千㎡の建築まで、様々な規模と用途の仕事を手掛ける「kwas / 渡邉健介建築設計事務所」の、設計スタッフ(経験者・既卒・2024年新卒)募集のお知らせです。詳しくは、ジョブボードの当該ページにてご確認ください。アーキテクチャーフォトジョブボードには、その他にも、色々な事務所の求人情報が掲載されています。
新規の求人の投稿はこちらからお気軽にお問い合わせください。
kwas/渡邉健介建築設計事務所では、新規プロジェクトの受注などに伴う業務拡大のため、設計スタッフ2名程度の参加を希望しています。
kwasは代表の渡邉健介が2005年に立上げ、現在に至る建築設計事務所です。
最近の代表的な仕事としては、2023グッドデザイン賞を受賞した「KIND Center」があります。【手がけてきた仕事】
小さな単体のオブジェから数千㎡の建築にいたるまで、プログラムもスケールも違うさまざまな仕事に携わってきました。これまで関わってきた仕事に関しては、是非kwasのホームページを訪れご覧ください。kwasでは、プロジェクトの初期に入念なリサーチを遂行することで、そのプロジェクトの情報に精通し、固有の条件を洗い出すようにしています。また、要望された単体の建築を超えて、複数棟の建物の配置や道路の設計、ランドスケープに至るまでのマスタープランを行って、プロジェクトに最適な状況の提案も行っています。こうしたリサーチやマスタープランは自主的な営業としてではなく、そのものをプロジェクトに入る前の独立した仕事としてお引受する機会が増えています。
最近は建材メーカーの複数の工場においてマスタープランと、それに続く工場内の建築の設計監理、また高齢者に関係する仕事が続いているところで、時間を見つけてはコンペなどにも挑戦しています。直近では「小諸市立芦原中学校区再編に関わる基本設計・実施設計業務委託プロポーザル」において最優秀となり設計が進んでいます。
【事務所について】
東京の新宿御苑前、もしくは新宿3丁目が最寄りとなる、靖国通りに面したビルの2階に位置しています。北向きの広い窓の外に、陽の当たる街路樹を眺めながら仕事をしています。事務所周辺には美味しい店が沢山あり、昼には場所を選んでランチをスタッフと一緒に食べています。kwasでは、一旦プロジェクトがスタートすると、担当者の配置換えはほとんど行わず、初期のリサーチ、コンセプト作りから設計、現場監理までをずっと担当します。建築をつくるさまざまな局面、デザインの決定や施主との打ち合わせなど、どのように仕事がマネジメントされるかを、責任ある立場で経験することが出来ます。経験豊富な先輩スタッフの指導を受けながら、設計スキルの急成長が期待できます。
業務は朝の10時から19時までですが、繁忙期は遅くなることもままにあります。週末や祝日は休みですが、プロジェクトの都合で仕事をする際は休日勤務手当が出ます。賞与は業績にもよりますが、ここ最近は年間5~7か月分出しています。
模型と図面、CGをいったりきたり、全てのプロジェクトで可能性のある案を複数検討しながらすすめます。生みの苦しみはいつもありながら、さまざまな条件がぴたりと合うような案にたどり着いたときの喜びは格別です。建築や設計が好きで、実務を通した喜びをともにしてくれるメンバーと楽しく、設計を進めたいと考えています。