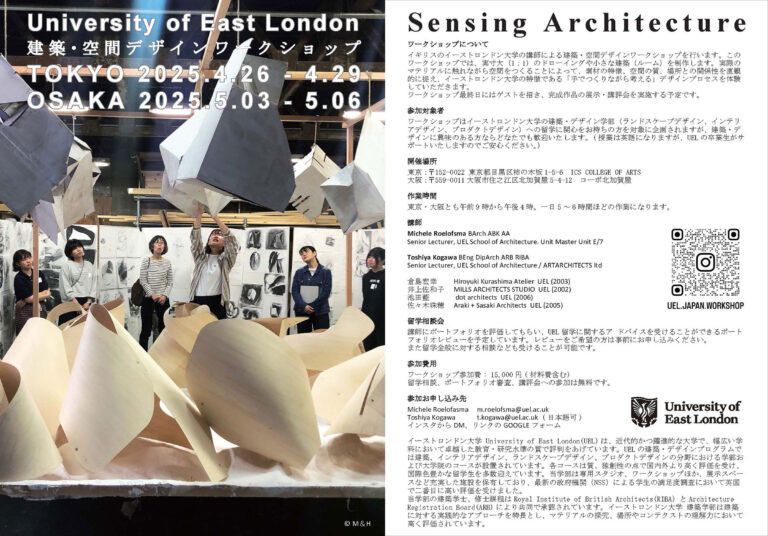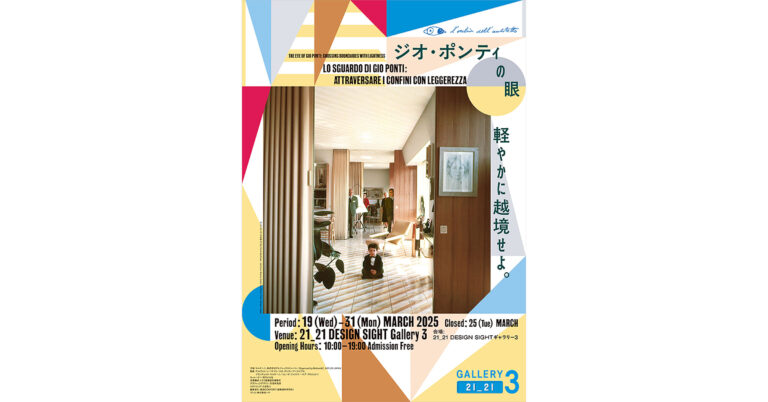注目のベンチャー企業等との協業が多く、多様なアワードの受賞歴を持つ「山路哲生建築設計事務所」の、設計スタッフ(経験者・既卒・2025年新卒)、業務委託、パート 募集のお知らせです。詳しくは、ジョブボードの当該ページにてご確認ください。アーキテクチャーフォトジョブボードには、その他にも、色々な事務所の求人情報が掲載されています。
新規の求人の投稿はこちらからお気軽にお問い合わせください。
山路哲生建築設計事務所では設計スタッフを募集しています。
【株式会社山路哲生建築設計事務所について】
隈研吾建築都市設計事務所を経て2015年に設立した山路哲生が主宰する建築設計事務所です。渋谷駅スクランブルスクエアや、中国を中心とした海外の大規模な開発に携わってきた一方、住宅やホテルの内装・家具、また小さな屋台の設計など幅広いスケールで設計をしております。徐々に活動規模が広がるこの過渡期に、一緒に計画に参加してくれる仲間を募集しています。都市部では今注目されるベンチャー企業やディベロッパーとの協業が弊社のひとつの特徴となっています。昨年5月にオープンし、380年ぶりに東寺の五重塔を超え56mの高さをもつ複合木造ビル「銀座髙木ビル」(新建築2023,12月号掲載、株式会社髙木ビル)では林野庁長官賞、ウッドデザイン賞、一連の活動において、これからの建築士賞、を受賞しています。
また、デザインコードによる新しい設計手法「ASOLIE」を株式会社ミラタップと協働開発し、リリース。現在全国約50社の施工者に参画頂いています。また弊社設計による情報発信と交流拠点「MONNAKA COFFEE」(株式会社biplane、株式会社三菱地所レジデンス)、食の体験をつくる市場「YOKOSUKA PORT MARKET」(横須賀市、いちご株式会社)、有楽町マルイにて「ORIENTAL BLUE」(株式会社biplane)などが近年オープンしました。その他「THE KNOT HOTEL」「IKE-SUN PARK」など注目の都市施設の設計に携わっています。
今まさに大きく変わろうとしている産業構造の中で、建築によって実現されるものも建築が担う枠組みも変わり続けています。建築を軸にまちづくりから家具デザインまでスケールを横断して設計に携わることで業種間における障壁を乗り越え、都市の創造と編集に挑戦しています。達成すべき目的の為に同業、異業種関わらず、様々なスペシャリストとチームをつくり協働し、既成の設計の枠組みを超えた設計手法を模索しています。
建築士としての経験・技術の習得ができるとともに、幅広い職種の方々と協働することで幅広い視点を学ぶことができます。大小様々な計画が同時進行しており、成長段階に応じた規模の計画を段階的にご担当頂きます。各人の個性を存分に発揮し、その挑戦と成長を共に楽しんでくれるベンチャー気質の明るい性格の方をお待ちしております。
代表の山路は大学講師を兼務しており、人材育成や研究・開発にも力を注いでいます。リサーチやスタディなどインプットの時間を大切にし、建築を周遊する研修旅行も毎年行っています。風通しが良く、同年代のスタッフ同士で互いに切磋琢磨できる職場環境にあります。