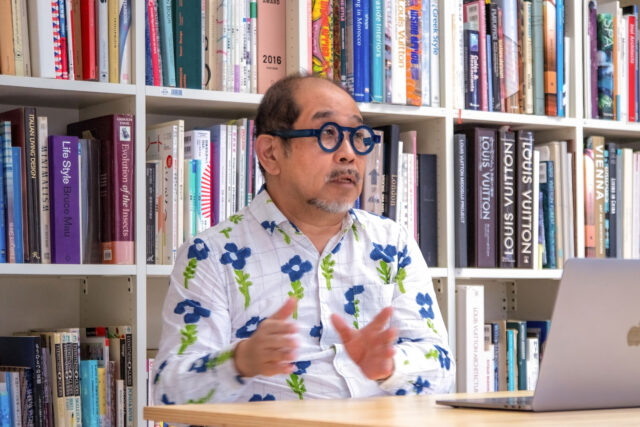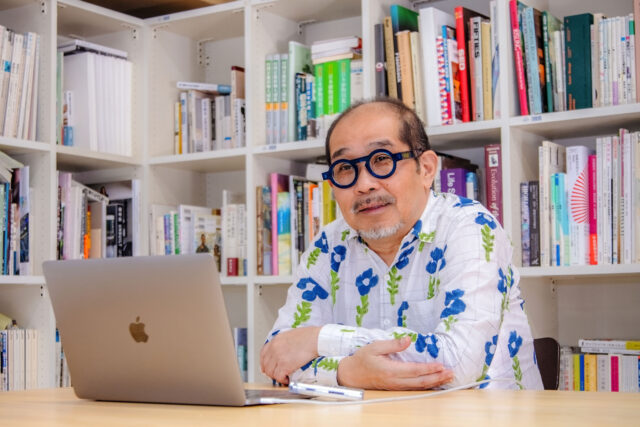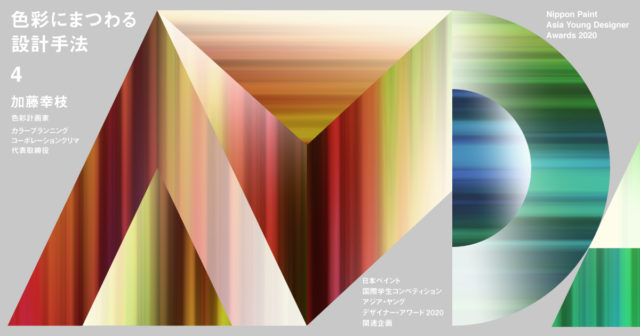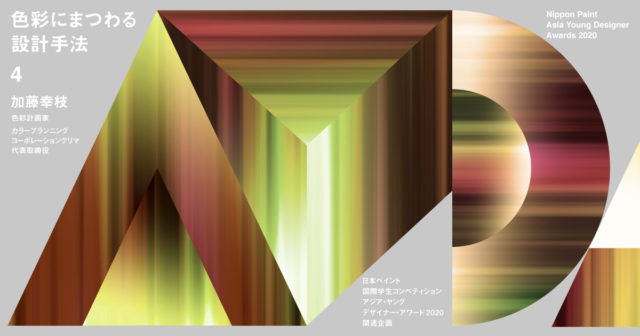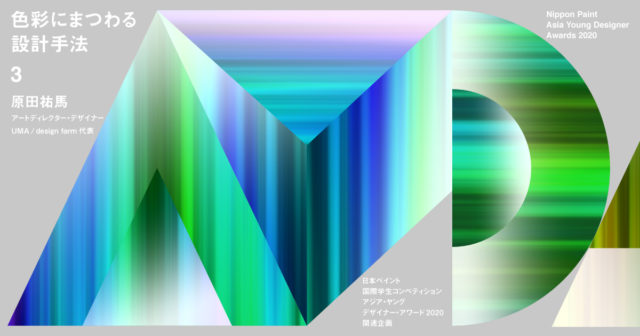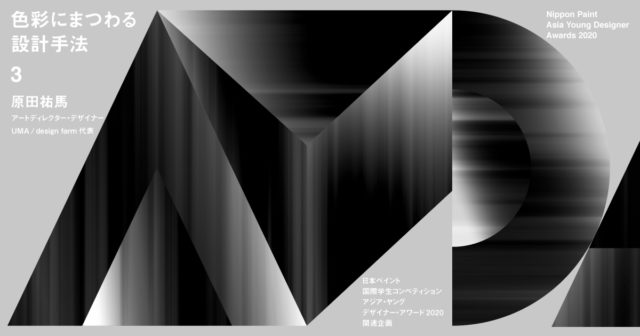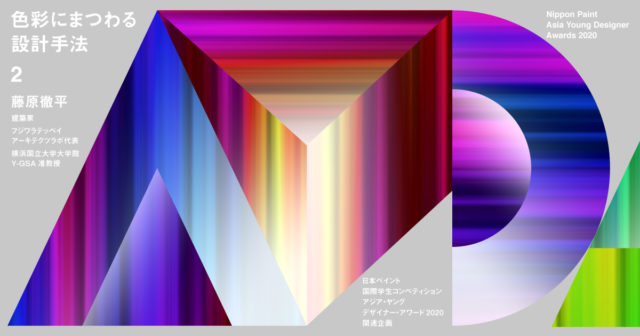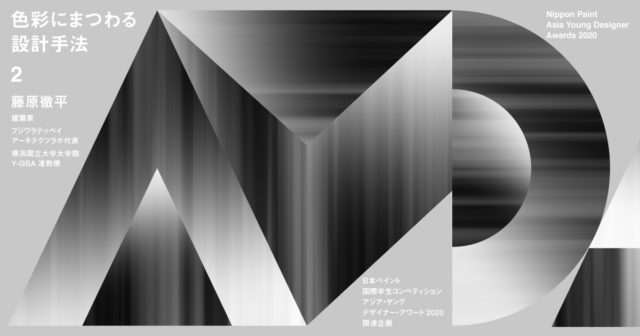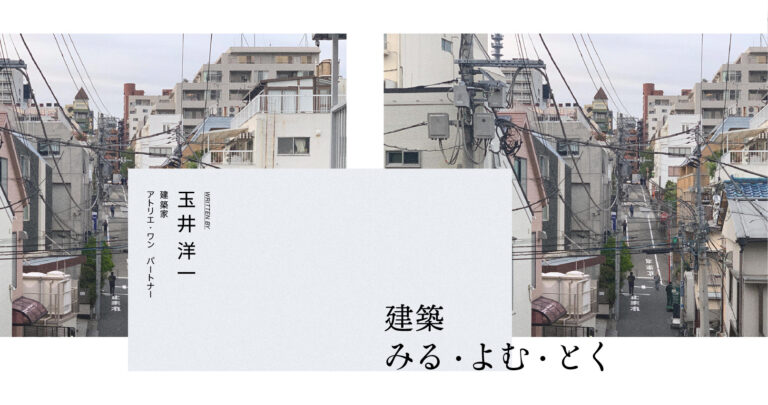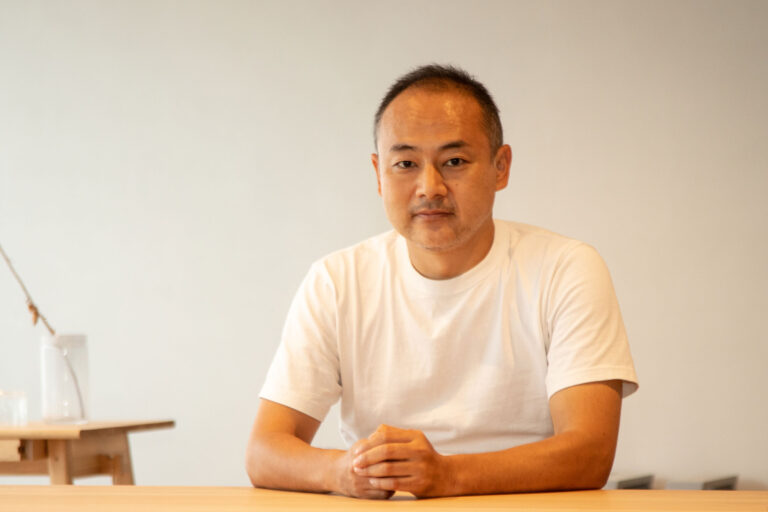
SHARE 【シリーズ・色彩にまつわる設計手法】第6回 芦沢啓治 インタビュー・前編「空間のクオリティを実現する、ニュアンスを持ったグレー塗装」

本記事は学生国際コンペ「AYDA2021」を主催する「日本ペイント」と建築ウェブメディア「architecturephoto®」のコラボレーションによる特別連載企画です。今年の「AYDA」日本地区のテーマは「音色、空間、運動」。このテーマにちなみ、現在活躍中の建築家に作例を交えながら色彩と空間の関係について語ってもらうインタビューを行いました。昨年、全4回にわたり公開された色彩に関するエッセイに続き、本年は建築家の青木淳と芦沢啓治の色彩に関する思考に迫ります。作品を発表する度に新鮮な驚きを与えてくれる二人。その色彩に関する眼差しを読者と共有したいと思います。
第6回・前編では、芦沢啓治が改修設計を手掛け2021年2月にオープンした「Karimoku Commons Tokyo」を題材に、ご自身の設計手法や色彩についての考え方を語ります。「Karimoku Commons Tokyo」は築37年の鉄骨造ビルをフルリノベーションした家具メーカー・カリモクのショールーム&ギャラリー。その室内は、塗装仕上げの内壁によって主役である展示物を魅力的に見せ、なおかつ心地よい緊張感をもたらす上質な空間となっています。はたして、いかなるプロセスで壁面の色を決めたのか。また、空間のデザインにおいて何を重視しているのか。建築設計やインテリアデザインを志す方々には必読の内容となっています。
※このインタビューは感染症予防の対策に配慮しながら実施・収録されました。
空間全体のハーモニー

――塗装といえば白を選ぶ建築家が多いと思うのですが、芦沢さんは幅広いグレー系統の色を場所ごとに巧みに使い分けている印象があります。なかでも2021年2月にオープンした「Karimoku Commons Tokyo(以下、Karimoku)」の内壁は、3フロアともグレー系統でありながら各階ごとに微妙に色を変えているのが印象的でした。フロアごとの色の違いはどのように決められたのでしょうか。
芦沢:まずフロアごとに床面を覆う素材が違い、さらに外光の入り方が異なるため、素材感や色味を微妙にコントロールする必要がありました。たとえば1階の床はコンクリート、2階はフローリング、3階はコンクリートとフローリングの両方を使っています。
その上で、2階は壁と天井をほぼ同じ色で塗り込んで全体的な空間として見せることを意図しました。それに対して3階は天井を少し暗めにして記憶に残らないような操作をしています。
以下の写真はクリックで拡大します



――実際に足を運んで、空間の絶妙な色合いが、置かれている家具と見事に調和していることに驚きました。色が決まるまで相当な試行錯誤があると聞きましたが。
芦沢:材料や照明、色は、建築の質を最終的に決める大事なところですから、毎回トライ&エラーの連続で、「これ!」という判断がなかなかつきにくい。今でもストレスです。
たとえば色は午前中のできるだけ色味の偏りが少ない光で見て判断します。照明も、空間の雰囲気にどれが映えてくるのかを気にしながら、現場で決めることが多々あります。
――実際どのような判断基準で「これ!」と決めるのでしょうか。
芦沢:まず重要なのは、空間の中に家具を全部並べた時にハーモニーを奏でていることです。だから壁は、家具と真逆の色にはしません。
――3階の窓際で床が高い部分は壁が塗装ではなくモルタルの掻き落としになっています。それはどのような判断で決められたのでしょう。
芦沢:その部分は外光がさんさんと入り、まるでバルコニーのようだったので、外部的なイメージで1階ファサードに使った掻き落としを持ち込みました。左官材も色をコントロールできるので、天井の色に合わせてモルタルに少しだけ黒を混ぜています。
以下の写真はクリックで拡大します


記憶という引き出し
――壁の色の候補は、どうやって選ばれているのでしょうか。
芦沢:毎回、現場がある度に自分が気になっている色について30センチ四方ぐらいのサンプル板を塗料メーカーや左官材メーカーに5~6枚つくってもらうんです。その中から空間の意図やそこに置かれる家具との相性を考えて選んでいます。
それが事務所にどんどんたまっていくので、毎年「これはもう使わない」という色のサンプルはすごい勢いで捨てているんですけど、それでも200枚はあるかもしれません。
ただ最近は「あの時のあの色よりも明るい色にしようか」とか、「あの時のあの色よりもちょっと濃くしようか」「あの感じの色から少しニュアンスを変えてみようか」という言い方をすることもあります。
料理にたとえると、「あの時のあの味よりも、もうちょっとこういう味付けをしたらこうなるんじゃないか」という感覚ですね。色番号は忘れても記憶の中の空間と色はデータとして引き出せますから。
――ということは、日常的に建築とか街も「この色が自分の建築に参照できるかな」という見方をされているのでしょうか。
芦沢:そうです。空間に合っているからこそ素材の色がパッと目に入ってくるんでしょうね。写真にも撮りますけど、記憶の方が写真より正しいんですよ。記憶をたどりながら手元のサンプルや見本帳を見ていくと、「あ、この感じ」という。
――これまでの経験を経て芦沢さんにとってのスタンダードな色はある程度、固まっているのでしょうか。
芦沢:だんだん固まりつつあるから、むしろチャレンジという意味では一回ぶち壊した方がいいと思っています。様々なトライはするものの、色見本帳であれば1枚の帯の中でのグラデーションをよく使ってしまうので。
――芦沢さんから見て、他の建築家の色の使い方などに感想を持たれることはありますか。
芦沢:もちろん、「この人は色を上手に使う人だな」と思うことはよくあります。CASE-REALの二俣公一さんもそうだし、トラフもそうですね。
グレーのニュートラルな空間

――そもそもグレーを多用されるようになった経緯を教えていただけますでしょうか。
芦沢:以前は白を随分使っていましたが、いつしか、思いっきり明るい白か、グレーがかった白か、その中間か、その3種類でしか選べない不自由さを感じるようになりました。
それと同時に、白があまりきれいに見えなくなってきたんです。というのも昼間は床材、夕方は照明の色を拾うから、そうなると、もはや白じゃないんですよ。
それで、他の色ならもう少し純度が高く空間が組み上がるだろうと思い、4~5年前から、白に黄色や緑を入れたり、グレーやベージュを試したりするようになったんです。
――その方向を決定づけた仕事はありましたか。
芦沢:ブレイクスルーは、2019年にオープンした「dotcom space Tokyo(以下、dotcom)」というカフェ兼イベントスペースでした。カフェだけに留まらない自由な空間で様々なものを展示するというので、余計な色を拾わないピュアな空間を目指しました。
アプローチを兼ねたオープンスペースが砂利敷き、室内の床がコンクリートなので、壁もコンクリートの色とできるだけ近づけることで内外を含めて全体的にグレーのトーンが回っている方がいいかなと思いました。
ギャラリーのような“白い箱”のイメージとグレーの中間のギリギリのラインを狙った感じです。黄色が混じったグレーを試し塗りした時にクライアントは「濃いのでは」と心配していたようですが、どうにか説得して押し切りました。
その結果、足を運んだ方々の多くは白だと思っているようです。僕としてはニュートラルなスペースをつくろうと思っていたので、白だと思われているのは成功と言っていいかと思っています。
以下の写真はクリックで拡大します

――確かに注意深く見なければ気が付かないかもしれません。「dotcom」のグレーには、そこにいる人の意識を置かれている家具や什器に集中させる力があるようですね。
芦沢:本当に何もやっていない空間ですからね。予算などの条件でやれることが限られているなかで、そのぐらいシャープにしないと空間として成り立たないし、空間こそがあのスペースの売りなので。そこは「Karimoku」と共通しています。
――もはや色をコントロールする技術は掌中にあるという実感がありますか。
芦沢:どうなんでしょう。僕にとって色は素材と近い感覚があります。
かつて設計事務所を設立する前、super robotという家具工房で鉄製の家具を製作していた時期があります。その中で、鉄に関してはマスターしたとまではいかなくとも、何か自分の中で納得できる手応えを得ました。
今はカリモクさんと一緒に家具を製作したり東北の震災後に始まった石巻工房で家具をつくったりしながら木の扱い方を一つひとつ学んでいる段階です。
色や照明についても、ようやく自分で扱えている実感や、その先にある可能性が見えてきたところです。「この色だったらこういう空間になっていくかな」というイメージはありますね。
“ノイズ”を減らすという手法

――芦沢さんが空間デザインに色を使う上で大事にされていることは何でしょうか。
芦沢:“ノイズ”を減らす。すなわちいらないものをできるだけそぎ落とすために色を使っているという感覚はあるかもしれません。
――既存建物をフルリノベーションした「Karimoku」に関しても、“ノイズ”があったということですね。
芦沢:そうです。リノベーションの場合、ほとんどの既存建物はデザインとして何かを意識してつくられてはいないので、スケルトンにすればするほど無意識の塊がむき出しになります。
そこで、空間をニュートラルにしたい場合、天井がどこまでなら許容範囲かとか、既存の状態をどこまで消してここからは全部見せようなどという判断を行っています。
――つまり“ノイズ”を消すとは、意図しないところに現れる余計なものを消していくという意味でしょうか。
芦沢:たとえば「Karimoku」は家具のショールームですから、空間の目的と無関係の何かがあるとどうしても気が散ってしまいます。場合によっては外の景色だって気になるかもしれません。それを解消するための手段であって、必ずしも解き方は一つではありません。
色の系統をそろえることもあれば、既存の天井を隠すために天井を全部張る場合もあります。
――空間に方向性をつくるとか、ディテールをシンプルにするとか。多種多様な操作が“ノイズ”を消すという言葉に込められているということですね。
芦沢:そうですね。たとえば天井に意識を向けたくない場合、上部に光を当てず低い空間の中でコントロールすることもあります。
Noisyの日本語訳は「うるさい」ですから、要するにどうすればうるさくない空間にできるかを考えているんです。
――目的に集中できる空間ということでしょうか。
芦沢:シンプルに言ってしまえばそういうことだと思います。たとえ高級といわれる温泉旅館でも「落ち着きたい」「くつろぎたい」といった目的に反して、色々気になってしまったら良くないですよね。そういう空間は、幾つもの余計なストーリーが交錯しているといえます。そうならないよう、ある程度ストーリーを整える必要があるんです。
(後編に続きます)
(企画:後藤連平・矢野優美子/インタビュー:後藤連平・中村謙太郎/文章構成・中村謙太郎)

音楽家の蓮沼執太・藤原徹平・中山英之が審査する、日本ペイント主催の国際学生コンペ「AYDA2021」が開催されます。最優秀賞受賞者には、アジア学生サミットへの招待(旅費滞在費含む)、日本地区審査員とのインターンシップツアーへの招待、賞金30万円が贈呈されます。登録締切は2021年11月22日(月)。提出期限は2021年11月25日(木)。
芦沢啓治(あしざわ けいじ)
1973年、東京都生まれ。95年、横浜国立大学工学部建築学コース卒業後、96年から2002年までarchitecture WORKSHOPに勤務。2002年から04年まで、super robotにて家具製作。2005年に芦沢啓治建築設計事務所設立。2011年、東日本大震災を受け石巻工房設立。
現在までに、カリモク家具、無印良品、IKEA などの家具ブランドと協業。Panasonic homes とのパイロット建築プロジェクトなど幅広い分野で活動。グッドデザイン賞(BEST100、復興デザイン賞、Long life design賞:石巻工房)、AIA’s 2010 National Architecture Awards(Peter Stutchbury Architecture との協働による Wall House)Monocle best restaurant design 2021など、多数受賞。
著書として、台湾で出版された『On Honest Design 芦沢啓治 空間・物件設計作品集』(田園城市文化事業有限公司)がある。
■建築概要
Karimoku Commons Tokyo
設計:芦沢啓治建築設計事務所
担当:芦沢啓治、本條理恵
所在地:東京都港区西麻布2丁目22-5
主用途:ギャラリー、ショースペース兼オフィス
インテリアスタイリング:中田由美
施工:
株式会社まつもとコーポレーション(建築)
カリモク家具株式会社(木製建具、造作家具)
原田左官工業所(左官)
superrobot(スチールサッシ・金物)
階数:地下1階 地上2階
延床面積: 387㎡
構造:RC造+鉄骨造
竣工:2021年2月
dotcom space Tokyo
設計:芦沢啓治建築設計事務所
担当:芦沢啓治/Chaoyen Wu/古市翼
所在:東京都渋谷区神宮前1-19-19
施工:TANK
ランドスケープ:橋内庭園設計
家具協力:石巻工房、KNS (Karimoku New Standard)
ファブリック協力:kvadrat
竣工:2019年3月
■シリーズ・色彩にまつわる設計手法のアーカイブ
- 第5回 青木淳 インタビュー・後編「色彩の変わり続ける意味合いと面白さ」
- 第5回 青木淳 インタビュー・前編「場所の記憶を表現した“水の柱”」
- 第4回 加藤幸枝・後編 「色彩を設計するための手がかり② 藤原徹平『クルックフィールズ シャルキュトリー棟・ダイニング棟・シフォンケーキ棟』、原田祐馬『UR都市機構・鳥飼野々2丁目団地』」
- 第4回 加藤幸枝・中編 「色彩を設計するための手がかり① 中山英之設計『Yビル』」
- 第4回 加藤幸枝・前編 「色彩を設計するということ」
- 第3回 原田祐馬・後編 「石ころ、スマホ、記憶の肌理、」
- 第3回 原田祐馬・前編 「団地、ゲームボーイ、8枚のグレイ、」
- 第2回 藤原徹平・後編 「色と建築」
- 第2回 藤原徹平・前編 「まずモノクロームから考えてみる」
- 第1回 中山英之・後編「『塗られなかった壁』が生まれるとき」
- 第1回 中山英之・前編「世界から『色』だけを取り出す方法について」