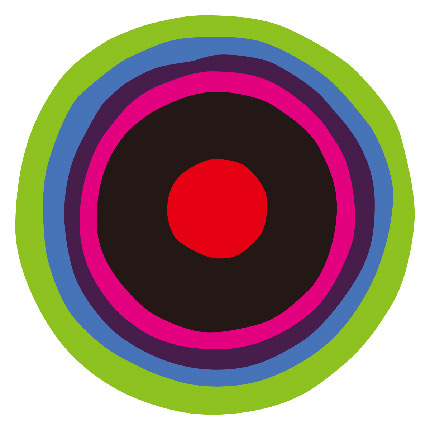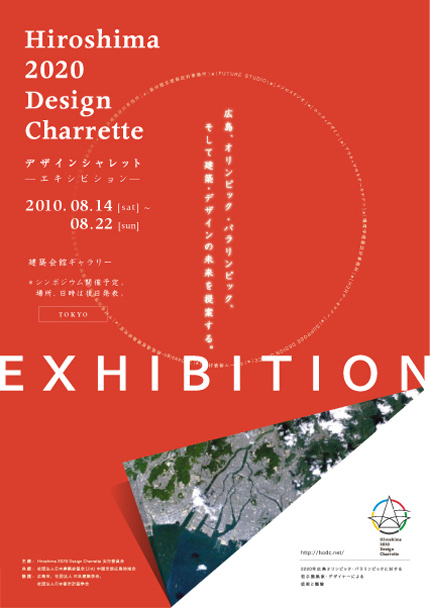SHARE 加藤孝司 BEYOND ARCHITECTURE “柳原照弘 / TERUHIRO YANAGIHARA インタヴュー”

photo©Takashi Kato
現在開催中のミラノサローネで早くも話題の展示が、”補色”をテーマにしたデザイン展 “COMPLEMENTARY COLORS”だ。柳原照弘、坪井浩尚、倉本仁、参、沖恵美子といった今注目の日本の五人の若手デザイナーが新作プロダクトを発表する。
今回の展示会にはデザイナーが寄り合い作品を発表する、単なる合同展とは異なる極めてユニークな点がある。それは五人の若手デザイナーたちが自分たちのために、作品制作のコンセプトを掲げるディレクターを”逆指名”したことだ。今回彼らが逆指名したディレクターは、毎日更新のデザイン・建築の情報サイトdezain.netや、リボンを使ったプロダクトレーベル、リボンプロジェクトを主宰、デロールコミッションズ名義で気鋭のデザイナーや建築家を起用し、アートとデザインを軽やかに横断する問題作を発表し、デザイン界に物議を醸してきた岡田栄造。彼が五人のデザイナーたちに与えたテーマは”補色”という、色そのものをテーマに作品づくりをすることであった。
先日、COMPLEMENTARY COLORSで作品を発表するデザイナーの一人、柳原照弘氏に会いに大阪に出かけてきた。現在開催中のミラノサローネでの展示について、柳原照弘というプロダクトデザイナーについて、そして自身が主宰するデザインユニット”ISOLATION UNIT/” について話を伺ってきた。
柳原照弘 / TERUHIRO YANAGIHARA インタヴュー

Photo©Takashi Kato
柳原照弘のアトリエ
今回のミラノサローネの展示について教えてください。
日本の若手五人で展示会をすることになりました。
そこで意外にありそうでなかった、新しい試みをしています。それは、本来展示であれば、比較的作り手の都合のいい解釈で作品作りができるのですが、今回は我々デザイナーの側から、展示会のコンセプトを決めるディレクターを逆指名しました。
そのきっかけとしては今回のミラノサローネの参加は、我々五人のデザイナーの合同展示会というかたちになるのですが、僕らデザイナーがそれぞれ好きなものを作って展示してもまとまりがないし、そもそも僕ら五人が集まった意味もないと思っていて、それだったら逆にお題を与える、じゃないですが、この五人を巧くディレクションしてくれる人を探そうということになって、メンバーと検討した結果、今回は岡田栄造さんにお声をかけまして、快諾していただきました。
通常ですと、ディレクターがいて、デザイナーを決める、というのが一般的だと思うのですが、デザイナーがディレクターを指名して、なおかつお題をくださいみたいなことをやりました。
ある種そこで生まれるのが「規制」だし、そもそもデザインすることに付いて回る規制に、ディレクターである岡田さんが、さらに規制をかけるということを敢えてやろうと考えました。
そこで今回、岡田さんから出たお題が「色」だったのですが、それも本来プロダクトには使ってはいけない補色を使いなさい、ということで、僕らにはそれがもの凄く新鮮だったし、面白いと思えました。

Photo© ISOLATION UNIT/
柳原照弘によるローテーブル”1915”。 ミラノでの“COMPLEMENTARY COLORS”展で発表される。
今回デザイナーが五人ということですが、それはどのように決まったのですか。
イタリアにL’Archivolto Libreria Galleriaという出版をかねた本屋さんがありまして、イタリアに行くたびにそこで本を買って帰るくらい僕はそのお店が好きなのですが、そこの地下にギャラリーがあるんです。
そこのギャラリーが日本人をフューチャーして今後毎年展示会をやりたいということでして。そこで以前に日本で出版された僕ら五人のデザイナーも掲載されている「シンク・グローバル・アクト・ローカル」というバイリンガルの本があるのですが、その本を見たギャラリーのオーナーの指名があって、今回はこの五人で行こうということに決まりました。
先ほどのディレクターの話もありますが、今回この五人でやろうと決まったときに、まずどのようなことが決め事として話し合われたのでしょうか。
この五人でまとめようかというなかで、まず先ほどもお話したように、五人が好き勝手に何かをするよりは、ディレクターを逆指名してみよう、ということになりました。
それではディレクター逆指名の件は、かなり早い段階から全員一致でそうなったのですか。
毎年こちらがディレクターを好き勝手に決めても面白いんじゃないかな、と思ったんです。
というのも今回思ったのが、デザイナーで出てくる物が変わるというのもあると思うのですが、ディレクターの裁量によってイベントそのものの性質が変わるということがあるじゃないですか。それをデザイナーである僕らも見てみたいというのがあります。
また、昨年秋の岡田さんのデロールコミッションズno2が物議をかもしたように、岡田さんにはもう一回失敗してもらおうかと(笑)。
デロールコミッションズではデザインの流れのなかで、物議をかもしたい、というがあったと思うんです。岡田さんとしては、これはデザインか?とか、批評に値しない、とかいうところをある程度狙っていたと思うんです。ですが意外と評価されてしまった。
この流れで、岡田さんにもう一度ディレクションの失敗をしてもらおうと思いました。
その失敗というのは岡田さんにとっては大成功なんですけれども、僕らはそれにある意味乗っからせていただこうかなという目論みもあります。
そういった意味では、デザイナーからみて岡田さんという人は、デザインの文脈のなかでユニークな存在であるという評価ですか。
いや、それはもう、補色をプロダクトに使いなさいというのは今までになかった事ですから。驚きながらも新鮮でしたね。
僕らとしては、もう少し直球勝負的な提案かと思っていたんです。
それは、かたちとか、デザインのディテールの提案といったような具体的なもの、という意味ですか?
そうですね。例えば会場でもある本屋さんにちなんだ何かとか。
それでいきなり、補色をつかいましょうということで。
あらためて自分たちが作ってきたものを見渡してみても、僕らは今まで色を使ってきていないんですよ。
逆にいうと、今回岡田さんがくれたお題は、海外ではなぜ日本人は色を使わないんだ、という疑問のところまで踏み込めるもので、問題提議としても、ものすごく良いテーマだったと思います。
今回の展示会の舞台となるイタリアという国は、モダンデザインの時代から色の使い方に意外性があり、かつ上手いですよね。ファッションなんかも最先端のトレンドを作ってきたといえます。プロダクトデザインでいえば、例えば’80年代のメンフィスなんかにしても、原色の洪水のなかで、デザインを積み重ねてきたような雰囲気さえありますよね。
実際に僕らも海外ではなぜ黒白グレーしか使わないの、と訊かれるんですよ。
以前にロンドンで講演したときにも同じような質問をされました。
そもそも色を使う理由がないから、というのが僕らに共通の答えであって、色とかではなく、僕らのデザインにはもっと違うストーリーがあるぞと。そこに色が入ると伝えたい別のものを邪魔をするとか、色で表現しなくても、物の在りようで表現できるとか、それが僕の答えだったんですが、今回は色を使いなさい、というのがテーマで、僕らのデザインの根本からの問いかけでもありました。
あえて自分たちが選ばない道というか、色を使わないことで、デザインするものがもつ用途や機能といったものを、鮮やかに表現するという、日本独自の世界観もありますから、根元的な難しい問題も含んでいますね。それだからこそ、面白い。
単純に色を使うのか、色を使う、ということについて考えながら取り組むのか。その辺は五人それぞれ背景が違うので、どういった意識でその問題について取り組むのか、楽しみですね。

©Takashi Kato
柳原照弘による”COVER IT /Flower Vase”
■問題意識のなかで、ここでしか生み出し得ないもの
僕らとしては、いいね、きれいね、で終わらせずに、何かしら問題意識をもちながら、僕らとしてはたとえばメンフィスのようなものを結果的につくりたいんですよ。
上の世代の人たちに、こんなのデザインじゃないとか、なにやってんの、って言われたいんです。
ではあらゆる制約や縛りから自由に、アイロニーを込めてということですか?
そこは今という時代背景も考慮して、さまざまな制約のなかで、ということですね。
今回でいえば、色のしばりがあるし、もちろん時間の制約、コストの制約もあります。制約というものをネガティブな要素としてとらえずに、そのなかで、何をどうつくるかということも、今回のひとつのテーマにしています。
そもそもかたちをつくるということ自体に制約がありますよね。
それはデザインがデザインするということの予定調和という袋小路に陥らずに、デザインするという行為の実践によって、デザインにおける問題解決の方法をさぐる、ということに繋がりますね。
デザインそのものも制約のなかにあると思っています。
当たり前ですが、たとえばクライアントがうどん屋さんをやりたい、といっているのにイタリアンレストランのインテリアはつくれないし、予算の問題もそうです。でも、そういった制約を越えていくことも、デザインの行為のひとつとしてあると思います。
今回のミラノでのプロジェクトでいえば誰か特に見てもらいたい対象はいますか?僕もまだ作品を見ていませんので、わからないのですが、サローネという見本市で発表する以上、製品化を目指すということでいいのでしょうか。
実は皆、製品化を目指しています。
では、アートではないと?
アートではないです、もちろん。ミラノサローネでやる意味というのもそこで、展示会というものもイベントという出来事のひとつかもしれませんが、イベントとして評価されて、物を買ってもらえるというところまで、僕ら全員が考えています。だからアートではないし、デロールコミッションズでもない。

photo©Takashi Kato
柳原照弘のアトリエの風景
柳原さんは一般的にはプロダクトデザイナーとして認識されているように思いますが、空間や建築のお仕事もされていますね。
最近では、建築家の藤村龍至さんらが主催するトークイベント、ライブラウンドアバウトジャーナルにも参加されていました。
個人的には建築家が空間を手がけることはよくあると思うのですが、プロダクトデザイナーが建築や空間を手がけるのは面白いなあと思いました。建築とプロダクトデザインの方法論の違いを感じることはありますか。
それは例えば、藤村君に限定すると、彼が建築以外の仕事、例えばインテリアであったり、フリーペーパーや書籍などをやっても、あくまでもその方法論は建築的ですよね。そこが一貫しているから、僕はすごく好きなんです。
藤村君とはやっていることは違うけれど、やろうとしていることは共通点があって、同世代で刺激にもなります。
柳原さん自身は建築を手がけてみたいと思っていますか。
もちろん。建築や空間、プロダクトなど、仕事を限定はしていません。ライブラウンドアバウトジャーナルでも、有形・無形のアーキテクチャという議論があったのですが、僕はどちらかというと無形に近い有形だと思っています。
かたちは絶対必要なのですが、そのかたちそのものというよりかは、そこに至るストーリーそのものが、僕にとっては建築のプロセスと一緒なので、プロダクトをつくっても、建築をつくっても、グラフィックをやったとしても、僕は一貫した考えでやっています。
それがモノなのかコトなのかは、あまり重要ではないですね。
モノにしてもコトにしても、ひとつの事象として空間にたちあらわれた時点で、はじめて、存在として認識されるものですよね。
そうですね。
大きいかちいさいか、重要か、重要でないかの区別でなく。
それをつくる行為全体がデザインだと思います。
極論をいえば、仮にアウトプットがなかったとしても、デザインとしては成立すると僕は思うんですね。

photo©Takashi Kato
柳原照弘のアトリエの風景
■作ることの責任とどう向き合うか
建築はあからさまな感じで、世界とか空間にマッシブにたちあらわれるじゃないですか。環境にも大きな規模で影響を与えるものだと思うんです。
かたやプロダクトはスプーンとっても、それが社会全体にあたえる影響というのは、ちいさくて解りづらいものかもしれないのですが、値段も建築より安くて、誰もが手に入れやすい、という点で、建築より多くの人に、速やかに影響を及ぼしうるという点で、責任は大きいと思います。
建築は必然的にスペシフィックなものですよね。それに対して、プロダクトは場所性関係なく社会に広がりうるという点で、建築よりも社会との接点は近いと思っています。
プロダクトは、例え小さくても社会性とか、モラルとかを考えて作っていかないと、マズイんじゃないかと僕個人は思っています。
そうですね。
たとえば育つ環境で人は変わると思いますか?柳原さんにはお子さんいらっしゃると聞きましたが、小さな頃から与えるものには配慮したりしますか。
いや、それはあまりないですね。アンパンマンとかスゴく好きですよ。あんまりないですね、その辺は。
たとえば、自分では物事の良し悪しを判断出来ない小さな頃は、テレビや漫画を見せないとか、ある意味ストイックにお子さんを育てている方もいるようですが。
いつも一緒にいると分かるのですが、子供って吸収する力がものすごいんです。だから自由に感性のままに吸収させないことはいけないな、と思うんです。もの凄くいろんなものを吸収させてあげたいので、そこには規制はないですね。
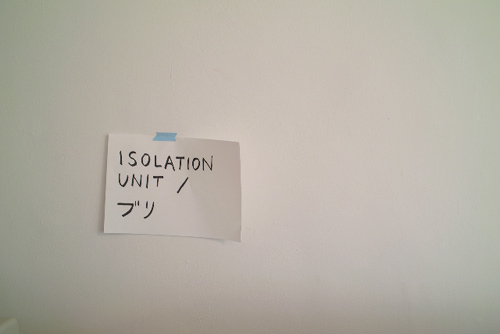
photo©Takashi Kato
柳原照弘のアトリエの風景
■デザインとは編集すること
柳原さんにとってデザインってなんですか。例えば仕事ということもできるでしょうし、自己のアイデンティティー、もしくは社会との関わるためのひとつの方法、ということもできると思いますが。
ひとつは社会と関わる接点というか、仕事をどうしていくかというときに、好きなことをやりたい、好きじゃないことはやれない性格というか、その中で選んだことですし。
かといってこれで何かを劇的に変えよう、という意識があるわけではありません。あくまで生きていくための方法論です。
柳原さんは個人名義の活動以外に、ISOLATION UNIT/として活動されていますが、ISOLATIONUNIT/というチームのなかで、柳原さんはどのような役割をされているのですか。
ISOLATION UNIT/として形成されていることの全てなんですが、ISOLATIONというのは孤独という意味があって、UNITというのはその反意語じゃないですか。
ある意味ユニット批判みたいなところから入っていって、一人なのにISOLATION UNIT/という名前でやっています。ちょうどユニット全盛の時代の頃だったんですが、僕の考えでは、社会のなかで何かをするということは、絶対的にユニットだと思うんです。どんなことをしていても。
どんなことをしても、物事の成り立ちって一人では成立しないと思うんです。例えば、加藤さんが好きなことをしているといっても、それを見てくれている人がいないと、加藤さんは形成されないし、評価してくれる編集の人がいないと仕事にならないですよね。
世の中のあらゆることが結局ユニットなんですよね。デザインって最もそのつながりが強くて、極端に言えばすべての行為、状況はデザインであるとも言える。例えば自分がアイデアを出して、ひとりでそれができる訳じゃなくて、作ってくれる人や、クライアントがいないとそれは成立しません。
もし、お店であれば、それを買ってくれるお客様や商品がなければ、そもそもお店は成立しません。
そのように社会のシステムが総和としてのユニットで形成されているところで、デザインするうえで、僕は僕の責任を持とう、って思ったのがきっかけです。
世の中は、それぞれの人がそれぞれに、どこかに自分の責任をつくりながらこの世界の中に暮らしている、という共同体としての意識が僕のなかにはあったのでISOLATION UNIT/なんです。
僕の立場としては事務所の組織をつくる責任をもちながら、今は分かれているのですが、プロダクトは自分の発想のなかで責任をもってつくっていく、インテリアのデザインですとISOLATIONUNIT/のメンバーのなかで、役割を分担するのではなく、自発性をもちながら、それぞれがそれぞれの責任をもってやっています。
ユニットとして有機的につながりながら、全体が出来上がっていく、そんなイメージが浮かびます。それは社会との関わりのなかで、モノだけでなく、コトをつくっていこうというISOLATION UNIT/のありかたの実践でもあるますね。
では、自分たちから仕事の提案をしていくこともあるんですか。
半分はそうしようと思っています。もともと最初は仕事がまったくなかったので100%自分たちで勝手に提案していました。ないなら作ろうと。それが僕らの「デザインする状況をデザインする」というテーマにつながっていきます。先ほどの僕のISOLATION UNIT/での役割でいえば、それをチーム内で共有しながら、何かを自ら思って、やりたいと思える状況をつくってあげることが僕の責任だと思っています。
例えば、ないけどやりたいものがあったら、やれるようにする、というところまで事務所の中では考えています。
依頼があるということはもちろんいいことなんですが、依頼があって何かをすることと、自分たちがやりたいことがあってすることって、最後には結びつくものなんです。依頼されてする仕事が面白くないことではなくて、僕らは依頼という制約のなかで何をするかは重要だし、仕事をとりにいっても制約条件のなかでやることには違いはありません。
ただ、ものを手がけるストーリーとしては、その二つのストーリーをつくっていくことで会社も伸びていくし、実力もついていくので、そのなかでクライアントに満足してもらえるものをつくっていけると僕は考えています。ただ依頼が増えていくなかで、同じくらいのボリュームで自分たちが提案する仕事をつくっていこう、ということは常に考えています。
僕もそう思います。それがたとえ依頼が先だったとしても、人と関わったり繋がったりすることから、クリエーションって生まれると思います。
そうですね。それは大阪にいることと関係してくるのですが、大阪にいると実際問題として依頼されることは少ないんです。だから結果的にそれが僕らのスタイルになったと思います。
僕も柳原さんとお話をしたい、という目的をもって今回大阪に来たのですが、それは柳原さんが日頃発信されていることに引き寄せられたということが大きいです。
それも状況をつくる、ということだと思います。事務所を始めたころはなかったことですから。それも含めて全てデザインの行為だと思っています。
自分自身も思うのですが、大阪って決して来たい、って思わせる場所ではないですから。そもそも来たいと思わせるインフラのストラクチャーのないところにこそ、自分たちが作れる場所があると思っているんです。
デザインって編集だと思うんです。雑誌や書籍の編集もあるテーマや枠組みをもってその規制のなかで最善のものを考えるじゃないですか。フリーの編集者やライターであれば出版社から依頼があって、その与えられた場所で自分をださなきゃならない。デザインも一緒なんです。この土地で、この予算でベストをやらなければいけない。編集と一緒なんです。その辺で僕らは自分たちのやることを編集的と言っているんです。
好き勝手に物を作ったりしたら楽しいと思いますけど、規制のなかでやることがクリエイティブなことだと思っています。
好き勝手といっても、物なら物、本なら本のフォーマットのなかでやるわけですから、そもそも規制があるわけです。その規制から逸れることは出来るけど、物だったり本でなくなることは出来ない。だからデザインも多様な人や物の関わりを編集する点では一緒なんです。
規制があるからその規制がもつ既成概念と向き合いながら、その規制をどう解釈しようかとか、それをどう覆してやろうか、と一生懸命考えるわけですね。
そうです。だから僕らの拠点である大阪っていうのも、それ自体がネガティブな規制要素だと思うんですけど、それがあるから自分たちをつくっていけるというのはあると思っています。
拠点があることは物づくりをする上でとても重要なことだと僕も思います。では、これからも大阪を拠点に活動されていく予定ですか。
これからもベースはあくまで大阪です。活動している以上、大阪とどこかを繋ぎたい、という思いはあります。
だから大阪にいる意味が僕らにはあって、ここにいるからこそ身近な東京さえも、ミラノ、ニューヨーク、パリと同じように、世界の一つの都市としてフラットに見ることができるんです。それはとてもいいことだと思っています。
ただ、大阪が好きだからとはちょっと違う。これもある種の規制ですね。
2月23日大阪 柳原照弘/ISOLATION UNIT/オフィスにて収録
柳原照弘 TERUHIRO YANAGIHARA
1976年香川県生まれ 1999年大阪芸術大学デザイン学科空間デザインコース卒業 2002年TERUHIRO YANAGIHARA ISOLATION UNIT/ 設立
New Wind From Japan「COMPLEMENTARY COLORS ~Missing Link of Design~」
ディレクター: 岡田栄造
参加デザイナー:柳原照弘、坪井浩尚、倉本仁、参、沖恵美子
会期:2009年4月22日(水)~27日(月) 09:00~20:00
パーティー : 4月24日(金) 19:00~22:00
会場:
L’Archivolto Libreria Galleria Via Marsala2 ,20121 Milano