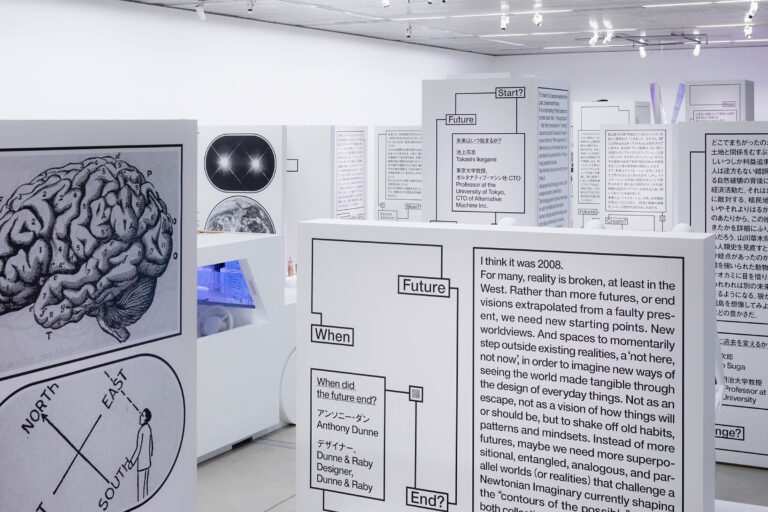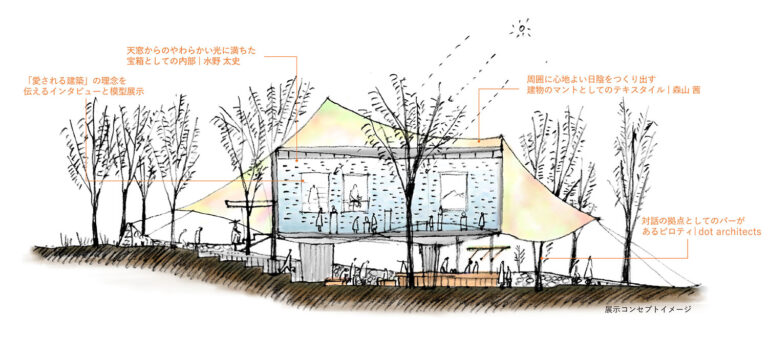スノヘッタによる、ノルウェーの、インスタレーション「Traelvikosen」。
著名な観光道の海岸に設置されました。建築家は、自然への深い理解を促す事を求めて、海に向かう“55個の飛び石”からなる作品を考案しました。それは、潮の満ち引きにより刻一刻と新たな表情を見せます。作品の場所はこちら。
こちらは建築家によるテキストの翻訳
ノルウェー北部にあるスノヘッタの潮汐のインスタレーションは、訪れる人を一時停止させ、時間の経過を体験させる
北緯65度、ノルウェーのナムソスとモスヨエンを結ぶ道路沿いにある「Traelvikosen」で、スノヘッタは旅行者のための特徴的なインスタレーションと休憩所を開発したのです。この場所は、ノルウェー公営道路局のノルウェー・シーニック・ルート・プログラムの一部です。現在、訪問者の為に開かれており、海に向かって横一列に並べられた55個の飛び石の上を、自然の中を歩くことができるのです。
砂浜から小島、そして名峰トルハッテンへの眺望に至るまで、砂浜の海底を正確に一直線に進み、干潮時には完全に見え、満潮時には完全に消える、潮位に応じた流動的な体験となります。海岸の小さなディテールから壮大な景色まで、さまざまな印象を与え、さらに時間そのものや刻々と変化する自然への深い理解を誘います。潮の満ち引きによって、刻一刻と新たな表情を見せてくれるのです。
ノルウェー公共道路局は、30年近くにわたる断固たる努力により、ノルウェー・シーニック・ルートを国際的に魅力あるアトラクションとして発展させてきました。道路を利用する旅行者には、サービス施設だけでなく、壮大な景色の中で斬新な建築物や考えさせられる芸術を体験することができます。選ばれた道路は、海岸やフィヨルド、山や滝など、ユニークな自然の景観の中を走っており、幹線道路に代わるものとして位置づけられています。観光産業における価値創造を支援するだけでなく、この取り組みにより、あまり知られていないさまざまな地域が、探索し、体験し、楽しむことができるようになりました。2022年、スノヘッタが設計したTraelvikosenは、新しいシーニック・ルート・プロジェクトシリーズの一部としてオープンする11の新しい建築プロジェクトのひとつです。