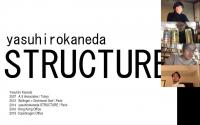MVRDVによる、ロッテルダム港の展示スペース兼ヴィジターセンター「ハーバー・エクスペリエンス・センター」。持続可能な材料・構法で造られる建築は、直方体ヴォリュームをずらして積層することで様々な港の景色を取り込む image©MVRDV MVRDVによる、ロッテルダム港の展示スペース兼ヴィジターセンター「ハーバー・エクスペリエンス・センター」。持続可能な材料・構法で造られる建築は、直方体ヴォリュームをずらして積層することで様々な港の景色を取り込む image©MVRDV MVRDVによる、ロッテルダム港の展示スペース兼ヴィジターセンター「ハーバー・エクスペリエンス・センター」。持続可能な材料・構法で造られる建築は、直方体ヴォリュームをずらして積層することで様々な港の景色を取り込む image©Kossmanndejong MVRDV による、オランダのロッテルダム港の、展示スペース兼ヴィジターセンター「ハーバー・エクスペリエンス・センター」です。持続可能な材料・構法で造られる建築は、直方体ヴォリュームをずらして積層することで様々な港の景色を取り込むことも意図しています。2024年のオープンを予定。
こちらはリリーステキストの翻訳
MVRDVのハーバー・エクスペリエンス・センターは、訪問者にロッテルダム港の新たな視点を提供します。
MVRDVは、ロッテルダム港の最西端に位置する同港の展示スペース兼ヴィジターセンター「ハーバー・エクスペリエンス・センター」の設計を公開しました。回転する5つの展示スペースで構成されたこの建物は、平坦で開放的な環境の中で際立っており、海岸線、港、海のあらゆる方向の素晴らしい眺めを提供します。ハーバー・エクスペリエンス・センターは、2024年にオープンする予定です。
ハーバー・エクスペリエンス・センターは、ロッテルダム港の第二次人工拡張工事(Maasvlakte 2)の建設期間中の2009年にオープンした仮設インフォメーション・センター「FutureLand」の後継施設です。FutureLandの成功を受けて、ヨーロッパ最大の港について知ってもらうための大規模な常設展示を備えた、より充実したインフォメーションセンターを作ることになりました。ハーバーエクスペリエンスセンターは、ヴィジターセンターをビーチのより目立つ場所に設置し、周囲から見えるビーコン(※かがり火) のようにしました。
この建物は、シンプルな機能性、ドラマチックな存在感、工業的な素材を用いて港の精神を表現し、実用的で無駄のないアプローチをとっています。建物の形状は、屋内外で行われる活動に直接対応しています。各フロアは正方形のプランで、大きなパノラマウィンドウからは、賑やかな港の風景を一望できます。1階のカフェの窓は西向きで、砂丘と北海の景色を眺めることができ、4階のレストランでは、北海と夜にきらめく港の光の両方の景色を楽しむことができます。
Kossmanndejongがデザインした常設展示は、その間の3つのフロアにに広がっています。展示では、各階がそれぞれ異なるテーマを扱っており、パノラマウィンドウは展示内容を引き立てる港内の要素に焦点が当てられています。建物の中央には大きなアトリウムがあり、それ自体が展示スペースとして機能しています。中央には説明用のキネティック彫刻が吊るされ、足元にはロッテルダム港の模型が置かれています。この印象的な空間は、1階からの入り口で強調されています。訪問者が建物の大規模な中心部に入るまで、回転式のドアが展示を隠します。
また、外からはチケットなしで建物に登ることができ、階段を使って様々なテラスから屋上に上がることができます。その途中にあるショーケースの窓からは、中の展示が見えるようになっていて、来館者を中に誘います。
建物の素材は、シンプルでインダストリアル、そしてサステナブルなものを使用しています。建築物はエネルギーニュートラルで、解体された構造物から寄付されたスチールを使用し、ファサードパネルは一部リサイクル素材を使用し、高水準の断熱性を備え、音響天井は再生紙パルプを使用しています。また、建物自体も循環型の設計となっており、構造体は部品を再利用しやすいように解体可能となっており、ファサードパネルはメーカーとの契約により、建物の寿命が尽きると返却されます。建物の基礎も、コンクリートの杭を使わず、痕跡が残らないように設計されています。
ハーバー・エクスペリエンス・センターは、持続可能な素材を使用しているだけでなく、エネルギー・ニュートラルな建物でもあります。コンパクトな容積、効率的な断熱材と機械部品のおかげで、建物のエネルギーは266枚のソーラーパネルと独自の風車でローカルに生成することができます。
MVRDVの設立パートナーであるヴィニー・マースは言います。