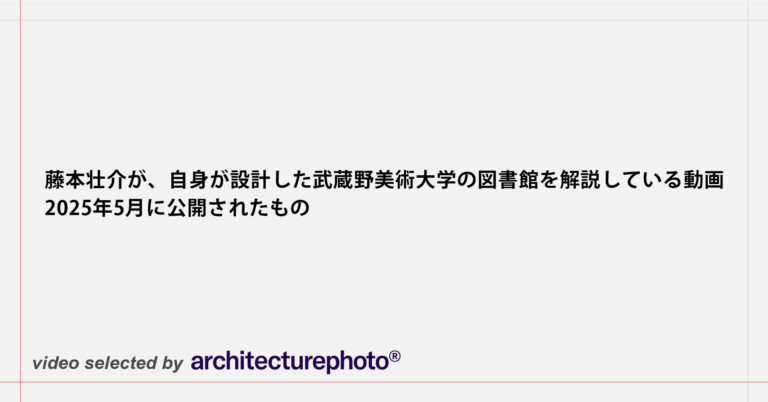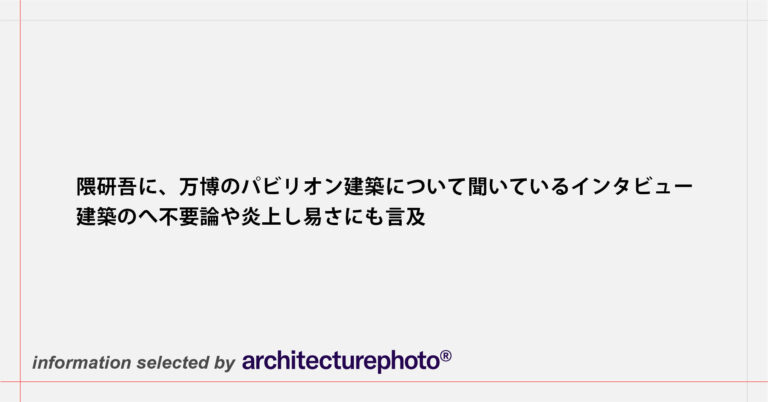ザハ・ハディド・アーキテクツによる、アラブ首長国連邦の複合開発「Oystra」。集合住宅を中心に商業とレジャーの施設も内包。海と空の自然のエネルギーに着想源とし、バルコニーやテラスのデザインは“波が砂に刻むさざ波の模様”も反映。環境予測で日射遮蔽の最適化と自然換気の強化も実施 Render by Redvertex ザハ・ハディド・アーキテクツによる、アラブ首長国連邦の複合開発「Oystra」。集合住宅を中心に商業とレジャーの施設も内包。海と空の自然のエネルギーに着想源とし、バルコニーやテラスのデザインは“波が砂に刻むさざ波の模様”も反映。環境予測で日射遮蔽の最適化と自然換気の強化も実施 Render by MIR ザハ・ハディド・アーキテクツによる、アラブ首長国連邦の複合開発「Oystra」。集合住宅を中心に商業とレジャーの施設も内包。海と空の自然のエネルギーに着想源とし、バルコニーやテラスのデザインは“波が砂に刻むさざ波の模様”も反映。環境予測で日射遮蔽の最適化と自然換気の強化も実施 Render by Pyxid ザハ・ハディド・アーキテクツ が設計している、アラブ首長国連邦の複合開発「Oystra」です。
こちらはリリーステキストの翻訳です(文責:アーキテクチャーフォト)
ZHAがアラブ首長国連邦におけるオイストラ複合用途開発のデザインを公開
アラブ首長国連邦のラス・アル・ハイマにあるアル・マルジャン島に位置するオイストラは、12万8,000㎡の海沿いの開発で、1~4ベッドルームのアパート、デュプレックス、ペントハウス、ウォーターフロントヴィラ950戸に加え、充実したショッピング、飲食、レジャー施設を備えています。
ラス・アル・ハイマはアラブ首長国連邦で最も急成長している首長国の一つであり、その人口は2030年までに55%増加すると予測されており、将来の需要を満たすために追加で45,000戸の住宅が必要とされています。ラス・アル・ハイマの観光部門も記録的な成長を遂げており、2013年の来訪者数10万人から増加し、2030年までには年間350万人の観光客を迎えると予測されています。
アラビア海に4.5キロメートル突き出し、7.8キロメートルの白砂のビーチを含む全長23キロメートルの海岸線のあるアル・マルジャン島は、アラブ首長国連邦内の主要な観光地としてそのインフラが開発されています。公園、マリーナ、ウェルネスセンター、エンターテインメント拠点を備えるこの島は、ラス・アル・ハイマ空港から25分、ドバイ国際空港から45分の場所に位置しています。
全体の75%以上のアパートメントに遮るもののない海の眺望を提供するようにザハ・ハディド・アーキテクツにより設計された、この開発の流動的なジオメトリーは、波が砂に刻むさざ波の模様を反映するように形作られた大きなバルコニーやテラスを含んでいます。これらのバルコニーは、それぞれのアパートメントの居住空間の継ぎ目のない延長部として機能すると同時に、室内を直射日光から遮る役割も果たしています。
オイストラの彫刻的な20階建てのウォーターフロントタワーは、湾を見渡す美しく整備された庭園、中庭、スイミングプール、ビーチクラブを備えた4万2,000㎡の敷地内に建てられており、屋上のレストランと360度のインフィニティプールからは、アル・マルジャン島とアラビア海の全景を望むことができます。
この開発は、アル・マルジャン島の街路樹の並ぶ海沿いの遊歩道と直接つながっており、そして、海から内陸に吹く北西風によって冷やされる屋根付きの海岸沿いのこの歩道を通じて、住民は島内を徒歩で移動することができます。
環境シミュレーションによって、敷地条件、構造、方位における効率が最大化され、また、デジタルマッピング分析により、デザインの外部日射遮蔽が最適化され、自然換気が強化されました。この開発では、海水を利用した冷却システムと、建物の外皮と直射日光にさらされるファサードの間に断熱層が取り入れられる予定です。これらの戦略は、ラス・アル・ハイマの乾燥した気候において、冷却のためのエネルギー需要を削減しつつ、室内の快適性を高めることになります。
ザハ・ハディド・アーキテクツのディレクターであるクリストス・パッサス(Christos Passas)は次のように述べています「私たちのリッチマインドとの協業は、共通の志と創造的な対話の成果です。オイストラの彫刻的なデザインは、海と空の自然のエネルギーに着想を得ており、ダイナミズムと開放感をもってその環境に応答しています」