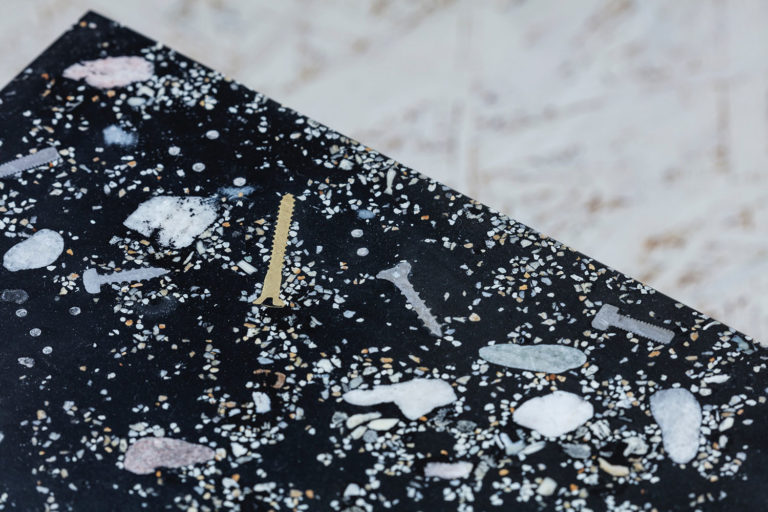『観察の練習』『ヘンテコノミクス』でも知られる菅俊一の展示「正しくは、想像するしかない。」が松屋銀座で開催されています。会期は2019年4月15日まで。
菅の公式サイトで会場写真などが7枚閲覧可能です。
この度、日本デザインコミッティーでは、第753回デザインギャラリー1953企画展として、映像作家の菅俊一氏による個展「正しくは、想像するしかない。」を開催いたします。
菅氏は、人間の知覚能力に基づく新たな表現の研究・開発を行っているクリエイターです。今回の展覧会では、私たち人間が持つ想像する能力について考察するものです。以下の3つのテーマによって展覧会は構成されます。
1)線の質感・表現を変えるだけで「透過」感覚を作りだす試み。
2)ディスプレイや紙に描かれた顔の視線同士をつないで、空間に線を描く試み。
3)これまで目にしてきた情報を手がかりに、その後どうなるのかを想像させる試み。
それぞれの展示を通し、人間の知覚能力の可能性を実体験していただければと思います。
菅俊一(企画・監修)からのメッセージ
私たちは普段目で見たものを手がかりとして、たとえば止まっている絵を見て動きや時間の経過を感じてしまうなど、頭の中で様々なイメージを作り出しています。今回のプロジェクトでは、この私たちの持つ素晴らしい能力の一端に触れるため、点や線で構成された最小限の手がかりだけで、「透明」「視線による空間把握」「切断による時間生成」という3つのイメージをみなさんの頭の中に作りだす試みを行います。ここに並んでいるのは手がかりだけです。正しいイメージを作りだすには、鑑賞しているみなさんの想像力を使うしかないのです。
展覧会担当 鈴木康広からのメッセージ
菅俊一さんの考察に触れると、ふだんの何気ない「見る」という行為を支えている自分の存在に気づかされる。人間の視覚はカメラのように外部を写すものではなく、対象に自らを映し出す過程そのもの。知覚と認知の隙間に潜む未知なる能力は、個人の体験を通して開発が可能であることを菅さんは丁寧に示そうとしている。