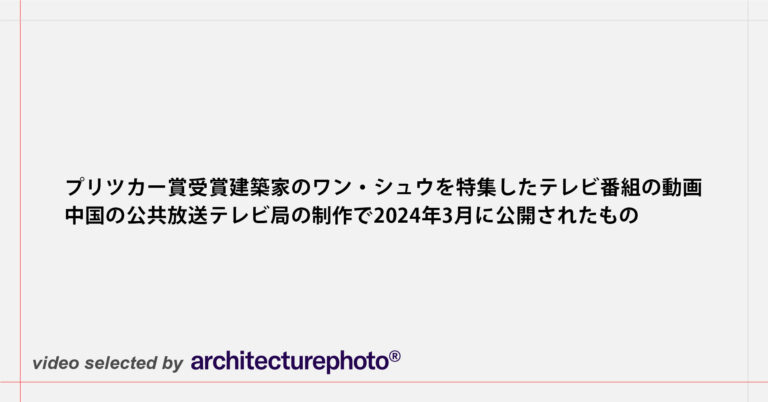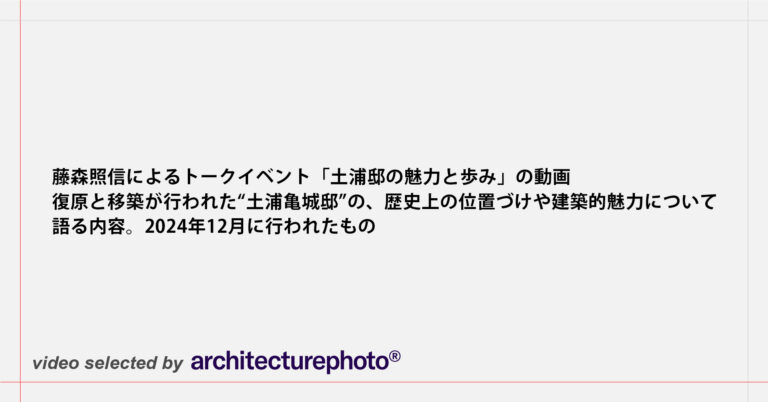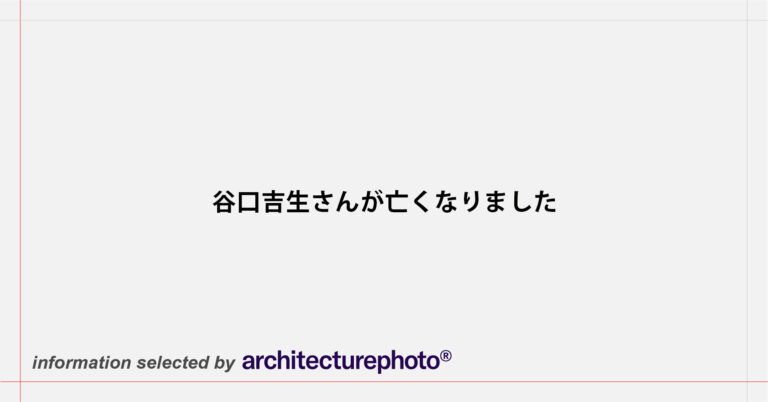アクセル・ヴェンスティンキステとサイドバイサイドが設計した、千葉・山武市の「ウシマルレストラン」です。
豊かな畑に囲まれた飲食店の増築計画です。建築家は、食材の物語を体感できる“開放的”空間の創造を求め、気積のあるラウンジを内包する“抽象的な量塊”を既存に追加しました。また、金属板で覆った外観は風景を柔らかく反射し環境に溶け込みます。店舗の公式サイトはこちら。
千葉県山武市の郊外に佇む「ウシマルレストラン」。
その周囲はまるで絵画のような豊かな農地や畑に囲まれています。レストランは、千産千消をテーマに掲げ、地元の山や近海からシェフによって厳選された旬の食材を使った料理が、日々変化する季節と地元の味覚を提供します。オーナーは料理を通して訪れる人々が実際に食材が育まれる風景との一体感を味わうことができる空間を望んでいました。既存の閉鎖的なダイニングスペースを開放的にし、この場所を訪れることで食材の物語が大地の恵みと共に体感できるレストランへの増改築を目指しました。
既存の建物のレイアウトは、南北にダイニングスペースとサービスゾーンで構成されていました。南側のダイニングスペースは内向的であるものの吹き抜けで、天井が高く、木の構造梁が空間にリズムを生み出しています。一方、北側にはファサードに沿ってキッチン、倉庫、トイレなどのサービスゾーンが配置されています。この建物の既存の特性を踏まえつつ、南北それぞれ抽象的なボリュームを拡張し、増築の設計を進めました。
新たなラウンジスペースとなる南側の増築は45度の傾斜屋根で構成され、ダイニングスペースから周囲の田園風景への眺望を確保するために、東面に大きな開口を設けました。その開口からはテラスや隣接するガーデンへもアクセスができ、早めに到着したお客様が散策したりハーブを摘んだりすることができます。
南側の屋根は、隣接する駐車場が隠れるように地面ぎりぎりまで延ばし、日差しも遮ります。大屋根は既存の建物に向かって上方にカーブし、増築部と既存部の境界に新たに設けられたレストランの入口を印象的に示し、お客様を歓迎します。小さな入口をくぐると、高さ7mの開放的な三角形の空間が広がり、既存の建物の特徴的なジオメトリーと木構造が感じられます。
一方、北側の増築部は低く閉じられたボリュームで構成され、キッチンとサービススペースの拡張となっています。南側と北側の異なる形状が反映される東側ファサードでは、南北の対照を強調し、増築部分の抽象的な性格を表現するために、ガルバリウムをファサード全体に採用しました。空と周囲の景色から柔らかな反射を受け、建物が周囲の環境に溶け込むように演出されています。