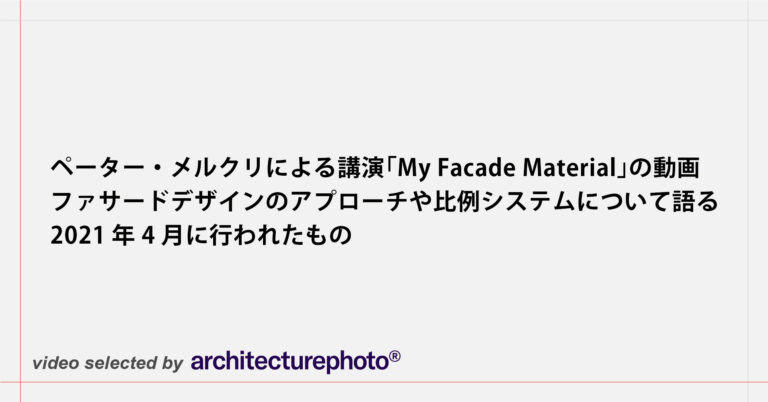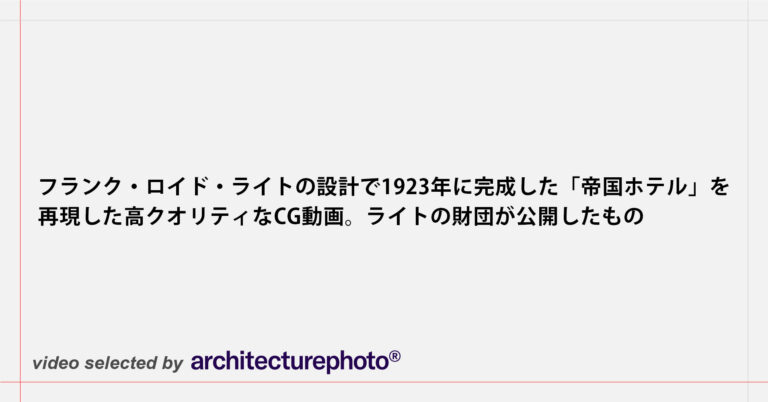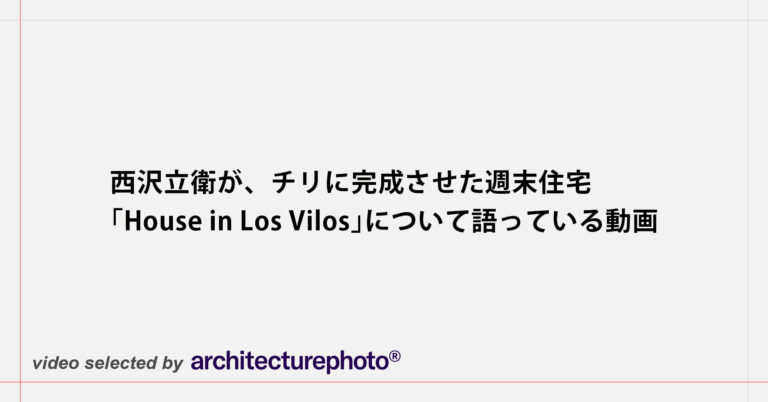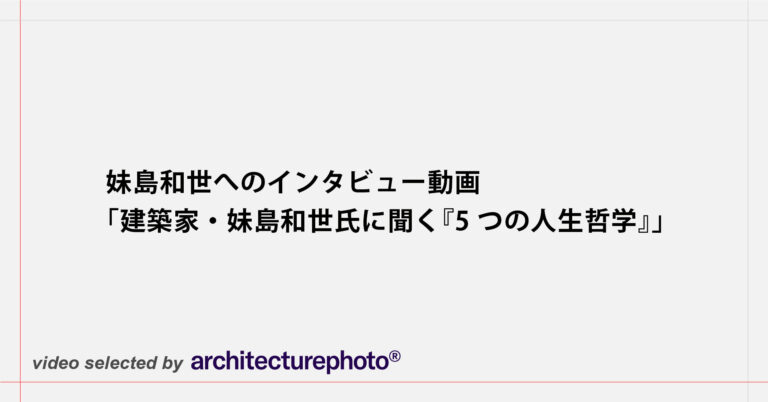ペーター・メルクリが2021年4月7日にオンラインで行った講演「My Facade Material」の動画です。ファサードデザインのアプローチや比例システムについて語られています。英語字幕付きです。イギリスのアーキテクチャー・ファンデーションの主催で行われたものです。この講演はペーター・メルクリがキュレーションするオンラインイベント「For the Love of Architecture」の第一回目として行われたもの。今後、MOS Architects、貝島桃代、Adam Jasperとそれぞれメルクリが対話するようです。そして最後にメルクリが自身の近作等を紹介するレクチャーを行います。
video archive
「建築家ノーマン・フォスター氏:環境に配慮した建造物について語る」という日本語字幕付動画が、Bloombergのウェブサイトに掲載されています。
安藤忠雄の、中国で行われている二つの展覧会の会場動画です。制作は中国の動画メディア一条。「水の教会」等が原寸大で再現されています。Fosun Art Center Shanghaiでの「Tadao Ando: Endeavors」展は2021年6月6日まで、He Art Museumでの「Beyond: Tadao Ando and Art」展は2021年8月1日まで解されています。
小山光+KEY OPERATION INC. / ARCHITECTSが、自身が設計した横浜の「関内の集合住宅」を解説している動画です。
関内駅から徒歩5分の不老町の交差点に面する角地に計画された集合住宅。
この敷地には元々、横浜防火帯建築として知られる「不老町2丁目第一共同ビル」という宮内建築設計による小さな県公社共同ビルが建っていた。交差点を挟んで反対側には横浜文化会館のPFI再整備事業としてメインアリーナの工事が進められており、近くの教育文化センター跡地には関東学院大学のキャンパスも建設されていて、エリア全体が大きく様変わりしてきている。
このプロジェクトでも既存が4階建てだったが、11階建てのマンションとして計画され、22-25m2程度の小さめの面積の住戸が94戸集まる投資用の賃貸住宅として分譲される。アリーナの正面に位置することもあり、建物全体をファサードでアピールする事も求められた。
佐藤可士和と村上隆の対談等の13個の動画が公開されています。国立新美術館での佐藤の個展に合わせて制作されたものです。アーキテクチャーフォトでは佐藤可士和展の会場写真を特集記事として公開しています。
国立新美術館は、「さまざまな美術表現を紹介し、新たな視点を提起する美術館」を活動方針とし、デザインや建築の展覧会を定期的に開催してきました。この理念に基づく企画として、日本を代表するクリエイティブディレクター、佐藤可士和(1965年生)の過去最大規模となる個展を開催いたします。
1990年代、株式会社博報堂でアートディレクターとして斬新な広告プロジェクトを次々と手がけた佐藤は、 2000年の独立以来、企業から、幼稚園、病院、ミュージアム、エンターテインメント界、ファッション界、地域産業まで、多種多様な分野で革新的なVI・CI計画やブランド戦略を手がけ、内外から注目を集めてきました。
本展では、佐藤自身がキュレーションする会場構成のなかで、約30年にわたる活動の軌跡を多角的に紹介します。
フランク・ロイド・ライトの設計で1923年に完成した「帝国ホテル」を再現した高クオリティなCG動画。ライトの財団が公開したものです。現在はその一部が愛知の明治村に移築されています。建設の経緯などはこちらのページにも。
Frank Lloyd Wright: The Lost Works explores some of Wright’s most important demolished and unrealized structures. The project brings these lost buildings to life through immersive digital animations reconstructed from Wright’s original plans and drawings, along with archival photographs.
Two years in the making and based on a Japanese publication of original plans and historical photos, Frank Lloyd Wright: The Lost Works – The Imperial Hotel is a comprehensive digitally-animated recreation of the exterior (Part I) and interior (Part II) of this masterpiece.
西沢立衛が、チリに完成させた週末住宅「House in Los Vilos」について語っている動画です。2019年に竣工した住宅で写真や図面はこちらのページで閲覧できます。
妹島和世へのインタビュー動画「建築家・妹島和世氏に聞く『5つの人生哲学』」です。ビジネススクールの企画で行われたものです。収録は2020年10月。
グロービス経営大学院学長の堀義人が、日本を代表するビジネスリーダーに5つの質問(能力開発/挑戦/試練/仲間/志)を投げかけ、その人生哲学を解き明かします。第3回目のゲストは、建築家の妹島和代氏。今までどうやって能力を鍛えてきたか、独立後の挑戦について、妹島氏の哲学についてなど聞いていきます。(肩書きは2020年10月撮影当時のもの)
《動画内容》
・イントロダクション
・能力開発
・挑戦
・試練
・仲間
・志
・質問、回答



ヘルツォーグ&ド・ムーロンらの設計で完成した、香港の美術館「M+」です。一般公開は、2021年末を予定しています。「M+」は美術館の完成以前より、倉俣史朗が設計した寿司店の購入や、アーキグラムのドローイングの購入などの活動でも注目を集めていました
以下、リリーステキストの翻訳、要約です
「M+」は、ミュージアム建物の建設完了という重要な節目を迎えました。2020年12月24日にミュージアムビルの占有許可を取得したことで、「M+」は2021年末に一般公開されることになります。
世界的に有名な建築事務所であるヘルツォーグ&ド・ムーロン、TFPファレルズ、アラップのグローバルチームが共同で設計したM+の建物は、世界の芸術文化のランドスケープに新たに加わり、国際的な建築のアイコンとなることが期待されます。香港の西九龍文化区、ビクトリア・ハーバーのウォーターフロントに位置する「M+」は、20世紀から21世紀にかけてのビジュアル・アート、デザイン、建築、映像、香港のビジュアル・カルチャーの収集、展示、解釈を目的とした、アジア初のグローバルな現代ビジュアル・カルチャー・ミュージアムです。
堂々とした建築形態は、広大な基壇と印象的な細身のタワーという、水平方向と垂直方向のモニュメンタルなヴォリュームで構成されています。それは香港の建築景観のユニークなタイポロジーを読み解き、地元の都市条件に対する建築家の感性を反映しています。このビルの地下には、MTRエアポートエクスプレスと東涌線が走っています。この既存の敷地条件は、設計・施工上の課題であると同時に、「M+」の出発点にもなっています。鉄道トンネルの周辺を掘削することで、ダイナミックでまた入れ替わるインスタレーションを受け入れるための建物のアンカーとなる「ファウンド・スペース」が生まれました。
65,000㎡の「M+」には、33のギャラリーからなる17,000㎡の展示スペースがあります。また、3つの映画館、メディアテーク、ラーニングハブ、リサーチセンター、ミュージアムショップ、レストラン、ティー&コーヒーバー、メンバーズラウンジ、オフィススペースがあり、ビクトリア・ハーバーの壮大な景色を望むルーフガーデンも備えています。ほとんどのギャラリーは2階の大きな基壇レベルに配置されており、来館者は流動的で相互につながった展示を体験することができます。タワーは、香港の都市景観との視覚的な対話を定義しています。基壇とタワーは、光と天候の変化を反映するセラミックタイルで覆われたコンクリート構造として一体化されており、周辺のガラスやスチール製の高層ビルから際立っています。また、タワーのファサードにはミュージアムに関連するコンテンツを表示するためのLEDシステムが設置されており、香港の活気ある夜の環境に独特の貢献をしています。
美術館のスタッフは、「M+」の建物と保存・保管施設(CSF)に入居し活動を開始しました。2021年末の「M+」の一般公開に向けて、環境の安定化、スペースの調整、常設コレクションの移動、コレクション作品やオブジェの設置などの準備が始まっています。
西九龍文化区庁の最高経営責任者代理であるベティ・フォンは、西九龍文化区と香港の双方にとって「M+」が持つ意義を強調します。「『M+』は、将来的に香港で最も象徴的な建築物の一つとなり、地元住民や観光客が必ず訪れる文化的なランドマークになると信じています」。『M+』の完成は、2019年に予定されている『戯曲中心』、『自由空間』、『アートパーク』と合わせて、エキサイティングな新開発段階に移行しつつある西九龍文化地区プロジェクトの重要な節目となります」と述べています。
「M+」のミュージアム・ディレクターであるスハンニャ・ラッフェルは、「M+」の建設の旅が完了したことの重要性を強調しています。「これはミュージアムにとって大きな節目となります。建物が完成したことを記念して、オープニングの準備が本格化しています。私たちは恒久的な家に引越しましたが、もうすぐ香港や海外からの訪問者を『M+』に迎えることができると言えることに感激しています」。
ヘルツォーグ&ド・ムーロンの創業パートナーであるジャック・ヘルツォーグは、「M+」のデザインと実現に対する野心を明確に語っています。「『M+』は確かに、アジアにおける主要な視覚文化のミュージアムになる可能性を秘めています。多様性、平等性、あらゆる種類の芸術へのアクセスが最初から表現されています。それは世界文化としての我々の進むべき道を最もよく表しています。このような多様性と広さは『M+』のDNAの一部です。これにより『M+』は非常に地域に根ざした美術館であると同時に、普遍的で開かれた美術館であり、世界中の人々や来館者のためのものであるのです」。
ラフール・メロトラ(Rahul Mehrotra)によるTEDでのトーク「一過性の都市に見る驚異の建築術」(日本語字幕付)です。ラフールはインドとアメリカを拠点に活動する建築家でハーバード大学GSDでも教鞭をとっています。
インドでは12年に1度、巨大な都市がクンブ・メーラという宗教行事のために突如出現します。10週間費やして建設されるこの都市は、1週間で解体されます。全ての都市機能を備えたこの一過性の街から何を学べるでしょうか?この先見性のあるトークを通して建築家で都市デザインの専門家のラフール・メロトラが追求するのは、どこにでも移動できて、適合し、跡かたなく消えることさえ可能な、地球への影響が最小限の一過性の都市を建設することの有益さです。
モーフォシスのトム・メインによるオンライン講演の動画です。「Architects not Architecture」の主催で行われたもの。
SHARE MADのマ・ヤンソンによるオンライン講演の動画
MADのマ・ヤンソンによるオンライン講演の動画です。 「Architects not Architecture」の主催で行われたものです。
熊本地震における、くまもとアートポリスの取組みを紹介する動画「住民に寄り添い 後世に残る建築 ~ゆとり・あたたかさ・ふれあい~」が公開されています。
東日本大震災において、建築家伊東豊雄氏(くまもとアートポリスコミッショナー)の提案により始まった「みんなの家」。
「みんなの家」は被災された方々が再び立ち上がって新しい生活を回復するための拠点として整備されました。
この考え方は、熊本地震においても生かされました。
被災者の痛みの最小化を目指し、くまもとアートポリスとともに応急仮設住宅団地や「みんなの家」の整備に取り組まれた皆さまに想いを語っていただきました。
ぜひご覧ください。ナビゲーター くまモン
インタビュー(敬称略)
伊東豊雄(くまもとアートポリスコミッショナー、建築家)
田邉肇(震災当時 熊本県土木部建築住宅局長、熊本県建築住宅センター)
久原英司(木造仮設住宅団地を担当、熊本工務店ネットワーク)
岡野道子(益城町テクノのみんなの家及び甲佐町住まいの復興拠点施設設計、岡野道子建築設計事務所)
塚本由晴(被災した公民館を再建する「みんなの家」設計、アトリエ・ワン)
千葉学(被災した公民館を再建する「みんなの家」設計、千葉学建築計画事務所)
四宮利克(被災した公民館を再建する「みんなの家」を担当、モリスデザイン)
井上智大(熊本県建築課)
また、ダイジェスト版も公開されています
中川エリカの建築展「JOY in Architecture」について、藤村龍至・西田司・萬玉直子が語っている動画「中川エリカ展を藤村龍至さんと面白がる」です。中川の建築展「JOY in Architecture」については、アーキテクチャーフォトでも特集記事として掲載しています。
本日はZOOMのラジオを飛び出し、TOTOギャラリー・間で開催中の中川エリカ展を、藤村龍至さんと一緒に面白がる企画です。
ゲスト:藤村龍至/RFA主宰・東京藝術大学建築科准教授
モデレーター:萬玉直子/オンデザイン
主催:東京理科大学西田研究室
毛綱毅曠が1972年に完成させた北海道の住宅「反住器」の現在の様子を紹介する動画です。同建築を訪問した藤森照信のコメントも収録されています。
乾久美子と中川エリカが「リサーチと設計」をテーマに対談している動画。中川のギャラリー・間での個展に合わせて企画されたものです。動画の公開は2021年4月末までの期間限定予定との事。
第一線で活躍する建築家と中川エリカ氏が、展覧会の現場にて、中川氏の建築思想に深く関係する問題意識を手がかりに語り合います。双方向の批評を通じて、世代を超えた「建築のよろこび」「建築批評をする/されるよろこび」を見出そうとする試みです。
第3回:2021年3月1日(月)公開
出演:乾 久美子氏(建築家) × 中川エリカ氏
テーマ:リサーチと設計