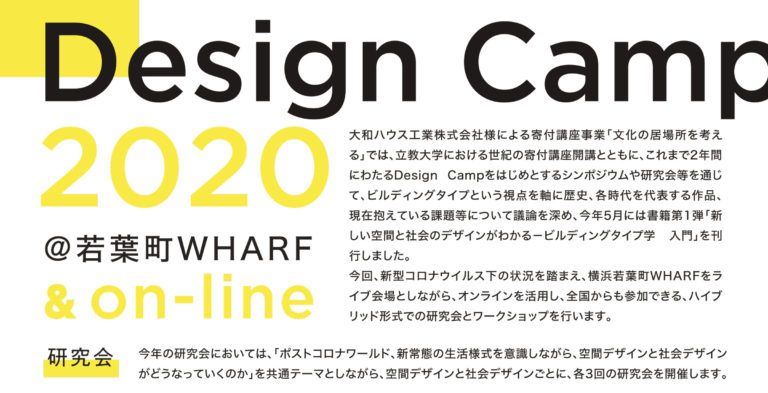SHARE 辻琢磨による連載エッセイ “川の向こう側で建築を学ぶ日々” 第6回「少しずつ自分を過小評価して仕事を取る建築家」

少しずつ自分を過小評価して仕事を取る建築家
このエッセイも6回目、ようやく折返しである。同時にこの10月で渡辺事務所の在籍予定期間の半分が終わる。この1年半、渡辺さんや事務所のメンバーの傍らで、本当にいろいろなことを学んできた。渡辺事務所では、僕が入所してから既に4つの物件が竣工し、さらに今も3つの現場が動いている。このスピード感もさることながら、仕事の量も常に一定以上ある。要するに経営的にも比較的うまくいっている。
渡辺さんは、地方都市における建築家の振る舞いや仕事への向き合い方を特に意識して活動する建築家で、このエッセイでも何度か紹介しているように、例えば施工者や施主との付き合い方一つとってもコミュニケーションを大切にし、多方面に対して無理のない建築の作り方を推し進めている。その地に足のついた態度は仕事の取り方(入り方)にも鮮明に現れる。今回は、仕事を泥臭く取る渡辺さんの経営術について書いてみたい。
現在、渡辺事務所の仕事は、大きく分けて4つのタイプに分けられる。一つは磐田市が発注する公共案件、もう一つはヤマハ発動機グループがクライアントのスポーツ系施設、3つ目が第一商事という磐田市拠点の企業がクライアントのコインランドリーを中心とした小規模建築、最後がウェブ経由を含む単発のプロジェクト群である。
端的に言って、特定の世界企業(民間)と地方自治体行政(公共)の両方をクライアントとして継続的に関わっているアーキテクトは、世界的にも稀ではないだろうか。
しかしこの状況は一朝一夕にしてならず。渡辺さんはまだ住宅の仕事が多かった頃から、地道な種まきを続けてきた。その結果がようやく今出始めていると言っても良いだろうし、今も華やかな竣工ラッシュの裏で泥臭くクライアントの信頼を得る努力を怠っていない。その地道で粘り強い「営業」について筆を進めていきたい。
世界のYAMAHAを相手にする
最新作である「ヤマハマリーナ浜名湖」は、ヤマハ発動機グループがクライアントの2つ目の新築案件である。指名コンペで設計者に選定されジュビロアスリートセンターを竣工させたことで確たる信頼を得て、ヤマハ発動機から浜名湖マリーナの事務所施設の建替えと、敷地内の機能整理を受注したという経緯がある。
そもそも、「ジュビロアスリートセンター」の前から、「種まき」は始まっていた。
以下の写真はクリックで拡大します
実は渡辺事務所は設立当初から、ヤマハ発動機の仕事を継続的に受注していた。例えば、既存工場の測量や既存図復元という大変地味な仕事である。そもそも建築の図面は、一般的には施工者に作ってもらうために設計者が描くものだが、長い目で見ると違う役割もある。その建築が次に改修される際に、次の設計者がその参考にするというリレーのバトンのような役割だ。改修の際は法規的にも確認申請の際に出された設計図書や検査済証と呼ばれる行政のお墨付きが施主や施工者によって保存されていれば、次の設計に非常に役に立つ。
上記の既存図面の復元については、今後の改修計画のために正確な現況図が必要となり、渡辺事務所に話がきたのだった。渡辺さんはこの既存図の復元に「必要以上の」モチベーションを発揮した。測量は細かく採寸し、それを隅々まで求められている以上の図面として納品したという。その甲斐もあって、「ジュビロアスリートセンター」の指名コンペのオファーが届き、そのコンペも勝ち抜いて難工事を竣工させたことでヤマハグループの信頼を勝ち得ることができた。
そして、このヤマハマリーナの話が舞い込んだ。当初は既存のクラブハウスの建替のみの計画だったそうだが、話を進めるうちに、断続的に敷地内で改変が加えられた現状を整理するとともに、高低差で断絶された敷地内の動線計画も刷新する方針に変化していったという。その過程で、単なる新築というよりも都市計画法上の開発行為の範囲内で工事を進めるべく過去の履歴を精査しつつ、法規的な整理整頓も行い、既存のクラブハウス、ボートラック、サービス工場をすべて刷新する一大計画となった。また、新クラブハウスの背後の崖上には、土地をヤマハ発動機グループが所有し、利用権を地元ホテルに貸し出して運営されている結婚式場が控えており、このホテル側との交渉も進めながら新しい動線を確保している。
以下の写真はクリックで拡大します

建築自体についても見えない苦労があった。この建築を崖に持たせるために擁壁のような巨大な基礎が仕込まれているのだが、建物が覆いかぶさって全く見えない。そのような見えない基礎工事に、実に工期の2/3ほどが当てられた。
以下の写真はクリックで拡大します

このような一つの建築の計画で終わらない複雑な要件と地形をすべて扱う方向にプロジェクトが動いていったのは、渡辺さんの醸す安心感が大きいはずだ。地道に既存図の復元から出発したからこその信頼と安心感である。そしてその後、今もヤマハグループのプロジェクトは複数動いている。
磐田市との地道な関係づくり
もう一つの大きなクライアントは地元行政の公共案件の施主、つまり磐田市である。大きなところで言えば入札で取った「豊岡中央交流センター」、「磐田卓球場ラリーナ」に続き、指名コンペで勝利してこの夏に竣工させた「磐田市立総合病院研修棟」が実績として挙げられる。
以下の写真はクリックで拡大します



そしてこの背後にもまた、地道な「営業努力」があった。豊岡以前、入札参加条件の規模や売上だけでなく行政からの信頼を得るため、渡辺事務所では磐田市の学校の耐震改修工事の設計を入札で落としたり、設計業務ではない、建物の保全やメンテナンス状態をチェックする定期調査も入札で落とし、入札参加資格のハードルを少しずつクリアしていくとともに行政関係者の信頼を醸成していった。
入札について、ここで少し補足しておこう。設計入札とは公共事業の発注の際に、税金をなるべく客観的な指標でもって公正公平に使うための仕組みで、その流れを超ざっくり説明すると、売上や事務所の規模等の指標でハードルが設けられている入札参加資格審査をクリアした設計事務所が、公告された公共事業の余条件(建物の用途や規模といった基本条件)から設計料を「入札」し、一番低い設計料を入札した設計事務所が受注するという仕組みである。設計者選定のプロセスで意匠性やデザインを問わないこの仕組には賛否あるが、渡辺事務所はともかくこの仕組を利用して数多くの公共建築を実現させてきた。この真意については、次回以降に改めて詳細に書いてみたい。
建築のプロジェクトとしても、上記以外に、合板サンドイッチパネルの変形梁による無柱空間が特徴的な「北部包括支援センター」や、建物の形状はすべて同じで、敷地の形状やシチュエーションによって配置計画と基礎構造設計のみを変更することによって各地区に建設された「磐田市コミュニティ消防センター」、磐田市が運営する既存施設(ワークピア磐田)内のレストランを改装して、新たにコワーキングスペースを作るプロジェクトの基本構想「はじまりのオフィス」、海と水路に囲まれた敷地に建つその平面が特徴的な「6角形の津波避難タワー」など、その規模は小さいながらも柔軟かつ着実に、実績と信頼、公共の経験を積み上げることで、大規模な公共案件の足がかりとしていったのだ。
以下の写真はクリックで拡大します

特に「北部包括支援センター」はわずか12坪の平屋建てで、その規模の小ささによって監理業務は業務範囲外(通常は営繕工事として磐田市によって設計監理される)だったのにも関わらず、足繁く現場に通い実質的な監理を無償で行っている。短期的にみるとこの無償業務は必ずしも良いことではない。建築設計のプロフェッションとして、職能の単なる安売りはすべきではないからである。しかし渡辺さんは行政との良好な関係づくりを優先したのだった(目と鼻の先にある現場を放っておけないという理由もあったそうだが笑)。
上記の案件は、建築プロジェクトとしてみればどれも規模が小さく、決して華やかな見せ所があるような類のプログラムではない。しかしどれもが行政、市民にとっては切実に必要とされるプログラムであり、渡辺事務所としても来たるその後の大規模な公共案件のための先行投資的な意味合いもあって、渡辺さんは積極的にこれらのプロジェクトに取り組んだ。
地元企業との継続的なコラボレーション
冷静に考えると、住宅やリノベーションの仕事が多くなっている昨今の建築業界の中で、上記した2つの巨大クライアントを相手にするだけでも凄まじい実績と言えそうなのだが、渡辺さんはよく「特定のクライアントや種類の仕事」だけに取り組まないことの重要性を話してくれる。どれかが倒れたときに突然事務所が立ち行かなくなることが明白だからだ。
第三のクライントは地元磐田の中小企業「第一商事」。以前話した「四八会」という同世代の経営ネットワークが縁で知り合った社長と意気投合し、現在、実に6店舗目となるコインランドリーを計画中である。同一クライアントで同一機能を6店舗ということは、上記した特定のクライアント、特定の種類の仕事となるわけだが、まさにこの点において、この第一商事のコインランドリーのプロジェクトだけで事務所が回っているわけではないのだ(現時点で言えば、ランドリー以外にも、ヤマハ案件が2つ、個人案件が3つ、他企業案件が3つほど動いている。)。
以下の写真はクリックで拡大します






このランドリーのプロジェクトがここまで続いている背景にも、もはや当然、特筆すべき地道な仕事がある。
一つはガソリンスタンド「ENEOS 磐田中央町SS」の設計だ。ガソリンスタンドはENEOSの仕様規定がありデザインできる範囲が限られるため意匠設計を専門とする渡辺事務所のようなアトリエ事務所は敬遠するケースが多い。しかしそもそもガソリンスタンド事業は第一商事の主幹事業でもあり、クライアントからの期待は大きかった(第一商事もまた、複数の事業を展開することでリスクヘッジを図る地元の優良企業である)。その厳しい制約の中、防火状可能な範囲での緑化や、上質なサービスルームの設置、仕様規定のかからない鉄骨部材の組み方や外壁を検討し、可能な限り良質な建築を生み出した。
以下の写真はクリックで拡大します
また、このタイミングで会社理念を実践した社員を表彰するムービーの制作にも関わっていて、会社のブランディングや会社自体についても多角的に知る機会が生まれた。こうしたランドリーとは直接関係のない継続的なクライアントとの関係づくりが、ランドリーの継続的な発注にも良い影響を及ぼしていることは言うまでもないだろう。
地域の建築力を底上げするという先行投資
こうした渡辺さんの未来への投資の感覚は、自分の事務所のプロジェクトに対してだけに向けられているわけではない。
僕もこれまで幾度となく渡辺さんに実務のアドバイスを貰っているし、磐田・浜松界隈の若手建築家の相談窓口にもなっているのだが、そのような兄貴的振る舞いも回り回って自分の未来への投資につながっていることになるという。若手が育つことによって地域の建築文化の底上げにつながり、例えば入札案件にしても質の高い建築をつくることができる建築家が複数いれば、より安心して入札にも参加できる。自分が駄目でもあの人がきっと良い建築を作ってくれるだろうというある種の信頼は、地域の建築を考える上でとても重要な感覚だと思う。
そう言えば先日、同じ磐田市で活動する建築家の後藤周平さんが事務所を訪れた。定期調査について渡辺さんにヒアリングをしたいとのことだった。入札への参加の仕方や定期調査の提出書類、気をつけるべきことまで、渡辺さんは事務所で受けた過去の同様の案件の書類を見せながら、丁寧に説明していた。そして僕も来週、自分の事務所のプロジェクトのことで話を聞く予定だ。
未来のための泥臭い感覚
渡辺さんの現在の影の努力は、未来のクライアントのからの信頼につながっている(今回ご紹介しているのは成功したものなので芽が出なかった投資も当然ある)。この、渡辺さんの経営における泥臭く未来を信じる感覚(その時はきついけど後々確実に花開くだろうという感覚)は結構独特で、言葉を選ばずに言えば建築家というよりも経営者の感覚に近い。良質な建築を生み出すことが建築設計者の使命の一つであることは間違いないから、渡辺さんもどのような仕事だとしても妥協せず、少しでも良質な空間と建築を目指していると思う。しかしそれだけでは足りないのだと、渡辺さんは考えているのではないかと僕は感じる。
改めて、渡辺さんに話を聞いた。
「少しずつ自分を過小評価するというか、自分の職能にもちろん自信はあるのだけど、その能力は必ずしも行政や大企業の担当者には届いていないと思う。そう思うところからスタートしているんじゃないかな。当初はあえてデザインと関係ない定期調査や図面復元のような仕事を信頼を得るために取っていたようなところがあって、いきなり新築はむしろやりたくなかった。その信頼を得た状態で大きな建築に向き合う方が得策に思えたし、自分のデザインの能力については、当時多かった住宅案件のオープンハウス情報を興味がありそうな担当者に積極的に送ったりもしていたよ。」
建築家の職能に胡座をかくわけでもなく、妥協を許してぬるい設計を実現させてしまうこともせず、ただただ現実を直視して、その時できること/できないことを見極めた上で、泥臭く地道な選択をひたすら繰り返すこと。言葉にすると至極真っ当な態度で、これまで何度も言及しているように、そんなことは建築家として当然の振る舞いだろうと思う人も少なくないかもしれない。しかし本当はその先にしか皆が夢見る「大きな」建築の実現はあり得ないのではないかと、渡辺さんに日々思わされている。
辻琢磨
1986年静岡県生まれ。2008年横浜国立大学建設学科建築学コース卒業。2010年横浜国立大学大学院建築都市スクールY¬GSA修了。2011年403architecture [dajiba]設立。2017年辻琢磨建築企画事務所設立。
現在、名古屋造形大学特任講師、滋賀県立大学、東北大学非常勤講師、渡辺隆建築設計事務所非常勤職員。2014年「富塚の天井」にて第30回吉岡賞受賞※。2016年ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展日本館にて審査員特別表彰※。
※403architecture [dajiba]
■連載エッセイ“川の向こう側で建築を学ぶ日々”