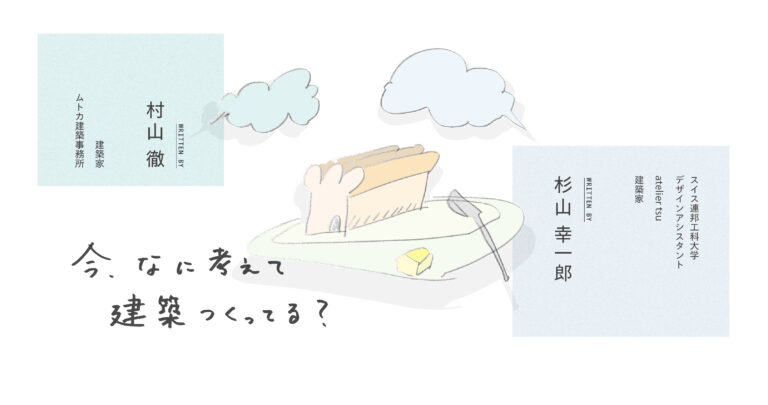SHARE 辻琢磨による連載エッセイ ”川の向こう側で建築を学ぶ日々” 第10回「川の向こう側から自分がいた場所を眺めて」

川の向こう側から自分がいた場所を眺めて
思い描いていた「修行」ではなかった3年間
2019年の4月から渡辺事務所での勤務が始まり、3年が経った。
勤務の日は朝8時に家を出て、息子を保育園に預け、天竜川沿いを走り、9時に出社、18時に退社。ざっとこの堤防を200往復以上、累計1800時間を超える非常勤職員の生活は、今振り返ると大変充実した時間だった。
当初は「修行」と銘打って週2-3回の勤務を想定していたが、二年目からは名古屋造形大学の特任講師の仕事が始まり、継続して403architecture [dajiba]のプロジェクトも動いていたこともあり、お茶汲み/電話取り/玄関対応は続けたものの、最終的には週1勤務となった。当初想定していた図面や申請図書の作成、拾いといった下積み業務は一年目こそ関われたが、週一勤務では断続的になってしまうため継続的には担うことがなかなかできなくなった。
代わりに、所内でその時に抱える大小様々な課題を渡辺さんやスタッフと一緒に解決するための打ち合わせが増え、あるいは現場に一緒に行き、設計監理業務を手伝うことも自分の役割の一つとなった。その他に、プロジェクト初期の案出しや、建築賞の応募資料の作成、所々の図面修正、断続的な法規チェック、外部打ち合わせへのスポット参加、書類提出や買い出しなどの庶務、など、ちょっとずつ事務所を助けるような役回りに自然となっていった。
建築家の重たい悩み
中でも一番大きかった業務?が渡辺さんとの昼食である。
スタッフ3名(2022年3月時点)の事務所規模では考えられない量の膨大な仕事に追われる渡辺さんの、その時その時の悩みや困りごと(もちろんたわいもない話もしたし僕の相談にもたくさん乗ってもらった)を聞くという役まわりである。
当然ここでは話せない内容が多いのだが、実はそこでの話が最も勉強になったのかもしれない。渡辺さんの重たい悩みを聞くたびに、あぁ自分がもしこんな大変な状況に出くわしたら無理だな、建築とはなんと大変な仕事なんだろう。と自分の建築に対するハードルが日増しに高くなっていった。そういう厳しい現実をお昼に聞いた帰り道は、運転しながら、なぜあんな大変なのに渡辺さんは建築を続けるのだろう、と渡辺さんの建築のキャリアに思いを馳せた。
建築へのモチベーションがどこから来るのか。渡辺さんと話す時にいつも辿り着く最終的な結論(極論)は二つ。
「建築が好きだから」と「人生の間が持つから」。純粋無垢な少年のようで、同時に山にこもった仙人の言葉にも見える渡辺さんの結論に、二人で毎回笑った。
価値観の混乱
渡辺さんの建築、建築家としての印象は、(入札というキラーワードも相まって)地方で土着的に地道にクオリティの高い建築をつくる、という受け取られ方が多いだろう。つまりこれははっきり言えるが、世界でグローバルに活躍しあっと驚く革新的な建築をつくるような、雑誌の誌面を賑わせるようなたぐいの建築、建築家ではない。
しかし、3年間、渡辺さんを、渡辺さんがつくる建築を間近で見てきて、自分にはその両者の間に差や線引が本当にあるのか、わからなくなった。一言で言えば、良い建築、目指すべき建築がわからなくなってしまった。
建築家が違えばディテールも違う、届けられる媒体も違うし、当然建築の形態も違う。施工者やクライアントとの関係性の作り方も違う。共通するのは、苦労をしてでもより良い建築を建てたいという意志だ。その意志に優劣はつけられないだろう。あるいは街場の大工だって工務店だって、組織設計事務所だって、スーパーゼネコンだって、与えられた土俵の中でより良い建築(建物かもしれないけれど)をつくろうとしているはずで、そうだとしたら、建築家か組織か、設計者か大工か、という違いは少なくとも僕からは消え失せる。
日本で建築教育を受けると、何故か建築家のつくった建築が一番良いという価値観に、設計が優秀な人ほど染まっていく傾向があるように思う。そして少なくとも僕は(決して優秀な学生ではなかったが)そういう価値観を持った学生だった。
その価値観は今でも僕に根付いて自分の建築観を支えてくれているが、3年間、渡辺さんの不思議なスタンスに触れ続けたことで、ともかくキャンセルされたのである。キャンセルされて価値観がゼロになったというよりも、フラットになったという感覚が近い。
背景への想像力
固執せずに割切る判断(第2回)、事務所経営(第3回、第6回)、施工者との関係(第4回)、番頭というポジション(第5回)、公共建築と入札(第7回、第8回)、福利厚生(第9回)。思えばここまで書いてきたのは、いわゆるスター建築家が海外を飛び回って天才的な巨匠スケッチで建築をつくる、というようなこれまでの建築家像(すでに相当古くなった言い回しではあるものの、依然として皆の脳内OSに憧れとして染み付いているだろう)ではほとんどすくうことができなかった、建築、あるいは建築文化を支える背景に迫るものとなった。そしてこれらは、キャリアも活動場所も関係なく、どの建築家の背景にも既に存在しているであろう。
建築をつくる背景にある、泥臭さや地道さ、目立たないかもしれないが確実に必要な努力。
こうして僕のテキストも「メディア」に掲載され、少なくない読者に読まれていくのだろうが、「メディア」が皆さんに伝える情報は、どうしても限りがあり、例えばその建築のすべてを伝えることはできない。従って伝える側は、作品であれば図面や写真、テキストによって情報をコンパクトにして伝える努力をする。その時に、皆が求める情報は、わかりやすい方が伝搬性が高い。その、ある種のわかりやすさの象徴が、建築においてはスター建築家の格好の良い姿や革新的な建築なのである。
しかし、そのような革新的な建築は言わずもがな、どんな建築にもその背景には膨大な努力と調整があり、その努力に優劣はない。このエッセイは、渡辺事務所の実例を通して、その背景にある努力への眼差しを読者が身につけるためのものになったと思う。「メディア」を入口にして、背景への想像力を働かせるのは読者一人一人だ。
立ち止まって想像する
今、これを読んでいる方に伝えたい。誰か(有名無名は問わない)が一生懸命つくった建築や芸術を一瞬で消費してしまうのではなく、1分でも良いから立ち止まって、その建築や、設計者の背景にある地道な努力を想像してみてほしい。そのような想像力が少しずつでも醸成されていけば、日本の建築文化は、西欧社会とは違った独自のプライドを築くことができると思う。
渡辺さんの建築や建築家としてのスタンス、僕と渡辺さんの関係は稀有だが、それらを通した背景への眼差しは誰もが持てるはずだ。もっと言えば、渡辺さんの背景に匹敵するストーリーを持った建築や建築事務所は、まだ知られていないだけで、目を凝らし、適切に描写しさえすれば日本にも無数にあるはずである。
建築を巡る鮮やかなグラデーション
建築にまつわる、目立ちにくい背景にまで目を向ければ、建築、建築家を巡る鮮やかなグラデーションに気づくことができるだろう。確固たる建築家像が溶け出している。概念がグラデーションになればそのどこかに自分を適切に置くことができる。もしそれができたなら、「巨匠になれなくとも」、今の、あるいは未来の自分を肯定できる気がするのだ。
巨匠になっても良いし、番頭でボスを支えても良い。コンペを目指しても良いし、入札に参加して公共を学ぶのも良い。世界を股にかけても良いし、地方でじっくり作っても良い。アトリエでもハウスメーカーでもゼネコンでも建築をつくることはできる。どれか一つを選ぶ必要もない。
建築という確固たる概念に自分を合わせるというより、自分という存在がまずあって、その次に自らを建築のグラデーションに位置づけること。読者一人一人にとって、このテキストがその手助けになったのであれば、これに勝る喜びは無い。
さあ、お前はどうするのか
さて、ここまで書いて、さあ、お前はどうするのか。というある種の「分かりやすさ」を求める声が聞こえてきそうなので、素直にお答えしたい(お節介)。
今、すべてが横一線となった判断基準から、自分は何を良しとして建築を考えていけばいいか。良い建築は本当によくわからなった(見方次第で全部良い)のだが、良い建築家、目指すべき事務所の姿や、歩みたいと思える生き方はなんとなく見えてきたので少し紹介していきたい。
ゆっくりつくる
まず、頭にあるのは、「ゆっくりつくる」ということである。
急ぐとお金は回るかもしれないが、建築家、施工者、施主、行政、といった関わる人たちの違いが際立ち、軋轢になってそれが多方面に対するストレスになる。「ここはこうすべきだ」という設計者の意図が先鋭化して伝わることで、「それはできない」と跳ね返され、設計者のエゴだと揶揄される。
逆も然りであるが、空気感を時間をかけて共有するだけでも相互理解は深まり、思考のズレがお互い担うべき役割に変化していく瞬間がある。渡辺さんの仕事のアプローチは、磐田市という場所に根を張ることで、行政、施工者、クライアントといった建築をつくるときに関係する人たちや、磐田という環境それ自体との相互理解を年々深めることに寄与している(もちろんプロジェクトベースで見た時には、渡辺さんも例えば公共建築や企業相手の場合は予算執行のタイミングという締切に急がされていることもあったわけで、現実的なバランスは常に探り続けねばならない)。
しかし翻って考えてみると、ゆっくりつくるということは、急いでたくさんつくるよりも一生につくる建築の数が限られるということだが、僕はそれで良いと思うようになった。むしろなるべくゆっくりつくりたい。だからこそ地方を拠点にしていると言っても過言ないだろう。家賃や固定費が高い東京では、ゆっくりしていたら自分の首が締まる一方だからだ。都市圏でのつくりかたを否定するつもりは毛頭ないし、建築界にとってクオリティの高い建築が一つでも多く増えることは手放しで喜べることだ。しかしとにかく今僕は、ゆっくり建築を考えたい。
豊かな環境で仕事する
もう一つは豊かな環境で仕事するということである。渡辺事務所での皆の振る舞いを見ていると、無理がない。徹夜はしないし、事務所は広く、あくせくした感じがない。こういう環境で建築を考えたいと思った。
以下の写真はクリックで拡大します
そして一方で、渡辺さんの仕事ぶりを間近に見て、建築を立ち上げる難しさを改めて知った。特に公共建築や大規模な建築のように、関わる人が多くなればなるほど、関係調整に時間が割かれ、なにか問題が起こった際の火消しも迅速さが求められる。端的に、そのプレッシャーに僕は自分が耐えられるか分からない。建築を実現する、ということはこれほどまでに難しいことなのかと、何度も心が折れそうになった。だからとにかく豊かな環境を用意して建築という大きな山に立ち向かうしかないのだと思っている。
向こうみずに独立してガムシャラにやってきたこの10年は消えないし、今でも一つ一つの仕事や仲間とこれまで積み上げてきた議論に誇りを持っているが、建築の「難しさ」を知ってしまった今、正直言って10年前のロケットみたいな勢いを保つことはできないだろうと感じている。だからこそ、建築に向き合う豊かな環境をまずは自分で拵えたい。
豊かな環境という意味では、渡辺事務所との関係も、これで一区切りは付くが、渡辺さんとも何度も議論し、関係をゼロに戻すのも勿体無いので、続けられるように続けようという話をしている。具体的には、今後僕は渡辺事務所の特別顧問に就任し、月一回渡辺事務所に今まで通りいくことになった。また今年から加入した個人事務所のスタッフも渡辺事務所と共同で雇用することになり、柔軟な仕事環境を渡辺事務所と築いていくつもりだ。
理解を超えた縁を手繰り寄せる
同じ場所に根付いて10年もすると、世間が狭くなるというか、関係が関係を呼び、脳内のシナプスが連続するような感じで人間関係や場所の縁が時に自らの理解を超えて連鎖していく。その象徴的な事例を紹介したい。
今僕は浜松の郊外の元々祖父母が住んでいた一軒家に住んでいるのだが、その図面の帯を見て驚いた。偶然にも我が家は、渡辺さんが独立前に勤めていた竹下建築設計事務所が設計したのだった。
以下の写真はクリックで拡大します
そもそも僕はこの家を継ぐ予定ではなかったが、住むはずだった叔父が早逝し、その後祖母が他界、祖父も施設で暮らしているために空き家となっていた時期と僕のプライベートでの結婚や息子の誕生が偶然重なって住むことになった。
その時はまだ渡辺事務所の勤務は決まっておらず、結果的にこの家と渡辺さんとが結びついたのであった。これには縁を感じざるを得ないが、そもそも縁とは関係を意識して生きていけば無数に結びつく可能性があるのだとしたら、この世界は潜在的な縁で満たされているようにも思える。
少なくとも自分が独立してからは、関係を意識して地域の中で生きてきたという実感があって、その一つの象徴が、僕の自邸と渡辺さんとの結びつきとして理解される。関係の中で生きる、関係を意識して生きる、ということは、日本の地方でなくとも、どの場所でもできるだろう。
僕の場合はこのきっかけとして建築があったが、建築でなくともできるだろう。もし一人一人がこのような意識を少しでも持つことができれば、「ストレス」という言葉もいつかは消えるかもしれない。自分が関係の中に生きる、という実感は、生の実感とほぼ同義だと思うからだ。僕や渡辺さんの場合は、地方で建築を考えることがこの生の実感に役立った。果たして皆さんはどうだろうか。
肯定できる価値観は多い方が良い
渡辺事務所が始まって3年、特に名古屋造形大学が始まってからの2年間は、渡辺事務所と大学に加えて、403architecture [dajiba]の活動や個人事務所、学会委員会など、家庭も含めると日毎に、あるいは時間毎に自分の立場や役割、周囲との関係性を目まぐるしく変化させながら日々が過ぎていった。その負荷は並大抵のものではなく、しばしば心身のバランスも崩れた。
父になって初めて親の気持ちが分かるように、スタッフとなることでスタッフの気持ちが少しは分かるようになり、あるいは前述したように建築家のスタンスや建築の良し悪しも視点を変えれば違う見え方になる、という時の「視点」が随分と増えた。それらが同時並行で見えるわけなので結果的に「よくわからなくなってしまった」のだが、肯定できる視点が増えたのは少なくとも自分にとっては良いことだと感じている。
自分以外の他者の価値観を肯定するというのはとても難しいことだし、視点を増やすのは混乱を招く。しかし、僕はその方が自由で、豊かだと思う。否定する価値観が多いよりも、肯定できる価値観が多い方が良いと思うからだ。そのためには、単に「思いやりを持つ」という言葉では足りない。自分の周りに多くの信頼できる他者がいる、という環境を用意しなければならない。しかし多様な他者は1箇所に集まってくれない。ならば自分が動くしかない。ということで草鞋を何足も履いていたのだと今振り返れば思う。渡辺事務所での勤務は、信頼できる他者との関係の実践という意味において、僕にとって象徴的な経験となった。
川の向こう側から自分がいた場所を眺める
このエッセイのタイトルの題材でもあり、通勤の道でもあった浜松と磐田の間を流れる天竜川は、かつて暴れ天竜と呼ばれ、多くの氾濫に流域の民は苦しめられたが、明治維新後に金原明善という郷土の偉人が私財を投げ打ってつくった堤防によって治められた。
そんな立派な背景を持つ堤防を、毎週、ローンを組んだポロで走りながら、自分の将来や過去をぼんやり考える。今、3年前は向こう側だった磐田から3年前にいた浜松を眺め、間を流れる天竜川は以前に増して雄大に感じられる。保育園で息子を送った朝、渡辺さんの悩みを聞いた帰り道、自分に建築ができるのだろうか、このまま価値観の混乱を抱えていて大丈夫だろうかと自問した。渡辺事務所の3年間を経験して、率直に建築の難しさと自分の限界を知った。「修行」を終えて強くなったどころか、自信が無くなったと言っても良いかもしれない。
しかし、環境や、人、自然、歴史、建築が持つ背景への想像力が3年前より確実に身についたと思う。
今は、そうした背景に敬意を持って、偉大なる他者に積極的に寄りかかって良いのだと思える。自分だけで頑張るには自分の能力は足りないということが渡辺さんの隣にいてよく分かった(特に精神面が足りない)。しかし同時に、渡辺さんの隣に寺田さんという心強い番頭さんがいるように、自分だけが頑張る必要もないということは大きな気付きだった。
そうした他者への想像力と敬意を携え、今までより自由に、豊かな環境で、これからも建築に向き合っていきたい。今自分が確かに言えることはこれが精一杯である。
いかがだっただろうか。10回のエッセイは大変だったが、3年に渡る自分の学びを読者の方々に毎回届けることができる、というのはとても貴重で歓びに満ち溢れた体験だった。
最後に、今回のような貴重な機会を与えてくれたarhchitecturephoto編集長の後藤さん、非常に変則的な働き方を快く受け入れてくれた渡辺事務所の皆さん、そして渡辺さんへの感謝に代えて、このエッセイを終えたい。
本当に有難うございました。
以下の写真はクリックで拡大します
辻琢磨
1986年静岡県生まれ。2008年横浜国立大学建設学科建築学コース卒業。2010年横浜国立大学大学院建築都市スクールY¬GSA修了。2011年403architecture [dajiba]設立。2017年辻琢磨建築企画事務所設立。
現在、名古屋造形大学特任講師、渡辺隆建築設計事務所特別顧問。2014年「富塚の天井」にて第30回吉岡賞受賞※。2016年ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展日本館にて審査員特別表彰※。
※403architecture [dajiba]
■連載エッセイ“川の向こう側で建築を学ぶ日々”