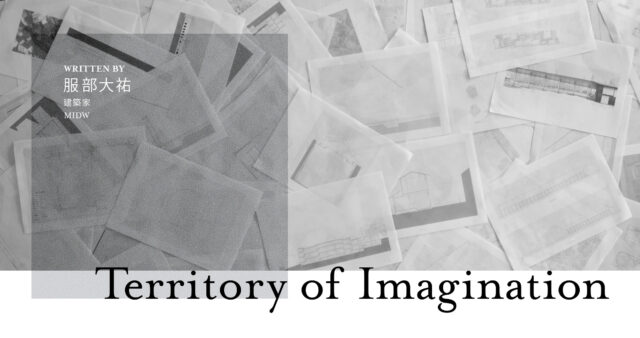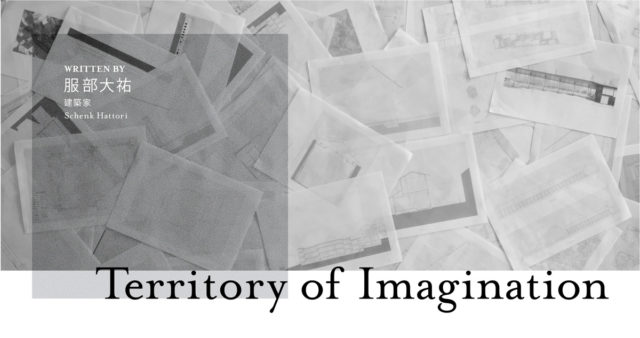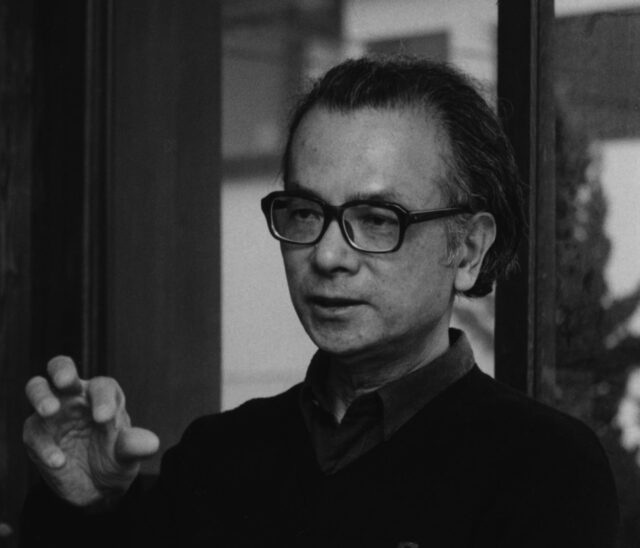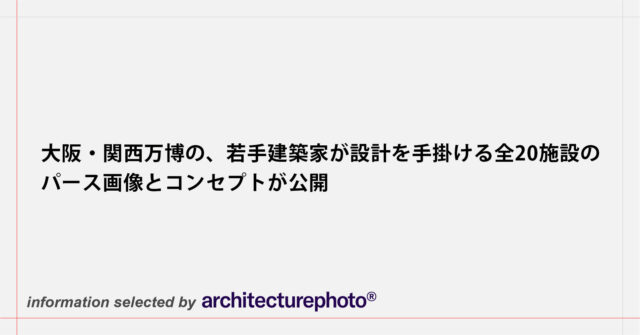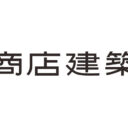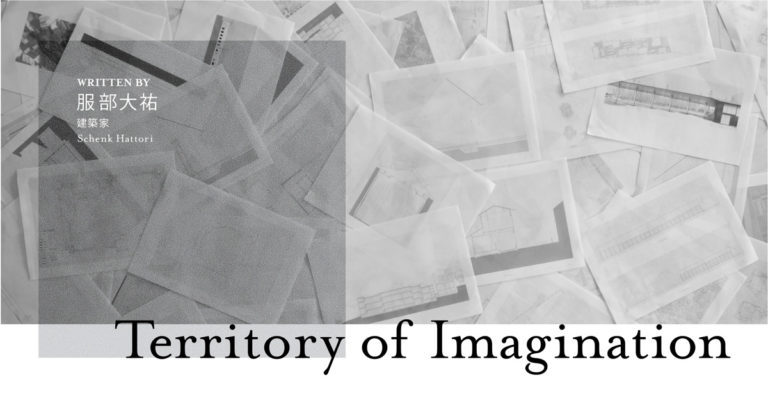
SHARE 服部大祐による連載エッセイ“Territory of Imagination” 第4回「Schenk Hattori 京都オフィス」

Schenk Hattori 京都オフィス
気がつけばベルギーから帰国して5年、京都に引っ越して3年ほどが経ちました。
2014年にベルギーで建築設計事務所を開設した後、2017年に日本でも設計活動を行おうと帰ってきましたのですが時の流れは早いものです(この辺りの話は第1回をご覧ください)。
さて、約一年ぶりのエッセイとなる今回ですが、この間に完成した我々の京都オフィスとそれを取り巻く出来事について書いてみたいと思います。
オフィスができるまで
なんで京都に移ってきたのか、という質問をほぼ全ての人に聞かれるのですが、正直なところ、さほど明確な理由はありません。強いて言うとすれば、いつも協働している構造家の柳室純さんとの打ち合わせで頻繁に京都に遊びに来ていたことや、その流れで柳室さんを通して森田一弥さんや魚谷繁礼さん、池井健さんといった先輩建築家と仲良くなったことが大きいかも知れません。彼らから冗談半分で「京都に来ちゃいなよ!」と言われたのを真に受けて、「確かに京都好きだし有りだな」くらいの軽い気持ちで引っ越してきました。
東京から京都へ引っ越すということが、一大事だとは思っていませんし、東京とのつながりは、京都に住んだとしても切れるものでは無いだろうと考えたことが理由の一つだったように思います。(実際、いまだにウチで関わっている国内案件の大半は東京です)
町屋を改修してオフィスにする
京都での暮らしも落ち着き、「そろそろオフィス欲しいなぁ」と言っていたある日、前述の魚谷さんから連絡があり、「キミのオフィス見つけといたよ」と。突然の話で驚きつつ、「そうですか、どうも有難うございます」と伝え、後日よくよく聞いてみると、魚谷さんのところに空き家になっている持ち物件の活用方法を考えて欲しいという依頼があり、「ちょうどいい奴がいたな」ということで僕を紹介してくれたということでした。
現地を見に行ってみると、路地に面した三軒長屋の両端二軒が対象物件でした。二軒続きではなく、間に一軒挟まっているため、物理的に一体での使用は難しいですが、二軒に何かしらの関わりを持たせることで、その間にある路地空間まで含めた関係を生むことが出来ると考え、両方の使い方をあわせて検討することにしました。
その結果、片方を自分たちで借り、もう一軒は、友人伝手に東京で広告系クリエイティブ関連の会社をやっている方達が「京都に自分たちのベースになる場所が欲しい」ということで借りてくれることになりました。
二軒同時で改修をして、一つを僕らSchenk Hattoriの京都オフィス、もう一つを彼らが運営する四条半(四条と五条の中間だから)という名前のギャラリーとして使い始めました。
以下の写真はクリックで拡大します



レクチャーイベント
オフィスが出来たことで、当然ながら通勤が生まれました。距離はほんの徒歩7、8分程度ですが、それでも在宅ワークだった以前と比べると、移動することで頭や気分の切り替えが出来るので、生活にオンオフのスイッチが加わったように感じます。
そして、オフィスがあると気軽に人を呼びやすいので、協働者やクライアントとの打ち合わせ、アルバイトの学生の受け入れも容易に行えるようになりました。
オフィスが出来てからの新しい試みとして、余剰のスペースを使ったレクチャーイベントを定期的に開催しています。メンドリジオに居た頃、学校で毎月何かしらのレクチャーが行われており、校舎の中庭でビールを片手に建築家の話を聞くのが楽しかったので、そういった雰囲気の会が作れたら、と思って始めました。
去年は春から秋にかけて、意匠や構造の設計者、映像の研究者など、僕と同世代の話し手をゲストに招き、月に一回程度のペースで計6回開催しました。20人程度の小規模イベントの為、話し手とオーディエンスの距離感も近く、アルコールも手伝ってレクチャーの最中から質問が飛ぶ、オープンな雰囲気の会になっています。
以下の写真はクリックで拡大します


春になり徐々に暖かくなってきたので、そろそろ再開を考えていたところ、長谷川豪さんから突然の連絡があり、仕事帰りに京都に立ち寄るということで、急遽今年の第一回イベントを開催しました。直前に開催が決まったため、話し手を含めて全部で10人程での濃密な会になりました。
去年は話し手が自由に喋りたい内容を用意してくる、という形でやっていましたが、長谷川さん、木村俊介さん(SSK)新森くん(Niimori Jamison)、僕という4名が話し手となったこの回は、議論の的を絞るためにテーマを設定してみることにしました。
テーマ決めのアイデアを出し合っている中で、長谷川さんから「いま若い建築家たちが社会性をテーマに色々な動きをしているなかで、キミらは割とオーソドックスなアプローチで建築をつくっている。それでも、いまの社会からの影響は当然受けているはずだ。いまの時代の建築を考えるときに、どうしたって建築と社会の関係を考えることから逃れられない。このあたりをどう考えるのか、議論するのはどうだろう」という意見が出ました。
そこで、「建築と社会」というテーマを設定し、それぞれが社会に対する自身のスタンスを示す作品をプレゼンし、その後、会場全員でのディスカッションという流れで行うことにしました。
建築の作り方について
プレゼンを準備する中で、僕自身初めて意識的に「社会」と自作の関係について考えたように思います。
そして、プレゼンでは建築の「作り方」についての話を用意しました。
Schenk Hattoriでは、自分たちのアイデアを形にする際、その建築がどのような構成で、あるいはどのような構法で、あるいはどのような材料で作られるのかといったことに関して、常に意識的に設計を行なっています。
例を挙げると、「Exhibition Pavilion in deSingel」(共同設計:SUGIBERRY)では、3ヶ月という展示期間に対する建築行為として、会場施設にストックされていた過去の展示パネルのリユーズによるパヴィリオンを設計しました。パネルを中庭の地面の土に突き刺して並べるというプリミティブな工法によって、仮設的でありながら中庭の僅かな傾斜を顕在化させる架構としています。
以下の写真はクリックで拡大します
「慶應SFC SBCプロジェクト 滞在棟3」(共同設計:アーキスコープ、miCo.、POINT、Sho Kurokawa architects)では、「使い方を限定しない学びの場」という構想の下、空間に微小な方向性や性格の変化を生み出す湾曲グリッドを設定しました。そこに幾何学上の調整を加えて、全スパンの部材長さを統一し、接合部のパターンを数種類に限定することで、施工の単純化を実現しました。
以下の写真はクリックで拡大します
「Entrance Pavilion in Palingbeek」では、広大な森を巡る自然保護区のエントランスに、移動する中で性格が少しずつ変化する軒下空間を構想し、微細にずれながら反復する短手方向の構造ユニットを考案しました。その上で、現地の自然や施工条件を考慮したプレファブ構法によって、工期短縮と冬期の施工を可能にしました。
以下の写真はクリックで拡大します
建築には様々な人が関わりますが、それを一旦「考える主体」「作る主体」「使う主体」に分けて考えてみます。僕ら設計者は「考える主体」、メーカーさんや職人さんは「作る主体」、個人案件の施主や公共案件の市民などが「使う主体」に該当するかと思います。
設計者が、作り方を考えた設計をすることで、まずは自分たちの設計プロセスにおいて、アイデアを具体的な形に翻訳していく上で守るべきものや課題が明確になり、チーム内の意思決定がスムーズに進むという利点があります。
また、作り手や使い手との関係においては、議論の中で設計内容の変更や修正が必要になることが頻繁にあります。そういった際には、設計のアイデアとその作り方の関連を明確にしておくことで、僕らがその建築で大事にしている考えが、職人さんや施主にも共有される感覚があります。
例えば現場で職人さんや現場監督さんから「こっちの方が安い」といったことだけではなく「そういう作り方でやるのなら、ここの納まりはこういう詳細にしたらどうか」といったような積極的な提案が出て来たり、施主からは「この作り方だから、必然こういう形になるってことね」という様に好みを超えた部分で提案に納得して貰ったりといった具合です。つまり、これらの例では「作り方」が異なる主体間の橋渡し役として機能してくれています。
もう少し踏み込んだ言い方をすると、「作り方」を介して、建築に込められた意思が異なる主体間で共有されていくことで、一つの建築の価値が拡がりを持つのではないか、そして、その拡がりが建築文化を発展させ、社会へと還元されていくのではないか、ということです。
「考えること」と「作ること」と「使うこと」が繋がる、そういう建築を世に生む出すことで、社会がより豊かになっていくのでは、と考えています。
ものごとを切り分けて考えない
他の3人のプレゼンに関しては、それぞれがまたどこかで話す機会があるかと思うので、ここでは要点のみを記します。
新森くんは、自らが購入した建物を、街の休憩所として開放する改修計画の紹介をしていました。
街のリサーチを行い、そこに必要となる機能の選定も行っており、そのプロセスもプログラムも、街に開かれた建築の在り方を示しています。と同時に、建物単体のスケールでの空間的な操作を随所で行っており、あくまでも建築それ自体の持つ強度を探る意思が明確に示されています。どちらが先行するでもなく、「建築」と「社会」を対等な関係として扱おうとする態度が現れており、興味深く感じました。
以下の写真はクリックで拡大します


木村さんは、建築が生み出す「ここではないどこか」へと向かう想像力についての話をしていました。
題材が単身者の住居の改修計画で、主な操作が内部空間に対するものだったこともあり、こちらは一見、個人に寄り添った作品のように見えます。その中で、人の想像力を駆り立てるトリガーとして、空間に挿入された「虚のボリューム」の話をしていました。
「想像力を働かせることが、ヒトが個人を超えて世界とつながっていくための鍵であり、その媒介となることで建築は社会性を獲得する」ということかと思いますが、これは僕の興味ともすごく近いように思え、印象に残っています。
以下の写真はクリックで拡大します


長谷川さんは、現場が進行中の、瀬戸内海沿いに建つ造船所の社員寮について話していましたが、自作のプレゼン以上に、僕ら3人との対話に多くの時間を割いてくれていました。
議論のスタートとして、新森くんの「私」と「公」・木村さんの「こちら側」と「あちら側」・僕の「考えること」と「作ること」、3人に共通する、それらの「ものごとを切り分けて考えない姿勢」が、今の社会に対する建築の在り方を考える上で大事なんだろう、という話をしていました。
世代論的なものは好きでは無いと前置きした上で、長谷川さん達や、それ以前の世代は、どちらかと言うと自身の見ている世界を他者のそれと切り分ける事で、独自性を示していた部分が強かったが、僕ら若手(と呼ばれている)世代にはそういう意識が薄く、むしろ様々な面で物事をシームレスに繋いでいくような印象がある、ということでした。
それは、設計の考え方のみならず、働き方に関しても同様で、僕や新森くんのように、海外留学の経験の後、設計活動としても実際に日本と海外の二拠点で建築を作るケースなどは、これまでにはほとんど無かった面白い働き方だということを指摘されていました。
一方で、その「切り分けない」ことの中には、「よく分からない不確かなモノや価値観」なんかも内包されるべきだということでした。Schenk Hattori の建築に対しては、「キミらのやっていることはとてもよく分かる。それは、違う言い方をすると、すでに存在する批評軸で十分語ることの出来る建築だということ。もう一歩先に進むために、積極的に、未だ得体の知れないモノや価値観も内包するような建築を目指すべきじゃないか。そうやって新しい批評軸を作っていくことが、いつの時代にも建築に課された使命ではないか。」という指摘を頂きました。
以下の写真はクリックで拡大します
偶然にも僕ら3人のことを学生時代から知っている長谷川さんですが、会の開催にあたり「同じ建築家同士、対等に議論をしよう」と言ってくれていました。ただ、いざ議論が始まると、そこはやはり先輩建築家である長谷川さんから、批評も交えつつ、大きく背中を押してもらったように思います。
会の盛り上がりはその後の飲み会でも延々と続き、結局夜更けまで皆で建築談義をしていました。この独特の熱気や密度は、やはり小規模かつ形式張っていない会ならではの良さだと思うので、そこは継続しつつ、今年からは少しストイックな勉強会に近いものも織り交ぜながらやって行きたいと思っています。
感覚の数値化
もう一つオフィスを作ってからの新しい試みとして、一年を通したオフィスの室内環境の計測を行っています。古い町家を改修しており、さらに建築面積の約半分を地表面の土剥き出しの状態にしているので、室内とはいえ、ほとんど屋外のような環境になっています。
Arupの環境エンジニアで、現在京都工芸繊維大学で教鞭も執る菅健太郎さんがオフィスに打合せに来た際に、この状態を面白がってくれて、計測データを取ってみることになりました。オフィスの様々な場所に温度計・湿度計を設置し、通り土間や諸室の温度・湿度、壁面温度や地表面温度の計測を行っています。
計測をしてみて面白かったことの一つに、感覚の数値化が挙げられます。温度と湿度の関係については元々知っていたつもりでしたが、やっぱりそれが数字になって見えることで、よりその関係について意識的になります。
例えば、夏場屋外からオフィスに入ると、一瞬ひんやりとした感じがあるのですが、次の瞬間から蒸し暑さが体を包み込みます。これは、地表面の土が剥き出しになっていることによる影響が大きいです。
屋外気温35℃・湿度60%の時に、室内温度32℃・湿度75%といった具合に、気温としては、屋外と比べて3-5℃度程低いのですが、代わりに湿度が10-15%程高くなっています。如何に湿度が体感に大きく作用しているかがよく分かります。
以下の写真はクリックで拡大します

地表面の土による夏場の冷却効果や調湿効果を期待していましたが、実際には上記のように残念ながらさほど効果はありませんでした。むしろ、地表面からの底冷えにより冬場の厳しさが増す分、住環境としてはマイナス面の方が大きいと言わざるを得ないでしょう。
やはり床を上げたり、土を叩いたりして、室内の床に何かしらの仕上げを施すのは、これまで先人が自らの住環境を改善する過程で確立してきた環境との付き合い方で、そういう蓄積を無視することが得策じゃない、と改めて思い知らされました。
とはいえ、屋内に手付かずの地表面がある状態は、建物がその中に何か野生を宿しているようで、なかなか気に入っています。どうやって快適性との折り合いをつけていくか、これから考えていこうと思っています。
町家のフレキシビリティー
最近いくつかの町家改修に携わって驚いたのは、それが如何にフレキシブルな作りをしているか、ということです。
壁は真壁造りで柱梁は露出していることが多いので、あとは簡単に剥がせる床や天井をめくると、ほとんど全ての構造材を目視することが出来ます。そして、腐っているところは取り替えて、弱いところは補強する、といった適切な処置を施せば、残りの部分はかなりの自由度を持って変えていくことが出来ます。
100年単位の時を経て、様々な使い手に受け継がれながら、多くの場合、何らかの改修を繰り返されながら、それでも町家がその原型を留めつつ現代に残ってきているのは、町家の持つこのフレキシブルな「作られ方」と無関係ではないでしょう。
もちろん、Schenk Hattori 京都オフィスも、都市スケールで広く汎用性を獲得しているそうした町家の「作られ方」を下地として改修されたプロジェクトの一つです。そして、ここでは僕らが考える主体でもあり、使う主体でもあります。完成から1年が経ち、四季を経験したことで、幾つかの問題点・改善点が見つかりました。これからまた少しずつ手を加えながら棲みこなしていくつもりです。自分たちで考え、時には作り、そして使っていくことで、時間と共に生きられた建築にしていけたらと思っています。
京都全体を見渡すと、まだまだ沢山の町家や路地が残っていますが、年々その数が減っているのもまた事実です。オフィスのある路地にも、10軒ほどの町家が軒を連ねていますが、その半数が空き家になっています。これらが近い将来一気に取り壊されて、通りに面した新築マンションに建て替わる、といった悲しいことも、あながち起こり得ないとは言い切れません。
単なるノスタルジーではなく、どんな使い方にも変え得るフレキシビリティーを内在した町家の「作られ方」は、その存在を残し続けていくに足る、大きな武器になるはずです。
小さな路地に建つ小さな建築を通して、少しでもこの街にとって良い影響となる設計活動を続けていけたら、と思っています。
服部大祐
1985年 横浜生まれ。2008年 慶應義塾大学環境情報学部, 神奈川 – 学部卒業。2012年 Accademia di Architettura, Mendrisio (CH) – 修士課程修了。2014年 Schenk Hattori, Antwerp (BE) / 京都 – 共同主宰。2014-15年 University Antwerp (BE) – ワークショップ講師。2016-17年 Academie van Bouwkunst, Rotterdam (NL) – 非常勤講師。2019年- 慶應義塾大学環境情報学部, 神奈川 – 非常勤講師。
■連載エッセイ“Territory of Imagination”