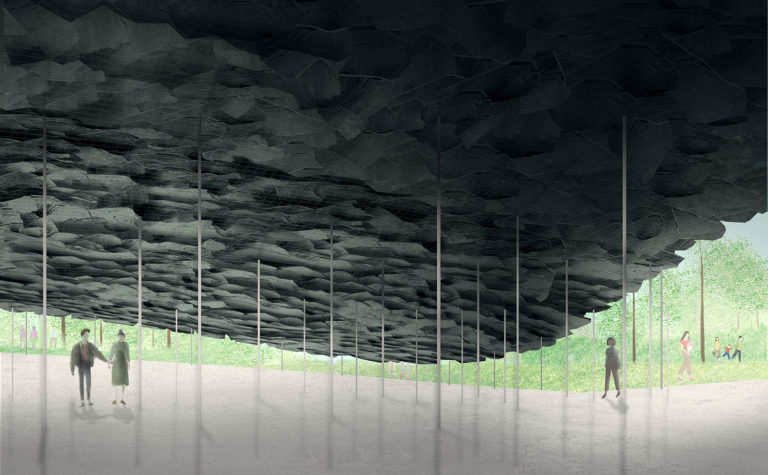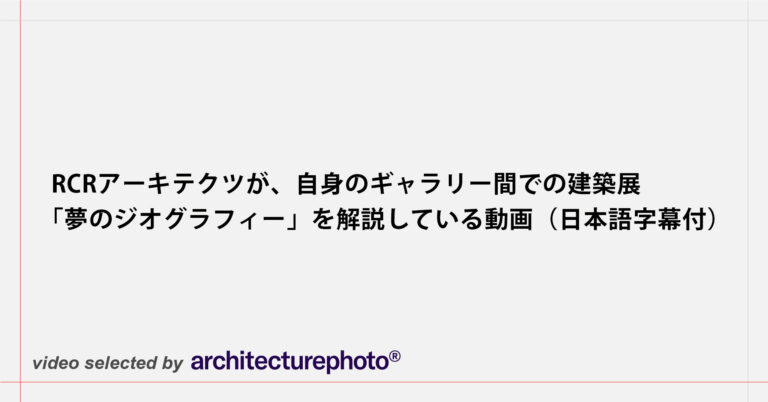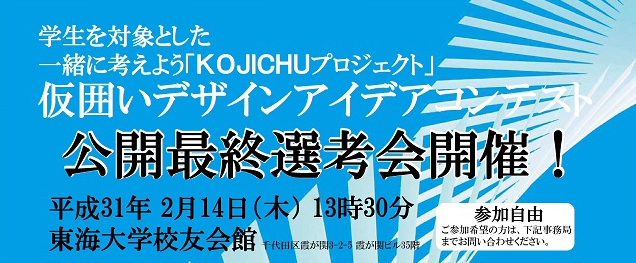SHARE 建築展「イームズハウス:より良い暮らしを実現するデザイン」が、東京・江東区のGallery A4で開催
- 日程
- 2019年3月19日(火)–5月30日(木)
建築展「イームズハウス:より良い暮らしを実現するデザイン」が、東京・江東区のGallery A4で開催されます。会期は2019年3月19日~5月30日。※日曜・祝日休館。開館時間10〜18時(最終日は17時)。会期中には岸和郎と植田実による対談イベント「イームズハウスの魅力を語る」も企画されています。
「イームズハウス」は、チャールズ・イームズとレイ・イームズ夫妻の住宅兼スタジオで、1949年に完成し、今日でも世界の名建築の一つに数えられています。類い稀な才能に恵まれた二人のデザイナーが創り上げたデザインの軌跡を辿ることによって、そこにある現代性と未来につながる普遍的な価値を見つめます。
また、イームズの思想を後世に伝えるため、この住宅の長期的な保存修復計画が策定され、2014年に第一ステージが完了しました。モダニズム建築保存の成功事例として紹介するとともに、その意義を伝えます。
更に、イームズ夫妻が日本のデザイン界と交流し、相互に影響しあったエピソードや、イームズ・オフィスが制作した映像等も紹介します。