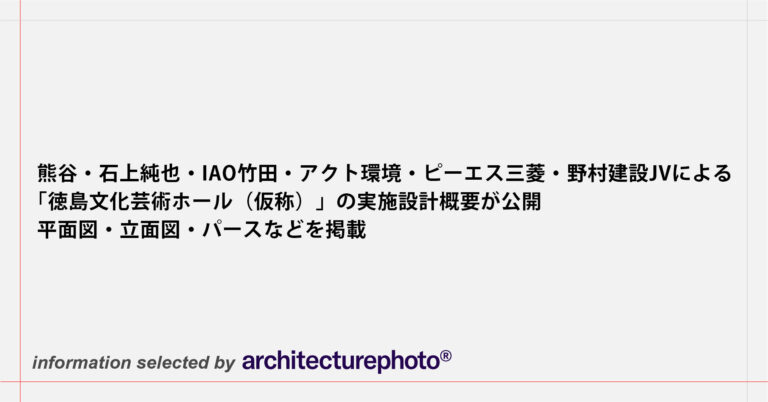【ap job更新】 全国各地を対象とし、建築の力で地域を豊かにする活動を行う「ようび」が、設計スタッフ(2025年新卒・既卒・経験者)を募集中[ようび] 家具工房
【ap job更新】 全国各地を対象とし、建築の力で地域を豊かにする活動を行う「ようび」が、設計スタッフ(2025年新卒・既卒・経験者)を募集中[ようび] 家具工房
全国各地を対象とし、建築の力で地域を豊かにする活動を行う「ようび」の、設計スタッフ(2025年新卒・既卒・経験者)募集のお知らせです。詳しくは、ジョブボードの当該ページにてご確認ください。アーキテクチャーフォトジョブボードには、その他にも、色々な事務所の求人情報が掲載されています。
新規の求人の投稿はこちらからお気軽にお問い合わせください。
地域の拠点をつくる仕事
建築設計職(2025年新卒・既卒・経験者)を1名募集しています。
『建築には、地域を変える可能性がある』
『地域は建築でより豊かに、楽しくなる』
自分や家族の生活や時間が大切にされるようになった昨今、多くの人が「サードプレイス」を求めるようになりました。
地域の人々のサードプレイスになるような建築案件が増えてきています。
鳥取県智頭町にある「那岐小学校」の利活用の事例をあげます。
地域の人から長く愛され続けてきた那岐小学校が、少子化による小学校統合に伴い、廃校となってしまいました。
地域に愛され続けた場所がなくなったことで、地域の人々の心にぽかんと大きな空洞が生まれてしまいました。
それはまるで、地域の魅力が減ってしまったような感覚です。
地域の人々は、那岐小学校を人々が集う、まさしく「サードプレイス」のような場所に変えたいと思っていました。
そこで、私たちようびは、地域の人々と協議やワークショップを行いながら設計を進め、那岐小学校を地域の人々のサードプレイスになるようなコミュニティスペースに変化させました。
空洞だった那岐小学校は、銭湯、宿泊施設、ショップ、遊び場、公民館、調理室など、様々な体験ができる場所を提供し、老若男女問わず楽しめる、地域の人々の生活を豊かにする空間に生まれ変わりました。
建築には、力があり
建築には、地域の未来を変える可能性があります。
今までのストーリーとこれからのストーリーを、建築という手法でつなげ、地域への役割を変えるような建築を全国各地で数多く設計しています。
また、弊社は建築設計だけでなく、インテリアデザイン部と家具制作工場があり、空間のトータルデザインも行っています。
考えたデザインのアウトプットが迅速にできるので、デザインのブラッシュアップが目に見える形で実感が出来ます。
他の部署の社員と話ができる機会も多く、建築知識だけでなく、デザインや家具設計に関わる知識も身につけることができます。
一緒に地域に場を作り、地域をより豊かに面白くしていく仲間を募集いたします。