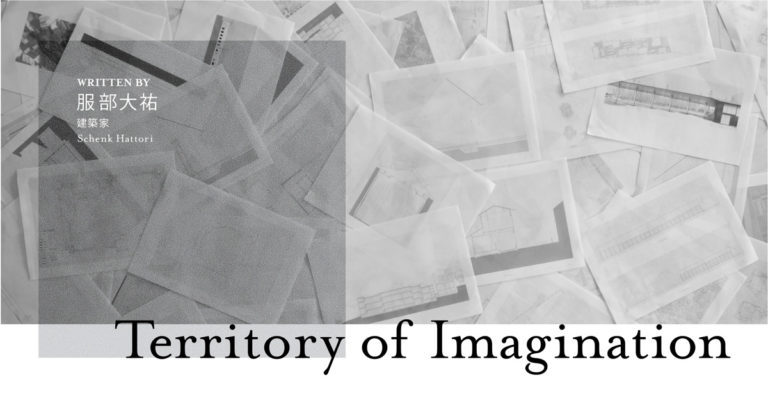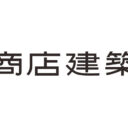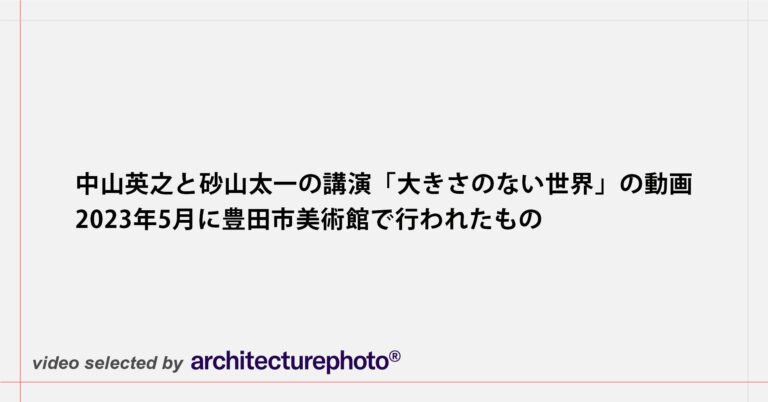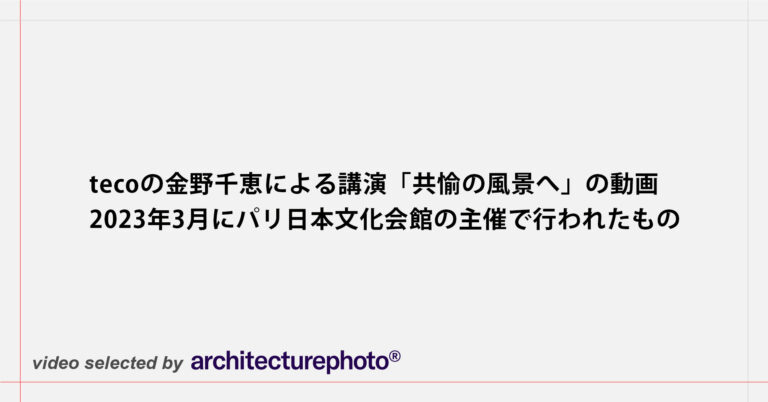池原靖史建築設計事務所が設計した、東京・大田区の、住宅改修「六郷の居拠」です。
ミニ開発の商品住宅を対象に計画されました。建築家は、既存間仕切を構造補強の上で取り除き、空の建物内に二枚の“ブロック”壁を配置しました。そして、“壁体”は生活機能を再配置すると共に住居への愛着を深める“拠り所”としての“機能”も担います。
防火地域に指定された敷地には同じデザインが反復されるように4軒の戸建て住宅が並ぶ。
いわゆる「ミニ開発」によって建てられた築20年弱の商品化住宅群であり、いずれも延床面積が99㎡、木造2階建ての準耐火建築物である。建主はそのうち1軒を、改修を前提に中古で購入した。
計画にあたり、まちなみの連続性を保持する意図から、建物の屋根と外壁は既存のまま利用する方針とした。軽量鉄骨を用いて構造補強したうえで間仕切り壁を取り除いた既存建物の外殻に対し、住まい全体を描き換えうる「確かさ」をもったコンクリートブロック積みの「壁体」を、慎重に布置する事とした。
建物内外の境界をときほぐし、また1階と2階をつなぐように2つの「壁体」が立ち上がると、幅員と明暗の深い階調が敷地内にレイアウトされ、それぞれの場所に相応しい生活機能が再配置される。
光庭、ライブラリー、ワークスペース、階段手摺、クローゼット等の機能を伴って立つ「壁体」はしかし、同時にそのどれでもない事が目指されている。定量化可能な機能の組み合わせからなる商品化住宅の中にあって、グレーの「壁体」はやがて生活を満たす以上の何か−−住人がこの場所を自分の住まいと認め愛着を深めていくための「拠りどころ」となる。それはおそらく建築の最も原初的な「機能」だろう。