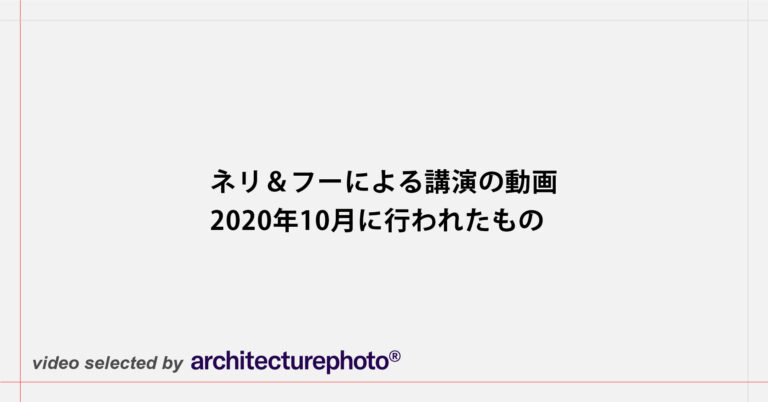
SHARE ネリ&フーが、2020年10月に行った講演の動画
ネリ&フーが、2020年10月に行った講演の動画です。RIBA(王立英国建築家協会)とVitrA(ヴィトラ ※トルコ発の水廻りメーカーの方)の共催で行われたものです。
ネリ&フーが、2020年10月に行った講演の動画です。RIBA(王立英国建築家協会)とVitrA(ヴィトラ ※トルコ発の水廻りメーカーの方)の共催で行われたものです。
横内敏人が2020年12月12月に行った講演「NIWA HOUSEの設計手法と理念について」の動画です。日本建築家協会東北支部福島地域会の主催で行われたものです。


北澤伸浩建築設計事務所が設計した、既存建売住宅の為の「リビングルームの棚」です。
戸建住宅のリビングのための棚である。
建物はいわゆる建売住宅で、普段自分たちが考えている住宅よりも圧倒的に開口部が少ない構成に驚かされた。さらに、隣地との関係からなのかアイレベルにはあまり開口がなく、吹抜になったリビングのハイサイドライトから、室内に大きく光を取り込む作りになっていた。真っ白な内装からは、少ない光を最大限に活かすような意図を感じさせられた。リビングの壁一面に、好きな本などを収納する棚がほしいという要望を頂いた。現状、趣味・仕事の部屋が別にあるが、お子さんがまだ小さいこともあり、なかなかそちらを有効に使うことができず、リビングで過ごす時間がほとんどだということだった。
普通に棚を設置していくと、この住宅で一番明るいスペースが窮屈になってしまう。
それを避けるため、まず背板をなくし、棚板の間隔も大きくすることにした。それによって、ものを棚に置いたときも、それぞれのマスの中で白い壁を大きく残すことができる。さらに、上にいくに従って棚の奥行をセットバックさせることで、高さ方向の圧迫感をなくし、同時にハイサイドライトからの光が棚の間に満たされ、室内を明るく広がりのあるまま維持できるように考えた。



長坂常 / スキーマ建築計画が設計した、東京・千代田区の物販店舗「and wander 丸の内」です。店舗の公式サイトはこちら。
and wanderのラインナップの特徴としてユニセックスで、かつ色のバリエーションが多いことがあげられる。
そのため、商品を一点一点手にとらないとわからない。むしろ一点一点手にとって発見していく楽しみこそがand wanderでの買い物の楽しみ方だと考えた。また、その一点一点の変化が、行くごと、そしてシーズンごとへの変化にもつながればと考え、レイアウトに変化が出やすいように天井から1500mmピッチの電源込みの構造グリッドシステムを吊るし、そこに照明、ハンガー、メッシュ、鏡、ポスター、フィッティングルームなどを自由に吊るせる可動システムをデザインした。
また、and wanderは上で記したある一定の仕組みは共通だが、出店場所の環境やターゲットの変化に伴い、その一店一店によって少しずつカスタマイズし、一店一店の異なるデザインをお客様に楽しんでもらいたいと考えた。
今回、間口が狭いものの奥に深いことからグリッドに配置されたライン照明が効果的に奥に続いている。また、並びが丸の内であることから大人向けのショップが多く、シックな暖色の色空間が続く。
その中デザインブランドとしての意思を強く出すために床をモルタルに白く浮かび上がるショップを目指した。


長坂常 / スキーマ建築計画が設計した、中国・香港の「ブルーボトルコーヒー 香港カフェ」です。店舗の公式サイトはこちら。
「美味しいコーヒーをシェアする」姿勢の表現であるカウンター越しの客とスタッフのFLATな関係を築くBLUE BOTTLE COFFEEはどこに行っても変わらない。
そして、その土地土地に合わせて変わり続けるBLUE BOTTLE COFFEEも変わらない。この香港は、豪華な巨大ビルディングの傍ら、細い横道には覆いかぶさるように汚れたアパートがひしめき、乱雑な看板や洗濯物が張り出している。その足元は所々で舗装が剥がれ水たまりができている。なので香港の印象として靴の裏は汚い印象がある。
そのせいと暖かい気候のせいかその足元の連なる商店では多く洗い流せるタイルが使われている。この場所もその一角にあるため、本計画ではタイルを使用することにした。
ただ、我々日本人がタイルを使うときに乾式ではなく、味わいをもつ湿式のタイルを使用することを考え、世界有数の陶磁器の生産地多治見で湿式のタイルを作ることにした。また、この建物がコンクリートであることから、そのコンクリートの構成色を使用してタイルを作ることで、シンプルで居心地の良い場所ができると考えた。


シェアする場をデザインする「成瀬・猪熊建築設計事務所」の、【募集職種】募集のお知らせです。詳しくは、ジョブボードの当該ページにてご確認ください。アーキテクチャーフォトジョブボードには、その他にも、色々な事務所の求人情報が掲載されています。
新規の求人の投稿はこちらからお気軽にお問い合わせください。
シェアする場をデザインする成瀬・猪熊建築設計事務所がプロジェクトチーフ及び経験者・2021年新卒を募集。
*今回の募集にあたり給与体系の見直しを行いました。
■VISION
私たちは、人々がシェアをする場をデザインしています。今、社会はますます急速に変わり始めています。
その中で私たちが目指すのは、建築を通して新しい豊かさを定義し続けることです。家族だけに縛られない多様な住まい、様々な国や地域をつなぐ宿泊、物の購入よりも体験に価値がおかれる商業施設、コミュニケーションとイノベーションがビジネスチャンスを作る時代の新しいオフィス、個人の人生に寄り添ったケアの場。これらはそれぞれ全く異なる用途でありながら、いずれも「シェア」によって価値を生み出します。
私たちはこうした「シェアする場をつくること」をコンセプトに掲げています。建築家の個性はしばしば形や素材に現れますが、私たちが突き詰めるのは「そこにどんな営みを作り出すか」ということです。
ハードとソフトの双方を捉えながら、それぞれの場に相応しいコンセプトとデザインを提案しています。私たちの事務所では、設計を軸としながら、プロジェクトによっては企画から提案を行い、人の生き方に多様な選択肢を生み出す建築を提案しています。
こうしたスキルを現場で磨き身に付けたい方に、ぜひご応募いただきたいと考えています。現在は、ホテル、山小屋、ビジターセンター、寺院建築、店舗、シェアハウス、コーポラティブハウス等、様々な案件が進行しています。昨年から導入したBIMとVRによる検討は、設計段階での解像度が高まり、大きな手応えを感じているところです。変化を楽しみ、挑戦を続ける私たちと一緒に働いてくれる仲間を募集したいと思います。



中村竜治建築設計事務所が設計した、兵庫・神戸市の「神戸市役所1号館1階市民ロビー改装」です。
また、2021年1月29日に、中村も参加する、こちらの空間をテーマにしたオンライントークセッションが開催されます(詳細は末尾に掲載します)。
神戸市役所の市民ロビーの改装である。待合、打合せ、休憩、喫茶席などの機能をもつ。大きな庁舎のほんの一部の改装ではあるが、意欲的で丁寧なコンペが行われ出来上がった。
ロビーは閉じた部屋ではなくエントランスホールなど他の空間とずるずるとつながっている上、あまり傷んでもいなかったため、建物には手をつけず、機能的にどうしても必要となる家具(椅子と机)の集合によって、輪郭が曖昧な場所をつくるのが良いのではないかと考えた。
水面に漂う木の葉の様に、床から一定の高さに浮いた木製の板が、くっ付いたり離れたりしながら不均質に散らばっているような状態を思い描いた。座板あるいは天板の高さを同じにし椅子と机の区別をなくし、平面形を長方形と楕円形の中間ぐらいの角のない形にし方向性を曖昧にした。茶屋の縁台のように、ベンチのようでもありテーブルのようでもあるこの家具をベンチテーブルと呼ぶことにした。使う人の状況や解釈次第で椅子にも机にもなり、使う人の創造力を掻き立てる。


株式会社ミライズワークスの、オフィス空間設計デザイナー・プロジェクトマネージャー(営業)・施工管理職募集のお知らせです。詳しくは、ジョブボードの当該ページにてご確認ください。アーキテクチャーフォトジョブボードには、その他にも、色々な事務所の求人情報が掲載されています。
新規の求人の投稿はこちらからお気軽にお問い合わせください。
株式会社ミライズワークスが、オフィス空間設計デザイナー・プロジェクトマネージャー(営業)・施工管理を募集!
私達は、企業の“働く場”を提案している会社です。
現在、働き方がどんどん加速していく中で、
『お客様の先のお客様まで見据え、感動を与える空間をデザインし企業の成長を加速させていく』
これが我々のミッションです、我々の特徴はチームで仕事をする意識がとにかく強い!ということ。
現在のコロナ禍においても即テレワークに切り替えました。その中で出た課題も多くありますが、即、議論し改善を繰り替えしより良く働ける場を考える会社です。
弊社のデザイナーは、お客様と関わることが多々あります。
完成したあとには、お客様から食事会を開いていただくことも多くあり、直接感謝の言葉をいただけるのもやりがいです。(このコロナで現在はありませんが^^)募集職種は、
②オフィス空間設計デザイナー(設計)
②プロジェクトマネージャー(営業)
③施工管理(コンストラクション・マネジメント)現在11年目の会社で、まだ14名の会社です。
おかげさまでお客様からの評価も高くいただけており、今後を担う人材を強化しております。
年齢性別など関係ありません。
ポストもがら空きです。自社の働き方も本気で改革しております。


フロリアン・ブッシュ建築設計事務所が設計した、北海道・磯谷郡の住宅「森の中の家」です。
同プロジェクトは約3ヘクタールの手つかずの森から始まった。
この敷地は一辺160メートルのほぼ完璧な正方形で、背の高い松の木が茂っている。敷地周辺の土地が盛り上がっており、近づいても外からの視線は遮られる。唯一のアクセスは、何年も前に敷かれた、一段下がった場所に走る北側の境界線に沿った小さな道だ。 この「小山」を乗り越えると、樹木に囲まれた敷地に入る。緩やかな下り斜面が南に向かって100メートルほど続き、急な坂道に差し掛かる手前で南側境界に突き当たる。中程に、西側境界に向かって拓けた空き地がある。
建物は水平方向に枝分かれする。家の中を歩けば、森の中を散策しているような錯覚に陥る。目前の森から彼方の森へ。森はここで、手に取って触れられる存在であると同時に遠い背景でもある。 枝分かれした先は、切り取られ、開かれている。枝の先に向かって進むにつれ森へと誘い込まれる。壁によって内と外が分けられ、家によって守られているという物理的な安心感とは裏腹に、森に向かって開かれた窓を通して森との関わりが凝縮され、鮮明になる。我々は森の中に座っている。 家の背骨とも言える中心部では、先端部での凝縮された景色に代わり、瞬時に多面的景色を見ることが出来る。様々な森の景色を取り込んだこの家の中では、この森に初めて足を踏み入れた時の体験がいつも存在している。

※このエッセイは、杉山幸一郎個人の見解を記すもので、ピーター・ズントー事務所のオフィシャルブログという位置づけではありません。
ブレゲンツ再考 / 光の霧
以下の写真はクリックで拡大します
ブレゲンツ美術館(1997年竣工)に初めて訪れたのは今から10年も前のこと。
実を言えば当時、ガラスに包まれた外観とそのすべすべとした質感を見て、«なんだか古い»という第一印象を持ちました。
乳白ガラスに包まれた建物。展示空間のガラス天井とテカテカしたその支持金具。それらがどういうわけか、少し古めかしく思えたのです。
僕が初めて訪れた2010年頃には、同じように乳白ないし曇りガラスでファサードを形成している建築が多かったから、見慣れすぎていたからゆえの印象だったのかもしれません。
そんなブレゲンツ美術館へは、僕の住んでいるスイスのクール市から電車で1時間半ほど。また、展示内容がいつも興味をそそられることもあって、それから何度も訪れています。
そうやって建築をある程度の時間スパンを通して何度も経験していくと、自身の建築の捉え方にも変化が起きてきます、そして、はじめに抱いていた印象はどんどん書き換えられていく。つまり過去は現在によって常に上書き更新されながら、新たな発見と認識をしていくことになるのです。
話は少しそれますが、ズントー事務所に送られてくるポートフォリオでは、よく見かける建築タイプがいくつかあります。
そのタイプの一つが、木造軸組で仮設構築物のようなものを作り、Zinc Mine Museumのように機能の入った空間(box)を挿入しているもの、またはWitch Trial Memorialのように一直線の細長い空間を作り上げたものです。
そして、ブレゲンツ美術館に見られるような乳白(ないし曇り)ガラスのファサードで光を吸収、拡散することで室内に柔らかな光を取り込むことを意図したタイプがあります。
いずれのタイプもシンプルでありながら、設計者の意図が建築の形にダイレクトに現れてくるのでインパクトがあり、構法や機能がユニークでわかりやすく、理解しやすいデザインであると言えます。
ただ、ここで単に、これらの建築タイプをズントー建築のオマージュと言って片付けてはいけません。そもそもこうしたタイプは全く新しく創造されたものではない。少しでも歴史を振り返れば、既に存在していたものだと思うのです。
ズントーが日常的に見つけることのできる形式をごく自然に取り出して、洗練させた状態で実現させた結果、ユニークな建築として多くの人のインスピレーションを喚起している、と言えるのではないでしょうか。
ズントー建築は一見、それぞれの国や文化が持つ建築史の延長線上とは少し離れたところに、孤高の島としてあるようにも思われがちです。
しかしよく考えてみれば、(ヨーロッパ)建築の歴史というやや格式ばったものではなく、身の回りに既に存在していた事柄の上に作り上げられている。
それをズントー自身が意図しているか否かにかかわらず、多くの人に共感される«強さ»になっていると僕は捉えています。
今回は、その“わかりやすい”ブレゲンツ美術館の形式を噛み砕いて、僕が今考えるその建築を(設計者であるズントーの意図も含めながら)、いくつかの建築的特徴を拾いながら再考していきたいと思います。



UAoが設計した、栃木の「那須塩原市図書館 みるる+駅前広場」です。施設の公式サイトはこちら。
那須塩原市の地域アイデンティティでもある「森」に足を踏み入れると、私たちは、季節や天気、動植物たちによる僅かな機微といった刻々の変化を感じ、そのうつろいをマルチモーダルに受け止め、心を動かされている。
この図書館では、館内に点在する言葉(アフォリズム)や展示物、活動や人々によって起こる多様なうつろいを緩やかな境界に表出させ、その機微の重なりの中をまるで森の中のように自由に歩き回ることで、共感覚を生み出し、新しい気づきや学びにつながることを意図している。
公共図書館は、単に人が集まるサードプレイスとしての役割を終え、まち全体の発展に寄与することが求められている。この図書館では個々人の気づきや学びが、活力の資源となってまちに還元され、次第にまちに波及し大きな変化を起こし、新たな気づきが持続する。そのような公共図書館を形にした。


創造系不動産の、‟建築と不動産のあいだを追究する”新たなメンバー(建築不動産コンサルタント)募集のお知らせです。詳しくは、ジョブボードの当該ページにてご確認ください。アーキテクチャーフォトジョブボードには、その他にも、色々な事務所の求人情報が掲載されています。
新規の求人の投稿はこちらからお気軽にお問い合わせください。
■創造系不動産とは・・・
創造系不動産は、2011年に設立され、建築の専門性を持ち合わせたメンバーで構成された新しいタイプの不動産コンサルティング会社です。創業時より建築家やデザイナーとタッグを組み、個人住宅・集合住宅・オフィス・商業施設等の建築不動産コンサルティング及び不動産仲介業務を行っています。創業より10年目になり、メンバーも14名に拡大し、本当に多くの建築家・デザイナーの方とコラボレーションさせて頂いてきました。これからは従来の物件探しや仲介、コンサル業務の専門性をさらに研ぎ澄ましていくと共に、新しい取り組みや事業にも積極的にチャレンジし、さらなる価値を提供できる会社に飛躍していくフェーズになると考えています。と言うのも、近くようで遠い建築業界と不動産業界を取り巻く環境にはまだまだ解決すべき課題が山積しています。
・住宅供給過多、人口減少による空家、価値観の多様化。
・建築家住宅が持つ中古としての市場での価値、良いバトンパス。
※『建築家住宅手帖』という不動産サイトを立ち上げました(2020年9月)
・相互の業界を取り持つ人材の不足。
・建築業界のお金や不動産、ビジネスへの意識。
・不動産業界の当たり前や固定観念、建築業界への理解。
・空家など築古物件に対しての住宅ローン、リノベーション費用の調達。
・外国人留学生や建築事務所所員の方の賃貸探しの困難さ。
etc不動産の世界に飛び込んで建築業界との懸け橋になり変革を起こしたい方、お金や不動産、ビジネスの知識・スキルを身に着けたい方、自分自身で建築業界に問題意識をお持ちで、なんとかしたいと考えている方、様々なキャリアで建築出身のメンバーと一緒に新しい「あいだ」の開拓に挑戦していく方を募集いたします。
不動産の知識ではなく、建築への情熱があれば大歓迎です!また昨年、千葉県の外房に位置するいすみ市に、初の支店「創造系いすみ」を設立しました。これから日本の地方経済の現実に正面から向き合い、地方創生の研究と実践を行うための拠点です。そうした地方での研修も行います。
さらに、創造系不動産では、定期的に社外の専門家(社会保険労務士など)からアドバイスを受け、コンプライアンスを遵守した働きやすい社内作りに取り組んでいます。正社員、パートタイムなど、その方に合わせた多様な働き方を実現できる環境です。是非ご応募いただき、お話しをお聞きできればと思います。
■参考書籍・連載
『建築と不動産のあいだ』(学芸出版社)
『建築と経営のあいだ』(学芸出版社)
『建築学科のための不動産学基礎』(学芸出版社)■創造系不動産で身につくスキル
建築の領域を越え、不動産・ファイナンス・プロジェクトマネジメント・営業戦略・企業経営理論を身につけることができます。
チーム制を導入しており、チームリーダーを経験するチャンスもあり、リアルな経営を知ることができます。
また、Off-JTとして、宅地建物取引士・ファイナンシャルプランナーの資格取得支援、ビジネススクールでの経営研修を実施しており、業務に関する知識を体系的に学ぶことが可能です。



川本達也建築設計事務所が設計した、愛知・一宮市の住宅「今伊勢の家」です。
「高い耐震性」と「開放的な空間」の両方を求められた場合、通常、2階の方が1階よりも構造上必要な壁量が少なくなるため2階にLDKをもっていく方が理にかなっている。
ここでは、前面道路が個人の所有物である私道(生活道路)という周辺環境を取り込み、内外がシームレスに連続する空間を計画することで与えられた条件の中で最大限の空間的ボリュームの獲得を目指す。幅8mの「門型フレーム」が並ぶだけの単純明快な構成とすることでバランスの良い耐震性能と大きな開口部を両立させた。
計画地は古くから繊維工場が多く栄えた工業地域に属し、近年の開発により宅地化され住宅が多く建ち並び、地域産業と住宅が共存して居住環境がつくられている。
敷地の前面道路はその宅地化するにあたってつくられた私道であり、この道に接する数件の家で共有する行き止まりの「生活道路」である。この辺一帯は主要な道路から枝分かれのように伸びるこの「生活道路」が張り巡らされ、それぞれ固有のコミュニティが形成されていた。この道路ごとに異なる独自の場所性をそのまま住空間に取り込むことで、地域産業の副産物的にできたコミュニティを住宅地としての新たな風土として地域づくりに寄与することができないかと考えた。



齋藤和哉建築設計事務所が設計した、埼玉・さいたま市の住宅「浦和のハウス」です。
1本の線で距離感をコントロールできるのが建築である。若い夫婦と3人の子供が生活する上で、周りから覗かれずに自然や家族の気配をどこにいても感じることができる住まいをローコストでつくりたいというのが施主の要望だった。それを実現するために最小限の床と壁で建築的に成立する住空間を模索した。
敷地を取り巻くさまざまな目線は切りつつも、家族同士の雰囲気を感じながら、周囲の空や緑を光と風とともに室内へ取り込むことができるよう、床と壁の高さを設定すると立体的な一室空間となった。
1階に南から天井の高い通り土間、リビング・ダイニング、階段、水まわりの順で部屋を配置し、それぞれのあいだに高さの違う5枚の構造壁を立てた。加えて東と西に駐車スペースを取ることで4周にバッファ空間がある構成とした。2階に屋根裏のような寝室を設け、吹き抜けで土間とつなげた。1階と2階の途中には視線と光と風が一気に抜けるロフト層がある。


ザハ・ハディド・アーキテクツがコンペで勝利した、中国・深センの高層タワー「Tower C at Shenzhen Bay Super Headquarters Base」です。低層部が公園と一体化し市民にパブリックスペースを提供する設計が特徴的です。
以下はプロジェクト概要の要約。
ザハ・ハディッド・アーキテクツは「深センベイ・スーパー・ヘッドクォーター・ベースのCタワー(Tower C at Shenzhen Bay Super Headquarters Base)」建設の設計コンペの優勝者として発表されました。
深圳ベイ・スーパー・ヘッドクォーター・ベースは、広東省、香港、マカオのグレーター・ベイエリアにサービスを提供する深センの重要なビジネス・金融センターとなり、毎日30万人の従業員を収容するグローバル・テクノロジー・ハブの中に企業本社のクラスターを統合します。
ザハ・ハディッド・アーキテクツによる「タワーC」は、市内の南北に計画されている緑の軸線と深センの東西の都市回廊が交差する場所に位置し、そこに対応するようにデザインされています。隣接する公園や広場と直接接続し、2つのタワー内で上向きに伸びる広く段々になったランドスケープに変化します。そして、文化やレジャーのアトラクションがタワーをつなぎ、建物の中心部にあるブリッジ部では、市民にパノラマビューを提供します。
ザハ・ハディッド・アーキテクツが開発した3Dモデリングツールにより、C棟のデザインは、建築物の質量、向き、ファサードと床の比率の効率を最適化されています。この建築は、約400mの高さにある2つのタワーからなる多次元の垂直都市で、柱のない自然光のオフィススペース、ショッピング、エンターテイメント、ダイニング設備、ホテル、コンベンションセンター、展示ギャラリーを備えた文化施設を提供します。
メールマガジンでも最新の更新情報を配信中