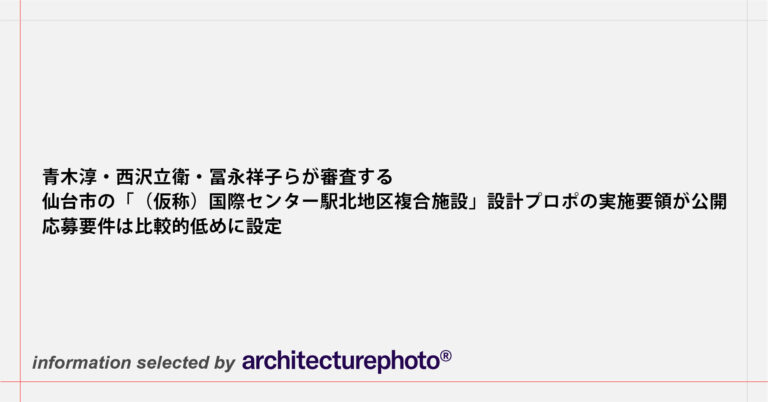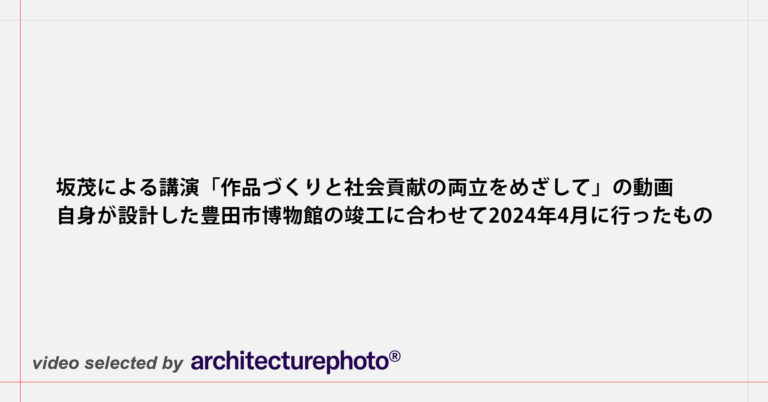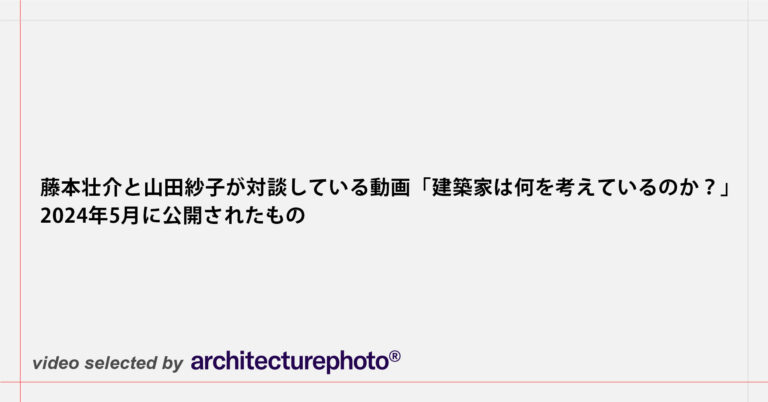MVRDVによる、オランダの「NIO・ハウス・アムステルダム」。リートフェルトの増築も施された19世紀築の建物を転用する計画。地域に貢献する“自動車ショールーム”として、上階に様々なパブリック機能を内包。施主企業のスローガンを参照して各階の色を段階的に変化させる 外観、夜景 photo©Ossip van Duivenbode MVRDVによる、オランダの「NIO・ハウス・アムステルダム」。リートフェルトの増築も施された19世紀築の建物を転用する計画。地域に貢献する“自動車ショールーム”として、上階に様々なパブリック機能を内包。施主企業のスローガンを参照して各階の色を段階的に変化させる 1階、ショールーム photo©Ossip van Duivenbode MVRDVによる、オランダの「NIO・ハウス・アムステルダム」。リートフェルトの増築も施された19世紀築の建物を転用する計画。地域に貢献する“自動車ショールーム”として、上階に様々なパブリック機能を内包。施主企業のスローガンを参照して各階の色を段階的に変化させる 4階、コワーキングスペース photo©Ossip van Duivenbode MVRDVによる、オランダの「NIO・ハウス・アムステルダム」。リートフェルトの増築も施された19世紀築の建物を転用する計画。地域に貢献する“自動車ショールーム”として、上階に様々なパブリック機能を内包。施主企業のスローガンを参照して各階の色を段階的に変化させる 7階、イベントスペース(リートフェルトルーフトップ) photo©Ossip van Duivenbode MVRDV が設計した、オランダの「NIO・ハウス・アムステルダム」です。
こちらはリリーステキストの翻訳です
MVRDVが、NIOの新しいヨーロッパ旗艦店のために、19世紀に建てられた指定建造物とヘリット・リートフェルトの屋上パヴィリオンをリスペクトしながら変容させる
電気自動車メーカーのNIOは、19世紀後半に建てられたアムステルダムのカイザースグラハトにある7階建てのビルに、ヨーロッパにおける旗艦店をオープンしました。新しいNIO・ハウス・アムステルダムは、MVRDVによるインテリア・デザインで建物を改装し、NIOのブランドを反映したデザイン要素と、歴史的建造物を尊重した扱いを組み合わせています。NIOのスローガンである「青い空がやってくる」にインスパイアされ、低層階のアースカラーから、モダニズムの屋上パヴィリオンを満たすエアリーなブルーまで、建物の各フロアはカラーグラデーションを形成しています。
この建物には語り継がれる歴史があります。ヤン・ファン・ロイの設計で、1891年にニューヨーク生命保険会社のために建てられた当時は、アムステルダムで最も高い民間ビルのひとつでした。20世紀の大半は、メッツ・アンド・カンパニー・デパートの本拠地であり、1933年には、モダニズム運動で最も重要なオランダ人建築家であるヘリット・リートフェルトの設計による鉄骨とガラスの屋上パヴィリオンが増築されました。この遺産にもかかわらず、2013年にアバクロンビー&フィッチの店舗が入ることになり、その結果、リートフェルト・パヴィリオンを含む上層階は一般公開されなくなり、オリジナルの内部ディテールの多くが覆い隠されました。
世界中のNIOハウスがそうであるのと同じように、NIOハウスの登場によって、その建物は単なる「自動車ショールーム」ではなく、それを受け入れる近隣地域に貢献するさまざまな機能を備えた公共建築物となるのです。1階のカー・ショーケースの上には、柔らかな黄色のキッズ・コーナーを含むカフェがある。次に3階にはフォーラムがあり、地元企業やイベント団体がワークショップやプレゼンテーション、小規模な講演会などに利用できるほか、子どもたちが楽しめる「ジョイ・キャンプ」も併設されています。4階には一般の人も予約して利用できるコワーキングスペースがあり、5階にはアートとデザインのギャラリーがある。このギャラリーはNIOの製品を展示したり、地元のアーティストが作品を発表する場としても利用できます。最後に、NIOのオフィス用に確保された6階の上には、7階のイベントスペースと屋上パヴィリオンがあります。
MVRDVのデザインにおいて、歴史的なディテールが再び明らかになった階段は、デザインの中心的な要素となり、各階の主要スペースから常に見えるようになっており、訪問者の方向を知るのに役立っています。プロジェクトを通して、明るく風通しの良い環境を作るため、空間は可能な限り開放され、内壁を取り除き、天井を高くし、1階とカフェをつなぐアトリウムのような縦のつながりを強調しています。
MVRDVの創立パートナー、ヤコブ・ファン・ライスは言います。