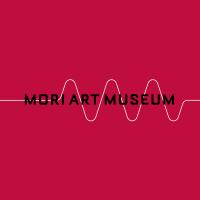ヘザウィック・スタジオの展覧会が日本で開催されます。会場は「六本木ヒルズ展望台 東京シティビュー・スカイギャラリー(六本木ヒルズ森タワー52階)」、会期は2020年4月8日~6月14日。「#トーマス・ヘザウィック」から過去の紹介記事を閲覧できます。建設が進められているGoogle新本社の設計でも知られています(BIGと共同)。
デジタルテクノロジーが発展し、日常生活に浸透するにつれて、周囲の環境や他者との関わり方も劇的に変化してきました。このような時代、私たちの感情を他者と繋げる共感を公共空間にもたらすことは可能なのでしょうか?
トーマス・へザウィック(1970年、英国生まれ)率いるヘザウィック・スタジオ(1994年創設)は、ロンドンを拠点に世界各地で革新的なプロジェクトを手掛けるデザイン集団です。ものや場所の歴史を理解し、多様な素材を研究し、伝統的なものづくりの技術に敬意を表しながら、最新のエンジニアリングを駆使する。そのなかで自然環境と対話し、大きな空間もヒューマンスケールに還元しながら、目の覚めるようなアイディアを実現してきました。
本展では、同スタジオの主要プロジェクトを、「ひとつになる」、「みんなとつながる」、「彫刻を体感する」、「都市空間で自然を感じる」、「古い建物を未来へつなげる」、「遊ぶ、使う」という6つの観点から掘り下げます。人間の心を動かす優しさ、美しさ、知的な興奮、そして共感をもたらす建築とは何か? へザウィック・スタジオの取り組みからこの問いを探ります。