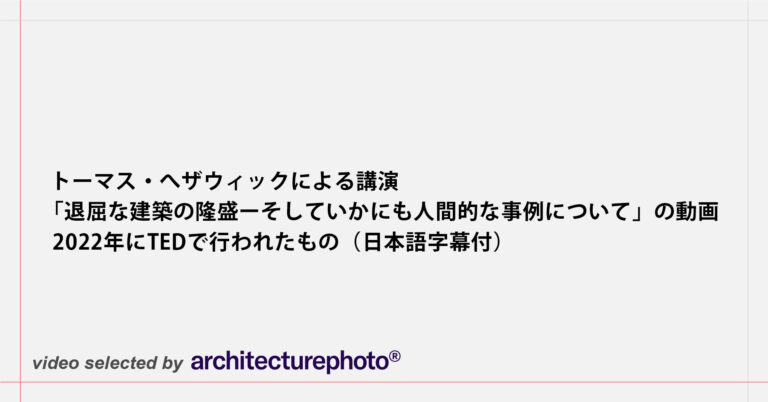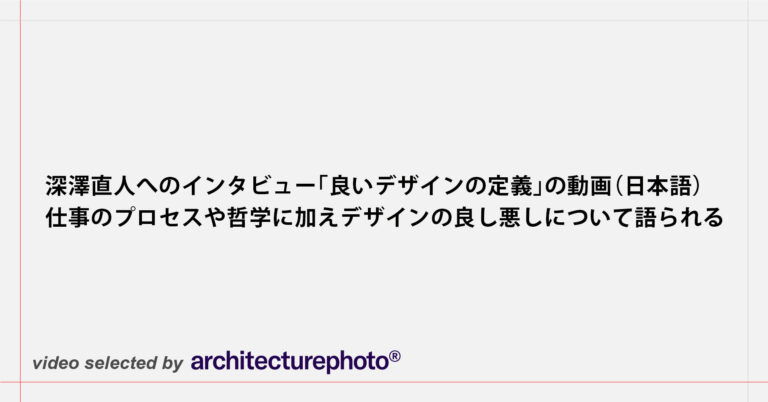家具・プロダクト・建築部材が集まる見本市「インテリア ライフスタイル 2023」が、東京ビッグサイトで開催されます。見本市の中では、芦沢啓治・トラフらが参加する展示「Upcycling Airplanes」やトークイベントも多数開催されます。開催期間は、2023年6月14日(水)~16日(金)。参加費無料(要事前申し込み)。来場事前登録はこちらから。【ap・ad】
これからのライフスタイルマーケットを提案するインテリア・デザインのための国際見本市として1991年から開催する本見本市では、多様化する衣・食・住のデザインアイテムを求めて、毎年多くの来場者が訪れます。2022年の開催では12カ国・地域から16,542名の来場者が515社の出展製品を前に、熱心に商談を交わす姿で賑わいました。
「Upcycling Airplanes JAL | Karimoku」展(見本市内で展示)

空を飛ぶ役割を終えた航空機の部品を、7人のデザイナーが次の形に作り変えていくプロジェクト。
JALとカリモクのコラボレーション
航空機部品のアップサイクル商品を企画するにあたり、日本を代表する航空会社として、安全・安心な航空機の品質をつくりこむJALの整備士の姿勢と、同じく日本を代表する木製家具メーカーとして、長く安全に使える高品質な商品を製作するというカリモクの物作りの姿勢に親和性を見出し、今回のコラボレーションが実現。また、カリモクとタッグを組むことで、インテリアになじみつつ機能的な製品として航空機部品に新たな命を与え、航空ファンだけでなく、より多くの人にアップサイクル品としての価値を提供出来ることを期待する。
航空機リサイクルの概要
- JALは、保有していたボーイング777型機を国内で初めてリサイクルした。
- 通常、退役した航空機は国外へ輸送され、航空機として再活用、解体・リサイクルが行われるが、国内で航空機リサイクルを実施することで国外へ飛行する必要がなく、燃油削減と排出ガス抑制の観点からSDGsに貢献することができる。
- 航空機リサイクルにおいては、航空機部品として他の同型機材で再利用されるほか、金属などを素材ごとに再資源化、また新たな用途/製品としてアップサイクル品に加工される。
参加建築家・デザイナー
アップサイクルで新たな価値をプロダクトに反映し、広く人々へ伝えていくことが期待できる建築家やデザイナーを選定芦沢啓治建築設計事務所 芦沢啓治 / JIN KURAMOTO STUDIO 倉本仁 / Shizuka Tatsuno Studio 辰野しずか / MUTE イトウケンジ / inter.office / kumano 熊野亘 / トラフ建築設計事務所 鈴野浩一