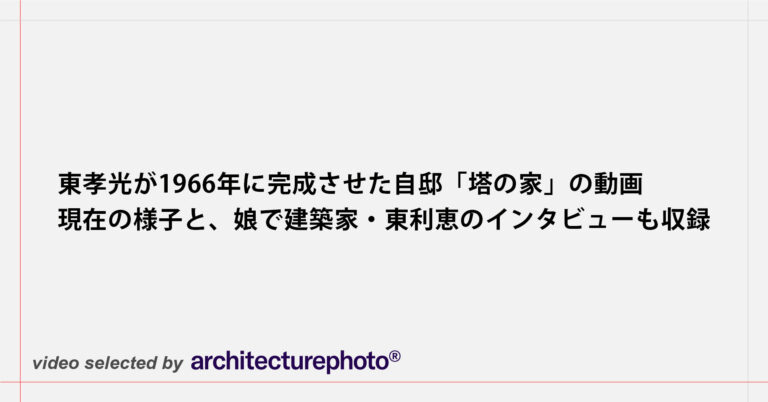伊礼智が建築設計の考えを語っているインタビューと、実際の住宅作品の様子が収録された高クオリティの動画です。
news archive
隈研吾が2000年に完成させた「那珂川町馬頭広重美術館」の様子と、隈のインタビューを収録した高クオリティな動画です。中国のメディア一条が制作しyoutubeに2016年11月に公開したものです。隈の公式サイトでは竣工写真やコンセプトテキストも閲覧可能です。
手塚貴晴+手塚由比 / 手塚建築研究所が2013年に完成させた「茅ヶ崎シオン・キリスト教会/聖鳩幼稚園」の使用されている様子と手塚由比のインタビューを収録した動画です。中国の一条が制作して2017年11月にyoutubeに公開されたものです。


アーキテクチャーフォトジョブボードに新しい情報が追加されました
ASEI建築設計事務所の、設計スタッフ・アルバイト募集のお知らせです。詳しくは、ジョブボードの当該ページにてご確認ください。アーキテクチャーフォトジョブボードには、その他にも、色々な事務所の求人情報が掲載されています。
新規の求人の投稿はこちらからお気軽にお問い合わせください。
ASEI建築設計事務所では、設計スタッフ・アルバイトを募集しています。
代表の鈴木亜生は、乾久美子建築設計事務所を経て、中村拓志&NAP建築設計事務所にて設計室長を務めた経歴を持ちます。現在は「クリエイティブ・リソース」をテーマに資源循環の仕組みをつくる活動を続けています。様々な地域で未利用な資源の価値を見出し、地域の技術を活用した材料を製造して、新たな構法・構造へと再編した環境建築を目指しています。
(参照:第4回これからの建築士賞受賞 / https://tokyokenchikushikai.or.jp/award/pdf/korekara-vol.4.pdf )
現在、住宅・オフィスビル・工場・マンションなどのプロジェクトが進行中です。プロジェクトの設計から工事監理まで担当できるスタッフを募集します。自主性と責任を持って仕事に取り組んでくれる方を求めます。


アーキテクチャーフォトジョブボードに新しい情報が追加されました
レベルアーキテクツの、業務拡張のため設計スタッフ募集のお知らせです。詳しくは、ジョブボードの当該ページにてご確認ください。アーキテクチャーフォトジョブボードには、その他にも、色々な事務所の求人情報が掲載されています。
新規の求人の投稿はこちらからお気軽にお問い合わせください。
レベルアーキテクツは業務拡張のため、設計スタッフを募集しています。
伊東豊雄が2015年に完成させた「みんなの森 ぎふメディアコスモス」の様子と、伊東のインタビューを収録した高クオリティの動画です。
MVRDVが2017年に完成させた、中国・天津の、曲面の書庫が特徴的な図書館の高クオリティの動画です。写真はこちらで閲覧可能です。
東孝光が1966年に完成させた自邸「塔の家」の現在の様子と、娘で建築家・東利恵のインタビューも収録した高クオリティの動画です。製作は中国のメディア「一条」です。2018年9月5日に公開されyoutubeで約40万回再生されています。


arbolが設計した、兵庫・宝塚市の住宅「宝塚の家」です。
兵庫県宝塚市の山手の住宅街にあり、なだらかな坂の中腹に立地する住宅。
建主は、子供たちと自然との接点を大切にしのびのびと育ってほしいという気持ちがあり、休日の過ごし方は、
家族で街に出かけるよりも公園でのピクニックやキャンプに繰り出されることを好まれることから、
住宅についても大らかで伸びやか、コンパクトながらも開放感のある豊かな暮らしを求められた。
そこで、暮らしの中で自然の美しさ等の感性を育んでいけるようにと思いを込めて計画した。敷地は3面が道路に面している。敷地をめいいっぱい活用し、建物は平屋としている。
建物形状については、なだらかに上昇する丘の稜線に沿って屋根を設け、屋根は片流れとしたが、
外周は建物から外壁にかけて一筆書きになめらかにすることで、合理的な構造で且つ造形的な建物を目指した。

柿木佑介+廣岡周平 / PERSIMMON HILLS architectsによる、神奈川・横浜の、保育施設が入居するフロアの共用部のアップデート「アメリカ山のこどもの回廊」です。
元町・中華街駅に直結するアメリカ山公園という立体都市公園の中にある、学童保育施設と保育園が入るフロアの共用部のアップデートの提案です。
学童保育施設は以前にPERSIMMON HILLS architectsで設計したアメリカ山ガーデンベースです。https://architecturephoto.net/69934/このフロアの共用部には腰掛けたりできる段差や、手すりで囲われたデッドスペース、避難経路に当たらないポシェがあり、法規的にも「用途のない場所」が数多くあります。
そこにベビーカー置き場や、遊具のようなベンチ、紙芝居のようなフロアサイン、展示ギャラリーといった家具をインストールすることで、こどもに関するフロアとしてのキャラクターを際立たせます。
一見ビルの共用部にも見えるのですが、横浜市所有の公園空間なので、休日に元町やアメリカ山にベビーカーで来た家族の預かり場所になったり、お迎えのちょっとした合間に子供たちがベンチでままごとを始めたりといった、公共空間としての新しい使われ方が生まれています。
(※アメリカ山についてはこちらの公式ページを参照ください)
サミープ・パドラが設計した、インド・コパルガウンの、レンガ造のシェル構造で作られた登れる屋根が特徴的な図書館の写真が27枚、archdailyに掲載されています。
ヘルツォーク&ド・ムーロンが計画している、ベルリンのミース・ファン・デル・ローエ設計の新ナショナルギャラリー横に建つ新美術館の最新画像が9枚、archdailyに掲載されています。
コンペでヘルツォークの勝利が発表されたのは2016年10月でした。
御手洗龍建築設計事務所が最優秀者に選ばれた、埼玉の「(仮称)松原児童センター建設及びテニスコート整備」設計プロポの提案書が公開されています。次点者はEurekaで、こちらの提案書もPDFで公開されています。


アーキテクチャーフォトジョブボードに新しい情報が追加されました
SEA Designの、設計スタッフ(正社員)募集のお知らせです。詳しくは、ジョブボードの当該ページにてご確認ください。アーキテクチャーフォトジョブボードには、その他にも、色々な事務所の求人情報が掲載されています。
新規の求人の投稿はこちらからお気軽にお問い合わせください。
SEA Designでは設計スタッフ(正社員)を募集しています。
現在、住宅、別荘、共同住宅、ホテル、商業施設、リノベーションなど様々なプロジェクトが進行しています。弊社は特別なものを自ら開発、発信し提供することを企業理念として、
設計デザイン業務の枠に止まらず、不動産を絡めた建物用途からの企画提案や、自社での建築開発、設計施工によるより精度の高い仕事の実現を目指し、工事部、不動産部も設立しました。設計事務所の枠を超えたプロジェクトにも力を入れています。お施主様との打合せから、企画、提案、監理まで一貫して担当していただきますので、幅広いスキルを磨くことが可能です。
これまでの経験を活かしながら、同時に自身のキャリアに磨きをかけ、共に新しい設計事務所のスタイルを創り上げていければと思います。

SHARE sinato大野力・ondesign西田司らが出展する、湘南モノレールの車内と駅構内を会場にした建築展「7人の若手建築家によるサーファーの家展」が開催
- 日程
- 2018年11月17日(土)–11月23日(金)

sinato大野力・ondesign西田司らが出展する、湘南モノレールの車内と駅構内を会場にした建築展「7人の若手建築家によるサーファーの家展」が開催されます。会期は2018年11月17日~23日。
参加建築家
大野 力(sinato)
西田 司(オンデザイン)
川添 善行(空間構想一級建築士事務所)
海法 圭(海法圭建築設計事務所)
髙濱 史子(髙濱史子建築設計事務所)
田辺 雄之(田辺雄之建築設計事務所)
伊藤 立平(伊藤立平建築設計事務所)
『7人の若手建築家によるサーファーの家展』
7人の個性的な若手建築家が鎌倉、藤沢エリアを対象に、サーファーのための木造住宅を提案いたします。
会場は大船と江の島を結ぶ湘南モノレールの車内と大船駅構内。
鉄道空間を会場にするというこれまでにない展覧会です。
世界でも珍しい懸垂式のモノレールに揺られながらご覧ください。
建築出身のブランディングデザイナーで、エイトブランディングデザインを主宰する西澤明洋へのインタビュー「デザイナーの本質を追う男。」がFINEDESに掲載されています。