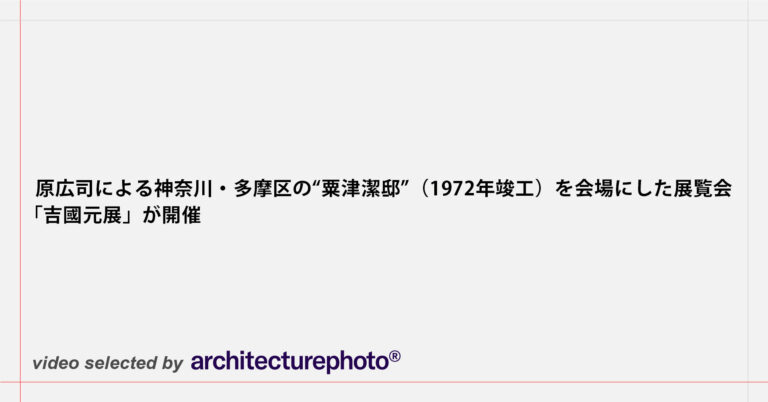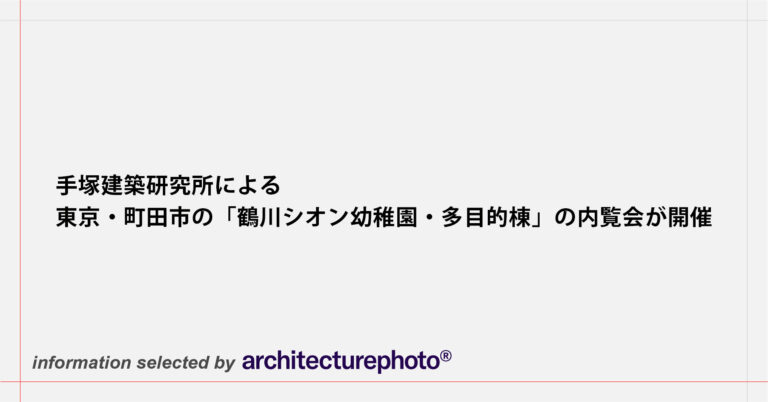五十嵐敏恭と佐藤研吾による建築展「グルグル広がって上がっていく」の会場写真です。
建築と生き方の“表裏一体”を体現する二人の建築家の展覧会です。対話の中で見い出された“言葉”をキーに“思考モデル”とも言える作品を制作して展示しています。本展は、畝森泰行と金野千恵の事務所でもある東京台東区の“BASE”を会場に開催されます。会期は、2023年10月1日まで。展覧会の公式ページはこちらです。また、2023年9月23日・30日・10月1日に現地やオンラインで行われる関連イベントも企画されています(詳細は末尾に掲載)。
2組の建築家 五十嵐敏恭-Studio Cochi Architects と 佐藤研吾-Korogaro Association による展覧会「グルグル広がって上がっていく」を開催する運びとなりました。
2組の建築家がそれぞれの拠点作りの構想を機軸に対話し、共有し得るいくつかの言葉を見つけ、新たな建築やモノのかたちの試行錯誤を展示します。言葉による対話、作ったモノによる対話、あるいは両者をつなげる構想自体が並置されることによって、これからの建築、生きていく世界を思考していきます。
五十嵐敏恭によるステートメント
グルグル広げた対話の中から、お互いのモノづくりと今後の活動につながるかもしれない言葉たちを拾い、その言葉たちを共通のキーワードとしてお互い新しくモノを制作することを試みた。キーワードはお互いに共有できる言葉だが、ひとりでは発見できなかった言葉でもある。自分たちが立っているところから、お互いに少しだけ離れたところからの視点を織り交ぜることで生まれたモノを、対話の成果物として展示したいと思う。
佐藤研吾によるステートメント
両者の異なる思考モデルが提示されることは、興行上とても有効だとは思うが、展示している当事者からすれば「おい、お前はどう生きるんだ」というヒリヒリと迫ってくる大きな問いに焦燥する最中でもあるので気が気でない。だがしかし、フラフラが次第にグルグルと、移動と行動の残像がボンヤリとした軌跡として見えてくるようになれば、自分はもう少し上に行ける気がするのだ。なのでひとまずは建築をつづけていこうと思う。