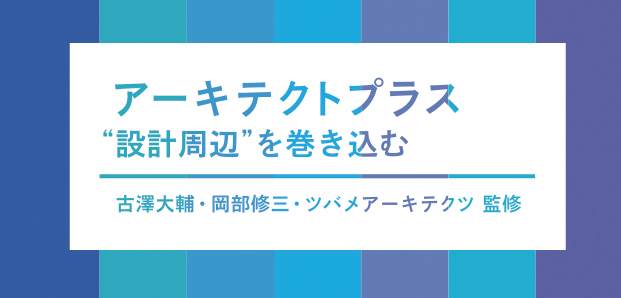【ap job更新】 坂東幸輔と須磨一清が主宰する「A Nomad Sub」が設計スタッフ・プロジェクトマネージャーを募集中 【ap job更新】 坂東幸輔と須磨一清が主宰する「A Nomad Sub」が設計スタッフ・プロジェクトマネージャーを募集中 えんがわオフィス・蔵/事務所/徳島県/2013 アーキテクチャーフォトジョブボードに新しい情報が追加されました
坂東幸輔と須磨一清が主宰する「A Nomad Sub」 の、設計スタッフ・プロジェクトマネージャー募集のお知らせです。詳しくは、ジョブボードの当該ページ にてご確認ください。アーキテクチャーフォトジョブボード には、その他にも、色々な事務所の求人情報が掲載されています。新規の求人の投稿はこちらからお気軽にお問い合わせください 。
坂東幸輔と須磨一清が主宰する建築設計事務所「A Nomad Sub(アノマドサブ)」では設計スタッフ・プロジェクトマネージャーを募集しています(経験者・新卒・第二新卒)。事務所の仕事や雰囲気を知りたい方には説明会も随時開催可能です、お気軽にご相談ください。
■A Nomad Sub(アノマドサブ)について
2人は2010年から徳島県神山町で建築ユニットBUS(元・バスアーキテクツ)のメンバーとして、空き家再生やまちづくりの活動を行ってきました。「ブルーベアオフィス神山」(新建築2012年4月号)、「えんがわオフィス」(新建築2013年7月号)、「KOYA」「WEEK神山」(新建築2015年11月号)などの設計を通して、それらが神山町のサテライトオフィスを生み出すことに繋がり、まちづくりに多大に貢献したことで、BUSは2016年のヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展日本館展示の出展作家の一組に選ばれ、審査員特別表彰を受けました。
それぞれ個人の建築家として国内外の様々な場所で建築設計やまちづくり、建築教育の活動を行ってきましたが、活動範囲を拡大するため、坂東幸輔建築設計事務所とSUMAを合併し2018年1月にA Nomad Subを設立しました。
これまで手がけてきた古民家リノベーションに加え、東京都内の新築住宅から、広島県神石高原町での日本初の全寮制インターナショナル小学校、八丈島での宿泊機能付きのサテライトオフィスなど様々な分野・規模のプロジェクトが進行中です。
■ご応募お待ちしております