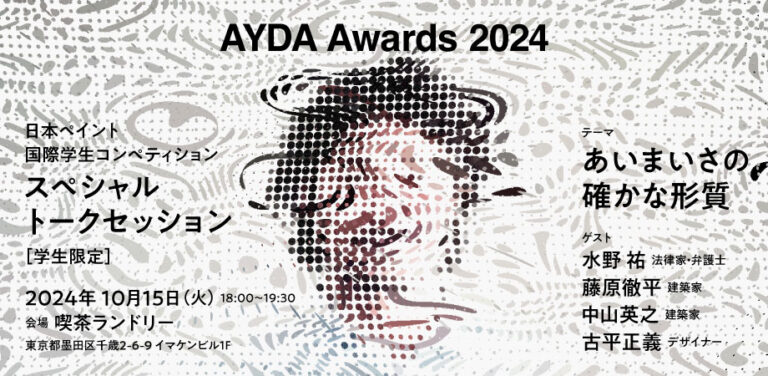BIGによる、デンマークの「ペーパーアートミュージアム」。元スーパーマーケットをペーパーアートの美術館に転用する計画。伝統を未来に引継ぐ存在として、“一枚の紙”の様な屋根で既存建物を覆う構成を考案。既存壁面には“折紙”を参照した音響調整機能層が付加される image courtesy of BIG BIGによる、デンマークの「ペーパーアートミュージアム」。元スーパーマーケットをペーパーアートの美術館に転用する計画。伝統を未来に引継ぐ存在として、“一枚の紙”の様な屋根で既存建物を覆う構成を考案。既存壁面には“折紙”を参照した音響調整機能層が付加される ワークショップスペース image courtesy of BIG BIG が設計している、デンマークの「ペーパーアートミュージアム」です。
こちらはリリーステキストの翻訳です
BIGがデンマークの元スーパーマーケットの建物をペーパーアートの新しい美術館へと変貌させる
BIG-ビャルケ・インゲルス・グループは、デンマーク北ユトランド地方にある元スーパーマーケットの建物を、新しいペーパーアートの美術館に変える予定です。デンマークの文化遺産に深く根付いたペーパーアート、例えばル・クリントによるアイコニックな折り紙ランプシェードやH.C.アンデルセンの紙クリップなどがありますが、この建物の転用と増築により、美術館の年間来館者数を倍増させるとともに、アートの一形態として、また専門技術として紙を取り入れていくことを目指しています。
2018年に切り絵作家のビト・ヴェイレによって創設されたペーパーアートミュージアムは、北欧唯一の紙工芸とデザインの専門美術館です。約900㎡の元スーパーマーケットの建物は、BIGによって改装と増築が施され、ワークショップ、イベント、教室、倉庫、オフィス施設を備えた2300㎡の美術館に生まれ変わります。アダプティブ・リユース・プロジェクトでは、DGNBのゴールドまたはプラチナ認証の取得を目指しています。
「ペーパーアートはデンマークの文化遺産に深く根付いており、ル・クリントの折りたたみ式ランプやアンデルセンの紙クリップといった象徴的なデザインを通じて、デンマークのペーパーアートの伝統が紹介されています。この遺産を未来に引き継いでいくことが、この美術館の中心的な使命です。私たちは既存の建物を再利用したことも誇りに思っています」─ カレン・ビット・ヴェイレ、ペーパーアートミュージアムのアーティスト兼ディレクター
「ペーパーアートミュージアムは、新しい軽量屋根構造として構想されています。一枚の紙のように既存の建物に屋根が載り、その周囲に新しい機能のためのスペースが生まれます。つまり、新しいものと古いものを一つの屋根の下に統合するのです。既存の建物の外壁には、折り紙にインスパイアされ、複数の紙アーティストとのコラボレーションでデザインされた新しい音響調整機能を持つ紙のアート層が施されます。
「ペーパーアートとは、単色の二次元素材である一枚の紙から、三次元の形や複雑なイメージを作り出すことです。屋根の表面を折り紙の1枚の紙のように扱うことで、既存の機能と新しい機能が1つの統一されたジェスチャーにまとめられます。明確さによって表現力が強調され、シンプルさから複雑さが生まれます。そして、老朽化したスーパーマーケットは、浮遊する湾曲した屋根の下で新たな命を得るのです」─ ビャルケ・インゲルス、BIG-ビャルケ・インゲルス・グループ創設者兼クリエイティブ・ディレクター