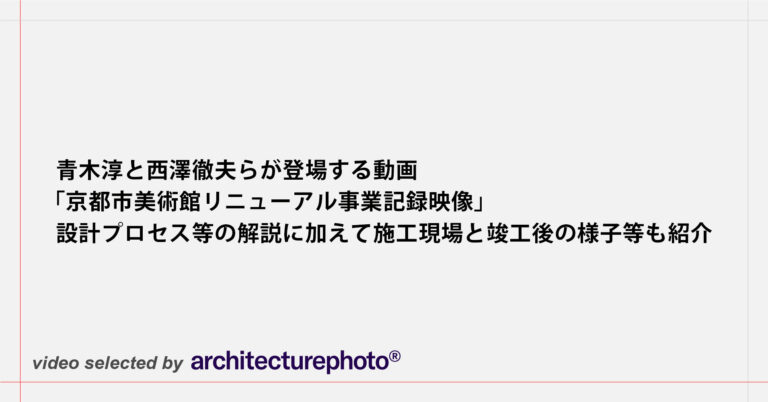武田幸司 / Ginga architectsが設計した、山形市の「空と軒下の間 / 山形の住宅」です。
積雪と猛暑が特徴の地域での計画です。建築家は、除雪と日差しへの対応を意図し、諸室を持上げて地上階を駐車や遊びの為の“半外部空間”とする構成を考案しました。また、上階は中央に吹抜を設けて“空への意識を高める”一室空間として作られました。
山形市中心部の密集地に立つ、軒下空間と空いた中庭から、ぽっかりと切り取られた空が見える、平家のボリュームが軽やかに浮かんで見えるような住宅である。
敷地は、山形城址北東部、2、3階建ての建物や貸駐車場に隣接する山形市の中では街中の建物が混在する密集敷地である。
眺望が望める環境とはなかなか言い難い。奥に両親が住む母屋があり、手前を貸し駐車場としていた場所へ、住宅を増築する計画である。家族分の駐車場としての台数を確保すること(山形では家族一人一台が基本である)、奥の母屋へのアプローチを確保すること、街中でありながらも抜けのある開放的で魅力的なリビングなどを求められた。
私も出身は山形であり、気候条件は肌身をもって重々承知である。冬は雪が多く降り寒く、夏は盆地特有の厳しい暑さになる過酷な気候条件の山形という土地柄のことも考慮し、1階はできるだけガランとしたピロティ形式とし、それ以外の居住空間を2階に持ち上げる建ち方とした。そうすることで、母屋へのアプローチを確保し、家族分の駐車場を確保している。
1階は玄関と寝室空間を最小限に設け、それらのボリュームを柱脚に見立て、ほとんどがピロティになっている。除雪をしなくてよい駐車場空間であったり、暑い日差しから守られた風の抜ける軒下空間は、子供の遊び場やBBQスペースなど第2のリビングと呼べるような豊かな半外部空間が街に開かれている。
2階ボリュームは、真ん中にぽっかりと余白となる中庭吹き抜けを持つロの字型の形状になっている。外周の開口部を極力絞り高さを低く抑え、真ん中の中庭に高さをだすことで、空への意識を高めるワンルームの空間にしている。