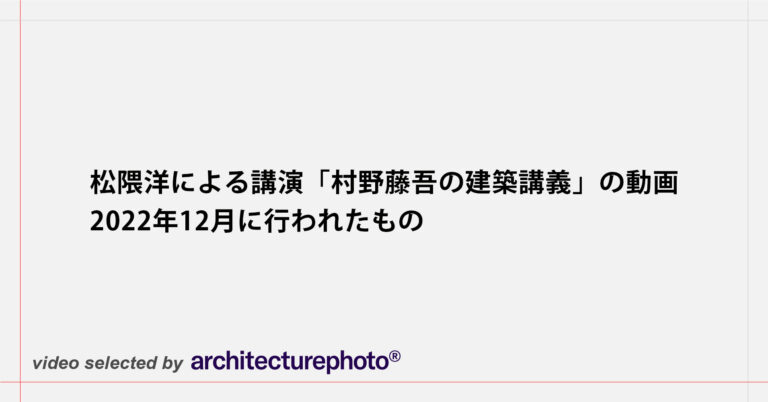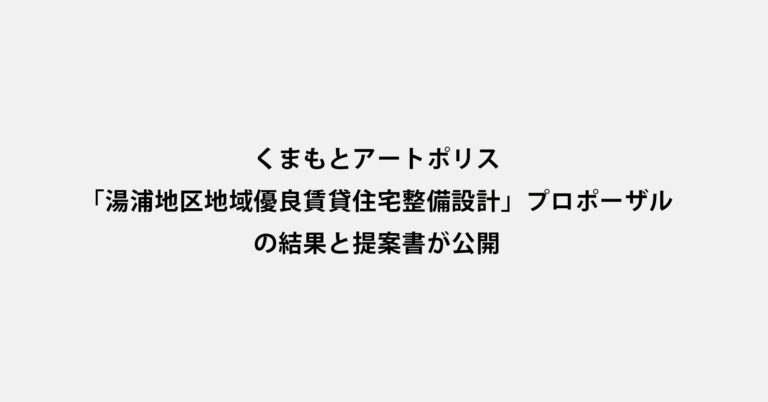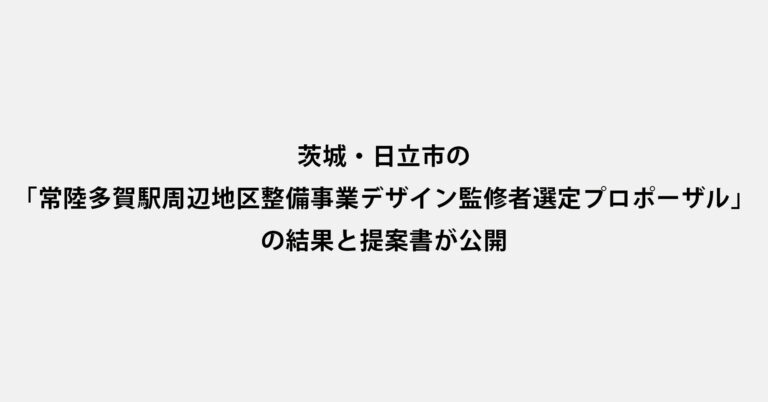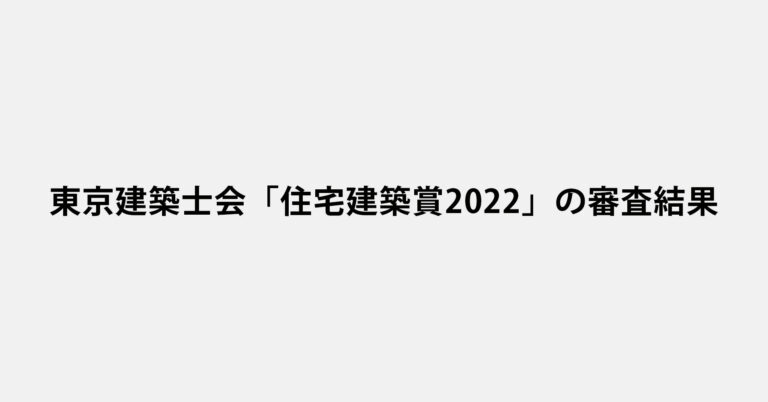近藤陽子 / nLDKが設計した、大阪の住宅「エンガワハウス」です。
土砂災害に若干のリスクを有する場に計画、施主の不安払拭を目指して災害への備えとなり日常の豊かさにも寄与する高基礎の“エンガワ”を考案、眺望を取り込みつつ生活の余白の場もつくる事が意図されました。
100年に一度の災害に備え長大な堤防を海岸線に築造する。防災の観点から至極まっとうであるが、非日常への備えが、海が見える、という日常の愉しみを奪ってしまうことにはやり切れなさは感じる。出来れば日常も非日常も豊かにするものであって欲しい。
日本国内で建築する以上、災害のリスクは免れない。いかに災害に備えるか、と同時にその設えを日常の豊かさにも寄与させる。本プロジェクトのメインテーマである。
計画敷地は昭和40年代に山の裾野を開拓した住宅地であり、土砂災害のリスクを有していた。
当該敷地はイエローゾーンに当たり、建築上の制限は無いが、建築主の不安を少しでも払拭するためレッドゾーン(原則建築不可、擁壁の設置や土砂高さまでRC造等で建築することが求められる)の建築条件を一部計画に取り込むこととした。一方で建築主の夫は在宅の際、そのほとんどの時間を庭で過ごされていた。そこで室内と庭の連続性を考慮し、また敷地を選んだ決め手が敷地南側の公園に植えられた桜の美しさであったので、室内から公園を眺望できることも配慮した。
これらの与件を「エンガワ」で実現しようと考えた。縁側は奈良時代にその原型が見られ、大正時代には庶民の住宅にも広く取り入れられた。室内と庭を曖昧につなぐ日本独自の建築要素である。しかし住宅の狭小化に伴い庭が無くなったこと、高気密高断熱を重視し外へ開くことが嫌われるようになり、姿を消しつつあった。ここ数年、省エネ指向や災害経験から、外に開き自然エネルギーを取り入れることが見直されつつある。本プロジェクトでは伝統的な縁側をアップデートしエンガワとして提案している。