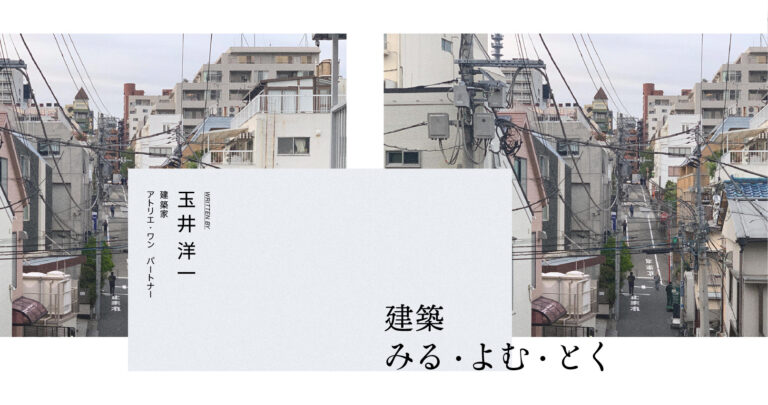ネリ&フーによる、中国・深センの「南投市ゲストハウス」。既存建物を改修した宿泊施設で都市の中に古さが残る街の特徴に注目、路地裏や日常を取り込む為に構造体に切込みを入れ垂直な中庭を計画、空間や意味を創造し都市の流動に溶け込ませる photo©Chen Hao ネリ&フーによる、中国・深センの「南投市ゲストハウス」。既存建物を改修した宿泊施設で都市の中に古さが残る街の特徴に注目、路地裏や日常を取り込む為に構造体に切込みを入れ垂直な中庭を計画、空間や意味を創造し都市の流動に溶け込ませる photo©Chen Hao ネリ&フーによる、中国・深センの「南投市ゲストハウス」。既存建物を改修した宿泊施設で都市の中に古さが残る街の特徴に注目、路地裏や日常を取り込む為に構造体に切込みを入れ垂直な中庭を計画、空間や意味を創造し都市の流動に溶け込ませる photo©Chen Hao ネリ&フーによる、中国・深センの「南投市ゲストハウス」。既存建物を改修した宿泊施設で都市の中に古さが残る街の特徴に注目、路地裏や日常を取り込む為に構造体に切込みを入れ垂直な中庭を計画、空間や意味を創造し都市の流動に溶け込ませる photo©Chen Hao ネリ&フー が設計した、中国・深センの「南投市ゲストハウス」。既存建物を改修した宿泊施設で都市の中に古さが残る街の特徴に注目、路地裏や日常を取り込む為に構造体に切込みを入れ垂直な中庭を計画、空間や意味を創造し都市の流動に溶け込ませる事が意図されました。
こちらは建築家によるテキストの翻訳です
切開 / 南投市ゲストハウス
城中村(cheng-zhong-cun ※都市の中の村)とは、工業化以前の集落の名残が、一見すると現代的な大都市の中に存在している現象のことです。ネリ&フーが11室のゲストハウスを建設した南投市は、そのような城中村の一例です。驚異的な発展を遂げる深センの中心に位置する南投市は、裕福な古都から現在のような過密な都心へと発展してきました。現在、南投市を訪れると、住民、露天商、子供、遊牧民が行き交う路地、広場、行き止まりなどにすぐに入り込むことができます。
このプロジェクトは、南投市の路地裏の活気ある環境からインスピレーションを得て、ありふれたものの中にある文化的遺産について考察することを目的としています。人、物、環境といった日常的なシーンが、デザインの主要な素材となるのです。城中村の生活を祝うために、既存の構造体を切り込み、マスキング戦略で、プライベートなアパートメントブロックの内側に新しい公共空間を作り出しました同時に、発掘調査によって、まるで遺跡のように多くの物質層や建築構造が明らかになり、新たな介入によって、過去と現在の間に思いがけない対話が生まれることになるのです。
南投市ゲストハウスのリサーチとデザインプロセスを通じて、スヴェトラーナ・ボイム(Svetlana Boym)の「反射的ノスタルジア」というトピックに関する著作が、このプロジェクトの背後にある思考を導いてくれました。このプロジェクトは、単に表面的な物質的効果を求めて過去を模倣するのではなく、ある種の過去が現代文化を活性化させる可能性を掘り起こすことを目的としています。都市のレイヤリングと断片の包含という概念を探るため、テクトニック・ランゲージを開発し、主要なファサード要素として軽いスクリーンのような被覆材と、スカイラインを「覆う」ものとして対照的に重く表情豊かなアッサンブラージュの2つの処理を明確にしました。
南投の都市景観は、路地の賑わいと同じように、屋根にも個性があり、ギザギザのスカイラインに沿って仮設の庭や野菜畑が点在しています。この進化し続けるヴィレッジの景観を再構築するために、フラットなフローティングルーフを設置し、眼下のストリートライフと上空の新しいパブリックグラウンドのドラマチックなパノラマを創り出しました。屋上の金属製モノリスは、パブリックスペースやサービス機能を備え、屋根裏のスペースに乏しい居住者が求めるヴァナキュラーな付属物として機能しています。
南投の都市構造の真髄である有機的な循環と関わるために、ゲストハウスのアクセスやパブリックスペースは、敷地内にある複雑な路地のネットワークに織り込まれるように設計されています。ゲストハウスの新しいエントランスは、建物の中心部に直接横道が伸びており、まるで隣人や友人を自分の家に招き入れるかのようです。