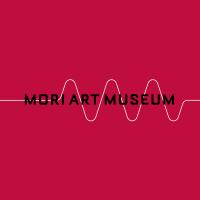栃木・足利市に映画撮影の為に制作された「渋谷スクランブル交差点」のセットの動画です。こちらのページにニュース記事があります。
architecture archive
SHARE OMAとの協同で知られるペトラ・ブレーゼの講演会が、東大で開催
- 日程
- 2019年9月26日(木)
OMAとの協同で知られるペトラ・ブレーゼの講演会が、東京大学で開催されます。開催日は2019年9月26日。ペトラによる2011年3月の東大のレクチャー時にはレム・コールハースが聴講に訪れたそうです。こちらにその際のまとめがあります。
日時:9月26日(木)19:00~20:30(開場18:30)
会場:東京大学 工学部1号館 room 15
SHARE 「磯崎新さん設計建築、勝山市取得へ」(福井新聞)
「磯崎新さん設計建築、勝山市取得へ」という記事が、福井新聞のサイトに掲載されています。類似する事例として、伊東豊雄が1981年に完成させた「笠間の家」を茨城県笠間市が取得し活用している事例があります(2012年2月に発表)。
SHARE 磯崎新の建築展「磯崎新の謎」が、大分市美術館で開催
- 日程
- 2019年9月27日(金)–11月24日(日)
磯崎新の建築展「磯崎新の謎」が、大分市美術館で開催されます。会期は2019年9月27日~11月24日。2019年11月16日には磯崎新も参加する講演会「大分という地霊(ゲニウス・ロキ)について(仮題)」も行われます(申し込みは9/30まで)。
大分市が誇る建築家・磯崎新(1931~)は建築の枠を超え、思想、美術、デザインなど多岐に渡る分野でも活躍する世界的にも稀有な存在です。本展では、展示室を2つのテーマに分け、それぞれのテーマに一貫する磯崎の思考を紐解きます。一つは、東西文化を融合させた独自の空間を作り上げた過程を建築模型に加えて、多くが日本未公開のインスタレーションにより示し、その思想に迫ります。もう一方では、活動初期の60年代から現在に至るまでの都市計画を紹介し、各計画に共通する磯崎の論理を追います。半世紀以上にわたり、あくなき挑戦を続ける磯崎の姿勢を映し出す、意欲的な展覧会です。


創造系不動産の、”建築と不動産のあいだを追究する”新規事業に携わる新たなメンバー(建築不動産コンサルタント)募集のお知らせです。詳しくは、ジョブボードの当該ページにてご確認ください。アーキテクチャーフォトジョブボードには、その他にも、色々な事務所の求人情報が掲載されています。
新規の求人の投稿はこちらからお気軽にお問い合わせください。
■創造系不動産とは・・・
創造系不動産は、2011年に設立され、建築の専門性を持ち合わせたメンバーで構成された新しいタイプの不動産コンサルティング会社です。創業時より建築家やデザイナーとタッグを組み、個人住宅・集合住宅・オフィス・商業施設等の建築不動産コンサルティング及び不動産仲介業務を行っています。創業より8年目になり、メンバーも12名に拡大し本当に多くの建築家・デザイナーの方とコラボレーションさせて頂いてきました。これからは従来の物件探しや仲介、コンサル業務の専門性をさらに研ぎ澄ましていくと共に、新しい取り組みや事業にも積極的にチャレンジし、さらなる価値を提供できる会社に飛躍していくフェーズになると考えています。と言うのも、近くようで遠い建築業界と不動産業界を取り巻く環境にはまだまだ解決すべき課題が山積しています。
・住宅供給過多、人口減少による空家、価値観の多様化。
・建築家住宅が持つ中古としての市場での価値、良いバトンパス。
・相互の業界を取り持つ人材の不足。
・建築業界のお金や不動産、ビジネスへの意識。
・不動産業界の当たり前や固定観念、建築業界への理解。
・空家など築古物件に対しての住宅ローン、リノベーション費用の調達。
・外国人留学生や建築事務所所員の方の賃貸探しの困難さ。
etc上記の中でも、現在創造系では建築家住宅の流通プラットフォームを構築する新規事業に取り組んでおり、入社された方には今までの創造系の業務に加え、建築家住宅の取材、記事の執筆、イベントや企画等の業務も行って頂く事が予想されます。こういった多岐にわたる業務に意欲的に取り組んで頂ける方、不動産の世界に飛び込んで建築業界との懸け橋になり変革を起こしたい方、お金や不動産、ビジネスの知識・スキルを身に着けたい方、自分自身で建築業界に問題意識をお持ちでなんとかしたいと考えている方、様々なキャリアで建築出身のメンバーと一緒に新しい「あいだ」の開拓に挑戦していく方を募集いたします。
不動産の知識ではなく、建築への情熱があれば大歓迎です!また昨年、千葉県の外房に位置するいすみ市に、初の支店「創造系いすみ」を設立しました。これから日本の地方経済の現実に正面から向き合い、地方創生の研究と実践を行うための拠点です。そうした地方での研修も行います。
さらに、創造系不動産では、定期的に社外の専門家(社会保険労務士など)からアドバイスを受け、コンプライアンスを遵守した働きやすい社内作りに取り組んでいます。正社員、パートタイムなど、その方に合わせた多様な働き方を実現できる環境です。是非ご応募いただき、お話しをお聞きできればと思います。
建築史家で東京理科大名誉教授の川向正人による安藤忠雄初期建築原図展についての考察と、安藤事務所出身で建築家・大阪産業大学の山口隆らによるfacebookでのコメント欄でのやり取りが興味深く勉強になります。ちなみに、安藤忠雄初期建築原図展の会期は2019年9月23日まで。
VUILDによる、富山・南砺市の「まれびとの家」のメイキング動画です。この建築の建設までのプロセスはこちらのページにまとまっています。
高度経済成長期以降、職を求めて人々は都心に向かい、都市の一極集中化が進行しました。その代償として、地方の過疎化・高齢化が進み、いわゆる、限界集落化と呼ばれる社会問題が生じています。
そこで、各地域はこの「都市と地方の圧倒的非対称性」に抗おうと、移住者の獲得に力を入れています。インターネットさえあればどこでも働ける時代なので、地域おこし協力隊などの仕組みを通じて、今では地域に参画する若者たちが増えつつあります。
ですが、都市で生まれ育った私にとって、移住・定住には心理的にハードルが高く、同様の感覚を持たれている方が大多数なのではないでしょうか。
そこで、「観光以上移住未満」の家の在り方を提案することで、都市から地方への人口流動を促進したいと考えています。
今、木材が産地から消費者の手に届くまで、加工業者、商社、施工業者など、多くの中間業者を介しています。そのため、輸送距離が長く、大きな環境負荷や時間、コストがかかってしまいます。
また、多くの木材は、規格に沿って販売されているため、丁寧に太く育てた良質材が細切れにされてしまったり、はたまたバイオマスに直行し燃料になるなど、木の良し悪しに関係のないものとして活用されています。
このように、今の林業の産業体系では、地域の生産者の努力が報われず、利益が残りにくい構造となっているのです。
そこで私たちは、デジタル時代における新しい木の流通・生産システムの構築と、それによって生まれる建築自体がどうあるべきなのかを問い直す必要があると考えています。
私たちVUILD株式会社は、ShopBot(ショップボット)という木材などをコンピュータ上の設計データの通りに削りだせる機材を導入しています。
このような技術を駆使することで、大工道具やコンピューターが人間の手の延長線上に存在するように、人間の能力を拡張し、専門性が高くなくても「ものづくり」に取り組めるようになり、「だれもが大工や建築家になれる世界への回路をひらく」ことが可能になります。
オリンピックをテーマにしたNHKの大河ドラマ「いだてん」に、丹下健三役として松田龍平が出演するそうです。
松田龍平
建築家 丹下健三(たんげ・けんぞう)日本建築界の巨匠。日本の伝統美と西欧の近代建築を融合させた斬新なデザインで、戦後の芸術界をリードした。1964年東京オリンピックのために設計した国立代々木競技場は、20世紀を代表する名建築として高く評価されている。

山﨑健太郎デザインワークショップが設計した、神奈川・三浦郡の住宅「千客万来の住まい」です。
敷地は葉山の山側に位置し、緑豊かで穏やかな地域コミュニティを感じられる場所である。
恵まれた環境を生かすように、土間やテラスといった中間領域を周辺環境と建物との隙間を埋めるように配置した。蛇行した前面道路と駐車スペースを一体的な前庭となるように土間の建物を配置し、隣地のお庭が借景となるようなパブリックなテラスや、北側と西側の間知石積擁壁を生かせるようなプライベートなテラスを設けている。
両親や兄弟、また多くの友人たちが住んでいるこの土地は、建主にとって特別な場所だった。
それゆえに、新しい住宅を家族や友人たちが集う「千客万来の住まい」として、この土地の記憶を引き受けていこうとする想いを強く感じた。そうであれば、住宅でありながら、まちとの中間領域となる土間やテラスを都市的な振る舞いを生み出す装置としてとらえてみた。

建築設計事務所SAI工房 / 斉藤智士が設計した、大阪・豊能郡の住宅「堰の家」です。
道路側に設けた大きな建具は、自然(山林)と人口(住宅地)を繋ぐ堰として機能する。
開け放つことで、住宅地から水が流れ込んでくるように、建物内部に様々な環境が入り込み、近隣との積極的なコミュニケーションの場となる。子供が中、外関係なく走り回り、大きなテラスではプールで遊んだり、バーベキューを楽しんだり出来る。またママ友や近隣住民とのコミュニケーションの場となり、ギャラリーやカフェなどの店舗としても使える空間にもなる。逆に大きな建具を閉めると、人が集い寛ぐリビングとなり、24時間多用な形で利用できる住まいとなる。
2つのボリューム内部は、落ち着く籠ったスペースとなるよう天井高さを抑え、山林や土間空間への抜けを作り出し、落ち着いたスペースから活発な空間が望める住空間として計画した。
隈研吾のウェブサイトに、東京・文京区の「お茶の水女子大学国際交流留学生プラザ」の写真が9枚掲載されています。
お茶の水女子大学キャンパスの新しい顔となる国際交流、同窓会活動の場。
キャンパスの外周に立つ大木を避け、その間を縫うように建物を配置した結果、不定型の平面、断面形状が生まれ、その不規則な幾何学面を、アルミエキスパンドメタルをねじりながらラップした結果、この有機的な流れるようなファサードが生まれた。
目の粗いエキスパンドメタルは、光の変化、季節の変化に応じて、多様な表情を呈し、ある時はソリッドに、またある時は透明なものとして出現する。多国籍の研究者や学生の交流の場にふさわしい、両義的でやわらかな状態、すなわち霞や霧のような、自然現象的な建物が、森の中に生まれた。
隈研吾の事務所の様子やインタビュー・作品も収録された、CNN傘下のGreat Big Storyによる動画です。約4分の中に色々と紹介されています。
ヘザウィック・スタジオの展覧会が日本で開催されます。会場は「六本木ヒルズ展望台 東京シティビュー・スカイギャラリー(六本木ヒルズ森タワー52階)」、会期は2020年4月8日~6月14日。「#トーマス・ヘザウィック」から過去の紹介記事を閲覧できます。建設が進められているGoogle新本社の設計でも知られています(BIGと共同)。
デジタルテクノロジーが発展し、日常生活に浸透するにつれて、周囲の環境や他者との関わり方も劇的に変化してきました。このような時代、私たちの感情を他者と繋げる共感を公共空間にもたらすことは可能なのでしょうか?
トーマス・へザウィック(1970年、英国生まれ)率いるヘザウィック・スタジオ(1994年創設)は、ロンドンを拠点に世界各地で革新的なプロジェクトを手掛けるデザイン集団です。ものや場所の歴史を理解し、多様な素材を研究し、伝統的なものづくりの技術に敬意を表しながら、最新のエンジニアリングを駆使する。そのなかで自然環境と対話し、大きな空間もヒューマンスケールに還元しながら、目の覚めるようなアイディアを実現してきました。
本展では、同スタジオの主要プロジェクトを、「ひとつになる」、「みんなとつながる」、「彫刻を体感する」、「都市空間で自然を感じる」、「古い建物を未来へつなげる」、「遊ぶ、使う」という6つの観点から掘り下げます。人間の心を動かす優しさ、美しさ、知的な興奮、そして共感をもたらす建築とは何か? へザウィック・スタジオの取り組みからこの問いを探ります。
芝浦工業大学・西沢大良研究室による2019年前半の研究内容の概要が、公式サイトに掲載されています。いくつかのグループに分かれて都市のリサーチを行っているようです。

山路哲生建築設計事務所が設計した、東京・江東区の「亀戸の集合住宅」です。
押上駅から歩行圏内である亀戸エリアは、空港へのアクセスの利便性やスカイツリーによる観光地化から、徐々に開発が広がっている。多くの寺社が点在する亀戸は戦前からの地域住民の繋がりが強い低層の住宅地だが、そこに混在するように、近年若い家族層が住む高層マンションが建ち並び始めている。本計画の設計中においても、隣接する地上2階建ての木造賃貸アパートの反対側では地上9階建ての高層マンションが工事中であり、ちょうど街が変化していく過渡期であった。大きくスケールの違う建築物が交じり合う地域であり、そのスケールや世代を繋いでいくような建築物であることを目指した。
法的な斜線制限と採光の確保によって切り取られたスカイラインは、山脈のような新たな街の風景を創出した。また斜線いっぱいの容積から生まれる最上階は自ずと高い天井をもつ魅力的な室内空間となっている。エレベーターのない5階建て最上階ではあるが、亀戸天神を望むことのできる特別な部屋をつくることで、高層階の価値を最大化するとともに、地域に馴染む風景をつくっている。
隈研吾・北川原温・深澤直人・原研哉・小泉誠らへのインタビュー音声です。Takram・田川欣哉がディレクターを務める、21_21 DESIGN SIGHT 企画展「㊙展 めったに見られない デザイナー達の原画」の関連企画として行われているものです。
隈研吾のインタビュー