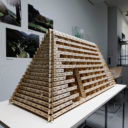アーキテクチャーフォトジョブボードに新しい情報が追加されました
株式会社フリークスの、設計スタッフ・設計補助スタッフ募集のお知らせです。詳しくは、ジョブボードの当該ページにてご確認ください。アーキテクチャーフォトジョブボードには、その他にも、色々な事務所の求人情報が掲載されています。
新規の求人の投稿はこちらからお気軽にお問い合わせください。
建築設計は「経験の上に成り立つ」と言う代表の考えの下、仕事、見聞、遊び、日々の暮らしの充実を追求する建築設計事務所です。
□仕事のこと
来年設立20年を迎える弊社は、集合住宅、リゾート施設等を主とした事業を展開しています。所員11名の小規模な設計事務所ですが、お客様は一部上場の一流企業ばかりです。
2019年ラグビーワールドカップに向け進めているANAインターコンチネンタルリゾート&スパの建築プロデュースは代表作として話題になると思います。
また、建築設計ではGD賞複数受賞の他、新しい商品企画での特許取得や月刊誌面での企画・立案・設計など様々な業務内容は、今後の建築設計人生の広がりや得難い経験になると思います。□見聞のこと
毎年見聞を広めるため海外研修を企画・実施しています。18回目を迎えた今年は、ドイツ・オランダに訪国しました。この国の建築が見たい!から始まる弊社の研修は、普段行くことがないような場所にまで及び、訪国先の建築事務所で頑張る日本の方々との出会いや、お宅訪問、有名建築物探訪など沢山の刺激を実感できると思います。□遊び、日々の暮らしのこと
好きな建築を仕事にする事は幸せなことですが、“一生懸命働く=長時間仕事する”ではありません。仕事をすると同時に貴方の人生を豊かにする事が大切な事です。代表の口癖は「時間内に仕事をスケジューリング、終業時間に帰れるように」です。繁忙期もありますが、残業をしている=仕事ができるという評価は弊社にはありません。豊かな人生を過ごす人がいい仕事も出来るという文化です。