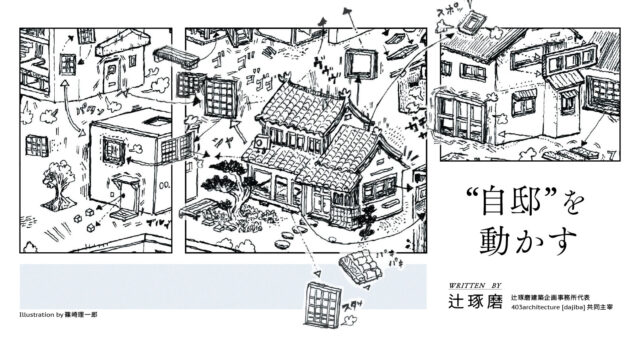SHARE 河部圭佑建築設計事務所による、いくつものゆるやかなアイデアを融合する方法論を試行した「名古屋みなとのアトリエ住居」 / 辻琢磨による本作品の論考「納まりの海に浮かべられた色彩と幾何学」


河部圭佑建築設計事務所が設計した、愛知の、集合住宅の一住戸を改修した自邸兼設計事務所「名古屋みなとのアトリエ住居」です。河部はアトリエ・ワン出身の建築家。
また、本ページでは、河部による論考に加え、辻琢磨による本作品に関する論考「納まりの海に浮かべられた色彩と幾何学」も掲載します
辻琢磨による論考「納まりの海に浮かべられた色彩と幾何学」より
目を見張るのは納まりの種類の多さである。
納まり(ディテールとも呼ばれる)とは、一般的には建築部材であるモノとモノが出会うときのその出会い方についての建築用語であり、例えば「トメ」という納まりは合板同士が直角にぶつかった際に双方の木口を45度にテーパーをつけておくことで出隅の木口を視覚的に消す効果がある。また納まりは、建築家同士の、あるいは設計者と施工者との共有言語であり、同時に空間に施工された後にも使い手や空間に身体的な影響を及ぼすという意味で、建築の平面構成や構造、配置計画と同等か、時にそれ以上の価値を持つ。例えば、カルロ=スカルパというヴェネツィア・北イタリアを中心として作品を残した建築家によるカステルヴェッキオ美術館は、手すりやドアノブ、扉のヒンジや噴水と側溝、什器の脚元まで凄まじい密度で設計されており、ひとたびそのディテールスケールの作品性に気がつくと、この建築の中に納まりという名の「作品」が数百-数千個あるのだという想像に至り、目眩を覚えるような建築空間の質を持っている。
河部圭佑による『名古屋みなとのアトリエ住居』を訪れた際も、その時と同じような感覚を少なからず覚えた。しかしスカルパの納まりは石とスティールを組み合わせ、圧倒的な職人技術に支えられた精巧なクオリティであるのに対して、この建築の納まりは基本的にDIYでもできる、小径の木材を転用した素人仕事を前提にした納まりの集積である。既存と新規の取り合い、異素材の取り合い、同素材の取り合い、家具から建築のスケールまで、わずか30㎡足らずの空間の中に、独自の納まりが数多収められている。
以下の写真はクリックで拡大します












河部圭佑による論考「いくつものゆるやかなアイデアを融合する」。
築45年鉄骨造4階建の集合住宅の改修である。名古屋市港区には名古屋港を拠点とする産業が広がり、この建物もいわゆる住工混在地域に立地する。
住民の高齢化が進むこの集合住宅に生じた空室を、新しい世代のライフスタイルが可能な空間に変えていくことが求められ、働きながら暮らすことのできる空間=アトリエ住居を提案した。この202号室は自邸兼設計事務所である。
ここでは、1つの明快なコンセプトを展開するように建築をつくる(ダイアグラム1)ことはしていない。
以下の写真はクリックで拡大します

どちらかというと、いくつものゆるやかなアイデアを出発点に、それらを紡ぐようにして建築をつくる(ダイアグラム2)ことを試みている。
以下の写真はクリックで拡大します

例えば、おおらかなワンルーム空間であることを強調するように4隅の柱型と梁型を青色に塗装しているが、そこで青色を選択する1つの明快なコンセプトはない。さまざまな文脈や記憶の断片の集合体として青色が選択されている。
港の海があり、濃尾平野に位置するこの敷地や周囲からは空が広やかに見える。工場の散在するこの町は基本的にグレーで、相対的に道路標識の青色が色彩として浮かび上がる。名古屋を本拠地とする中日ドラゴンズのチームカラー。隣接する小学校のプールの柵は青く塗装され、古い木造賃貸アパートの屋根には青い日本瓦がのっている。
以下の写真はクリックで拡大します

この町を歩いていると、ガルバリウム鋼板の外壁やトタン波板の庇など住工混在地域特有の素材感が感じられる。むき出しの金属配管を纏う工場の前には旋盤加工で生じたアルミのくずが積まれ、町全体として即物的でワイルドな印象を受ける。
このような地域的文脈から素材とディテールの検討を行なった。アルミ複合板の壁と床、ステンレス板の垂れ壁、金属蒸着のカーテン、鉄工職人が製作した家具。町の体験と建築の体験とが連続することを目指している。
以下の写真はクリックで拡大します



時間的文脈からも建築を考えている。
改修前は木造のインフィルが挿入されていたが、それらを一度解体し建材を転用した。105mm角の柱材を20mm厚にスライスし、床に敷き詰めた。鴨居や柱をコンクリートブロックの上に渡しただけのベンチを設けた。アトリエに面する既存のモルタル壁を研磨しエポキシ樹脂を塗布した。打合せの際には壁一面にマーカーで書き込み、消すことができる。
以下の写真はクリックで拡大します







地域的文脈や時間的文脈の他に、雑多な記憶の断片がこの建築のいくつものゆるやかなアイデアの要素となっている。
例えば、アトリエと寝室の間には丘のような壁を設けている。空間としてはつながっているので風や光は抜けるが、先が見えない。移動していくとだんだん奥が見えてくる。なだらかな地形を体験した記憶が、丘のような壁というアイデアにつながる。
以下の写真はクリックで拡大します



いくつものゆるやかなアイデアを融合するように建築をつくることに興味がある(ダイアグラム2)。
以下の写真はクリックで拡大します

これはただ場当たり的に建築をつくるということではない。重要なのは、それぞれのアイデアが単独でバラバラにあるのではなく、アイデアどうしの関係性を慎重に見出し融合していくプロセスである(ダイアグラム3)。
以下の写真はクリックで拡大します

今回示している方法論は無論発展途上のものであり、今後の設計活動の中でより精緻で深遠なものにしていきたいと思っている。
現段階の仮説として、いくつものゆるやかなアイデアは、
・抽象度/強度が近しく等価に扱えること
・数が多すぎても少なすぎてもその複数性を失うこと
・それぞれの関係性が重要であること
・発散していくのではなく収束させていくプロセスにあること
・秩序は後発的に生じうるということ
が大切に思える。
■建築概要
建物名:名古屋みなとのアトリエ住居
所在地:愛知県名古屋市港区
設計:河部圭佑建築設計事務所
施工:河部圭佑建築設計事務所+佐藤建設工業
構造:鉄骨造
階数:地上4階、塔屋
竣工:2020年6月
写真:きまたこはる
| 種別 | 使用箇所 | 商品名(メーカー名) |
|---|---|---|
| 内装・壁 | 壁1 | |
| 内装・壁 | 壁2 | |
| 内装・水廻り | 洗面 | |
| 内装・照明 | 照明 | |
| 内装・その他 | 見切り材 |
※企業様による建材情報についてのご意見や「PR」のご相談はこちらから
※この情報は弊サイトや設計者が建材の性能等を保証するものではありません
以下の写真はクリックで拡大します
























辻琢磨による論考「納まりの海に浮かべられた色彩と幾何学」
目を見張るのは納まりの種類の多さである。
納まり(ディテールとも呼ばれる)とは、一般的には建築部材であるモノとモノが出会うときのその出会い方についての建築用語であり、例えば「トメ」という納まりは合板同士が直角にぶつかった際に双方の木口を45度にテーパーをつけておくことで出隅の木口を視覚的に消す効果がある。また納まりは、建築家同士の、あるいは設計者と施工者との共有言語であり、同時に空間に施工された後にも使い手や空間に身体的な影響を及ぼすという意味で、建築の平面構成や構造、配置計画と同等か、時にそれ以上の価値を持つ。
例えば、カルロ=スカルパというヴェネツィア・北イタリアを中心として作品を残した建築家によるカステルヴェッキオ美術館は、手すりやドアノブ、扉のヒンジや噴水と側溝、什器の脚元まで凄まじい密度で設計されており、ひとたびそのディテールスケールの作品性に気がつくと、この建築の中に納まりという名の「作品」が数百-数千個あるのだという想像に至り、目眩を覚えるような建築空間の質を持っている。
河部圭佑による『名古屋みなとのアトリエ住居』を訪れた際も、その時と同じような感覚を少なからず覚えた。しかしスカルパの納まりは石とスティールを組み合わせ、圧倒的な職人技術に支えられた精巧なクオリティであるのに対して、この建築の納まりは基本的にDIYでもできる、小径の木材を転用した素人仕事を前提にした納まりの集積である。既存と新規の取り合い、異素材の取り合い、同素材の取り合い、家具から建築のスケールまで、わずか30㎡足らずの空間の中に、独自の納まりが数多収められている。
既存の根太を途中まで残したエントランス、ジャン=プルーヴェの家具を彷彿とさせる先細りのテーブルの梁、15mm角の木材で組まれた水回り、円形平面のファブリックカーテンの吊元を兼ねた棚、既存枠に当てるだけで隙間を許容したトイレの扉、円を部分的に切り取った立面を胴縁で支える舞台装置のような間仕切り壁、既存の壁を撤去した際に生まれたギャップを解消する傾いた合板の埋め木とそこから飛び出し並んだストリップ劇場にあるようなレセップ。まるで、ディテールの海に浸るような体験は、私もまたDIYとホームセンターで買えるような素材で納まりを考えた経験に依るところもあるだろう。しかし、その個人の経験を差し引いても、もはやこの細部で埋め尽くされた海が図と地でいうところの地、つまり全体であるという宣言を感じるほどに、この建築の納まりは豊富である。
一方で、このディテールの海という「全体」に差し込まれた「部分」がある。平面と立面にそれぞれ現れる円という幾何学の一部と、この空間を形どるフレームの青色である。円を代表とする純粋幾何学は、近年では1980年代のポストモダン建築によく用いられ、古くはクロード=ニコラ=ルドゥー『耕作の番人のための家』やエティエンヌ=ルイ=ブーレー『ニュートン記念堂』といった18世紀末の建築家によるアンビルドのドローイングや、ルネサンス後期のアンドレア=パッラーディオの『ヴィラロトンダ』の平面、あるいはローマを2000年見守り続けるパンテオンの天井に現れるように、西欧由来の石の建築に秩序と完全性を与える際に度々用いられてきた、「建築」の代名詞である。幾何学の記号化が消費主義と遊戯性に結びついて華開いたポストモダン建築※1への反省もあり、21世紀の(特に日本の)建築シーンにおいては見かける機会が少なくなったこの全体性と普遍性の象徴を、河部はここに部分として挿入している。一方で、マンション改修の制限でもあるインテリアの境界としてのフレームは鮮やかな青で塗装され、河部にその意図を聞くと周囲の公園のフェンスや、幼いころから親しみのある中日ドラゴンズのチームカラー、海の近くであること、といった個人の記憶の断片が判断基準となってなんとなく青に塗ったという。※2
まとめてみよう。「部分」で満たされた納まりの海という「全体」に、「全体」の象徴である純粋幾何学の円の一部が「部分」として挿入され、且つ記憶の断片=「部分」を意味する青い塗装が施された「全体」を規定するフレームもまた「部分」(差し色)として挿入されている。いわゆる部分と全体の関係が二重も三重にも反転しているのだ。
このように部分と全体の絶え間ない反転によって、トポロジカルな関係としての意味の優劣が(脚注に示すように現代日本建築の空気感も含めて)宙吊りにされることで、この建築に満たされた一つ一つの納まりが潜在的に持っている意味へのより自由なアクセスが可能になり、時に体験する人の脳内の記憶に、時に敷地を超えて周囲の景色に、記号的なリンクが埋め込まれていく。このような納まりの背後に隠された膨大な記号のリンクが空間全体に張り巡らされていることによって、建築を実際に体験する以外の方法で、空間それ自体が「記号」を介して周囲の環境や体験者と相互に影響関係を持ち得るという意味において、この建築は正しく「ポストモダン建築」の再解釈を促すことになる。
ここで、河部も敬愛するポストモダンを代表するアメリカの建築家チャールズ・ムーアの言葉を借りたい。
タリスマンの存在について知ること、そして、それが今日なお脈々と生き続けている生命力を知ることは大切だと思うのである。それは、近代建築の巨匠たちが道半端にして倒れたのとは違う地点、つまり〈純粋な〉形態や、立方体や、シリンダーや、球などでつくられる世界とは違う見方を強調することになるだろう。
ここで、「タリスマン」とはムーアの独特な意味づけがなされている言葉で、直訳すると”御守り”だが、ここでは建築部位に慣習的に込められてきた記号性(柱は男らしさのシンボルであるとか、4本柱のメガロンは裁きの場所の象徴であるとか、ペディメントは首長の威厳と結びつくといった意味で)というニュアンスで使われているのだが、要するにムーアは純粋形態では達成し得なかった生きた記号性に可能性を見出しているといえよう。
河部の取り組みのように、部分と全体の対立(意味の優劣の発生)をその度重なる反転によって宙吊りにした上で、「納まり」に内在された記号が様々なレヴェルで連鎖し、地域や体験者に溶け出していくようなアプローチは、ムーアのような生きた記号性の現代における実践と呼ぶこともできる。数々の建築雑誌の誌面の中に封印された40年前のポストモダン建築の取り組みを、今を生きる私たちが自分たちの価値観に引き寄せて再解釈することができれば、モダニズムから脈々と続く建築の歴史を実感を持って手繰り寄せることができるはずである。こうした歴史への実感こそが建築家に必要なのだ。
※1 本稿でポストモダン建築の現在における評価の正確な検証を行うには知識と紙幅があまりに足りない。ここでの描写は筆者がgoogleで「ポストモダン建築 記号」で検索して得た知識程度の一般論として記した。
※2 原色に近い塗装の仕上げも、幾何学同様に現代の日本の建築家はあまり使わない印象を受ける。特に近年の我が国の若手建築家の作品の改修を中心としたインテリアのプロジェクトを概観すると、基本的にはコンクリートやモルタルの素地、合板を含む木材の素地、鉄骨であれば溶融亜鉛メッキ、プラスターボードかクロスの白ないしグレーが多用され、色味としては白と薄い茶色、灰色でよく構成されている。この住宅もこの青い差し色を除けば同様であり、我々403architecture [dajiba]のプロジェクトを見ても概ねそうだ。しかし現在のヨーロッパの若手の改修の取り組みを見ると、例えばポルトガルのFala Atlierがつくる空間に度々現れるパステルカラーや、ベルギーのArchitecten De Vylder Vinck Taillieuの鮮やかな緑の梁や柱にみて取れるように、鮮やかな塗装色を差し色として使うことはさして珍しくない。『名古屋みなとのアトリエ住居』で「全体」として背景にあるのはリノベーション全盛の現代における日本の建築界の空気感であり、図として挿入されているのが古臭い幾何学と華美な装飾としての塗装という、我々日本人建築家が敬遠しがちな要素である、という意味にも読み取ることができる。それはそのまま、昨今の日本の建築界の空気感を、通時的にも(ポストモダン建築への接続)、共時的にも(西欧の建築・インテリアの潮流との比較)相対化する批評的な眼差しを私たちに与えてくれるだろう。