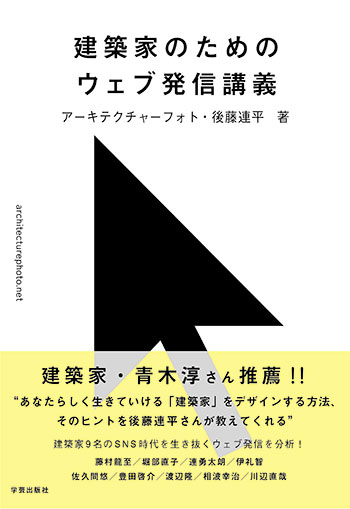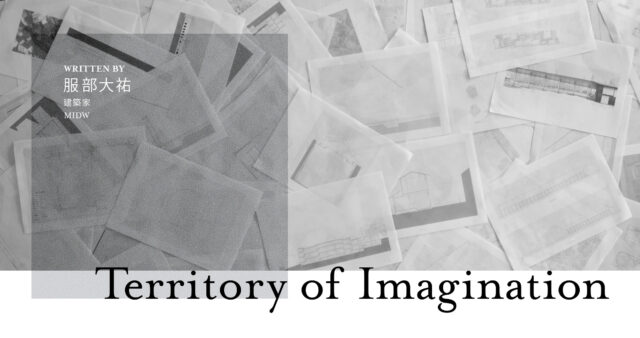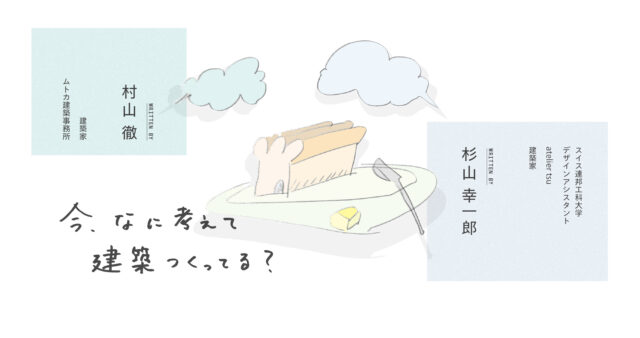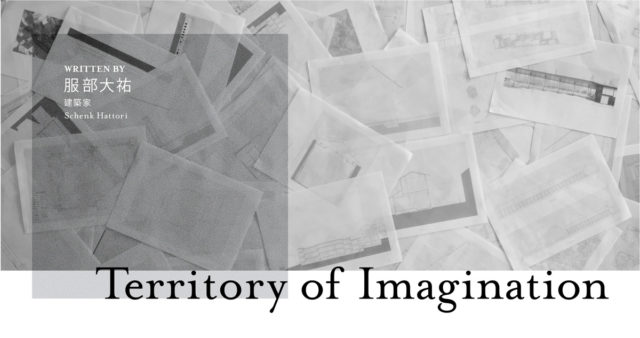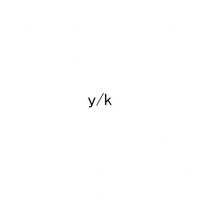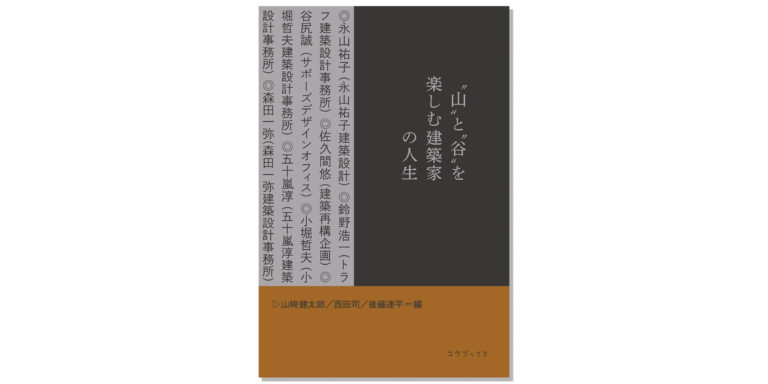
SHARE 【特集:“山”と“谷”を楽しむ建築家の人生】富永大毅によるレビュー「選べない仕事の先に切り開かれる建築家の新しい作家性」
アーキテクチャーフォトではユウブックスから出版されたインタビュー集『“山”と“谷”を楽しむ建築家の人生(amazon)』を特集します。
それにあたり、岸和郎さん(WARO KISHI + K.ASSOCIATES ARCHITECTS)、三井祐介さん(日建設計)、富永大毅さん(TATTA ※旧富永大毅建築都市計画事務所)、橋本健史さん(403architecture [dajiba])にレビューを依頼しました。
異なる世代・立場・経験をもつレビュアーから生まれる言葉によって、本書に対する新たな見え方が明らかになると思います。
その視点を読者の皆様と共有したいと思います。
(アーキテクチャーフォト編集部)

選べない仕事の先に切り開かれる建築家の新しい作家性
建築家が憧れられない時代に教えること
大学の非常勤などで学生に建築の設計を教えるとき、さて、このうちの何人が建築の設計で生きていくことになるだろうかということがいつも頭をよぎる。
自分が大学生の頃の最初の授業で、この中で建築家になれるのは1人いればいい方ですと、いきなり釘を刺されたことを思い出すからかもしれない。
その時に僕はきっと、「それなら人より頑張るしかないか」と思ったはずで、だから先生のあの一言は正しかった、有難かったと今も思っているし、結果としてうちの学年からは建築の設計で独立をした人が4-5人出ることになった。就職氷河期世代だったせいもあったと思う。
話が逸れた。
フレッシュな学生たちを目の前にして僕は、全員を建築家に仕立てよう!などと思って教えているわけではない。かと言って正直そんなに建築家になられると小さいマーケットなんだから困る、という自分の小さな器が僕を抑制しているというワケでもない。建築家志望の学生が減った現状において、建築家として建築の設計を教えることの意味と、それをどう教えたら最終的に建築設計を目指さない学生にとっても実のあるものになるかについて、最近は常に戦っている。
せっかく建築学科に入ったのに、他の人と同じように大学4年の春になると黒いスーツを着て、小さな差異を比べられて病むこともある、あの恐るべき就職活動に流れていって欲しくない。もっと大げさな言い方をすれば、建築家という人種が失われるのを食い止めようとしている。
お会いしたことはないが本著編集の矢野さんも、インタビュアーの山﨑さん西田さん後藤さんもきっと同じ思いなのだろうと思う。
踏み出す力と諦める力
『“山”と”谷”を楽しむ建築家の人生』は7人の建築家が登場し人生の紆余曲折を語るインタビューを書籍化したものである。
この手の書籍は既にたくさんあるが、この本が他のそうした本と一線を画しているのは、全員がナチュラルに従来の古い“建築家”像から脱却したような活動、キャリアを持った人たちだというところにある。
正直に言うと、ロールモデルとするにはちょっととんでもない人たちばかりかもしれない(笑)。永山さんは子育てをしながらどんどん仕事受けちゃうスーパーウーマンだし、佐久間さんは営業を学ぶために保険マンについて行っちゃうし、谷尻さんは編集部に持ち込みに行っちゃうし、森田さんは左官の技術を学びにヨーロッパに行っちゃうし、みな型破り過ぎる。
詳細はぜひ読んで確かめて欲しいが、共通しているのはみんな全く失敗を恐れずに一歩踏み出す力が凄いのと、半ば諦め的に現状をポジティブに変換してしまうところである。端から、仕事がなくてもまあ仕方ないか、じゃあ海外へ旅に行けるな!みたいな感覚しかないことに驚く。
お前の話は聞いていない、と言われそうだが、求められた文字数にだいぶ足りなさそうなので、僕自身の話を少しさせてもらうと、僕はその“失敗を恐れ踏み出せない自分”を自らで壊しに行ったように思う。
都立大学4年生時に、実質2-3年建築を勉強したくらいじゃどうしたらいいかなんて何にも分からんと、就活も院試も受けず、卒業後はどこにも所属せずに1年フリーターになる決断をした。接客業をしたり家具職人のところに泊まり込みで働いていたりして、試行錯誤の中でそれまでの自分に足りないと思われる人間としての力を磨こうとしていた。
大学院の試験を受けた後はバックパッカーだった先輩の影響をモロに受け、貯めたお金で2か月の予定でヨーロッパへ建築巡礼に出た。
ところが2週間目にしてスペインのトレドという街で、当時流行っていた首絞め強盗に遭会い、後ろから首を絞められて気絶している間に着ているもの以外すべて失ってしまう。
帰るしかないか、いやこれで帰ったらカッコ悪いよなーなどと悩んだ挙句、2-3日パスポート再発行のためにマドリッドに滞在して、戻ってきたトラベラーズチェックを失った20㎏近いバックパックの代わりに、スーパーのビニール袋に入れてそのまま旅を続けた。
その後も行く先々のユースホステルで首を絞められた話を笑い話として話し、代わりにいらない服や、街や建築の情報をもらって結局予定通りの2か月、旅を完遂した。
今と違ってiPhoneなどもちろんない時代。当初何日にこの町に行って何を見て、という予定びっしりだったスケジュール帳はとっくに失われ、曖昧な記憶で降りた小さな駅で、スケッチを書いてタクシードライバーに行き先を教えてもらったり、ユースであった日本人に明日パルマで中田英寿の試合があるよと誘われたのについて行ったり、最終的には全然行く予定のなかったシチリアに行って海に潜ってウニを取ったりと、軽い荷物なのでとても自由に、セレンディピティを満喫して帰ってきた。あれ以来旅に出るとき、僕の荷物はいつも少ない。
結果思っていた以上に、自分の中の“失敗を恐れ踏み出せない自分”というものが無くなってしまった。
そしてそれ以上に自分ではどうにもならない状況を諦めのように受け入れて楽しく生きることを身に付けた気がする。人生意外とどうにでもなる。
だって全然あてのない異国の地で持ち物全部なくなってからでも、どうにか楽しく旅して帰ってこられたワケだから。
しかし少なくともその当時の僕にとって大学を出て何にも属さないというのは、それまでなんとなく周りと同じように学歴社会に生きてきた自分にとって、人と違う生き方をするんだというひとつの宣言ではあったのだと思うし、本著になぞらえて言えば、あの首を絞められた瞬間こそが自分の人生の最大の“谷”であり、逆にそれまでの生き方の価値を反転する “山”だったのだと思う(笑)。
もしかしたら人と同じ価値観を強いられがちな社会において、人生どうにでもなるみたいな開き直りやある種の謎の自信こそが、人生を豊かにする大事な秘訣のひとつなのかもしれない。
本著にも各建築家の“失敗を恐れ踏み出せない自分”の壊し方(お金がなくて生きていけなくなるかもしれない不安に押しつぶされずに諦める方法)みたいなものが(先天的なものも含めて)インタビューの中にきちんと表れている。この人がこんなに自由にふるまえるのは何故なんだろうか、と各自探しながら読むのも楽しみ方のひとつだ。
建築家の言説が社会と接続しない時代に
さて本題である。なかなか聞けないお金の話やどういうスタッフを採用したいかなど、同業者の僕が読んでも本当に聞きたい話が満載の本著なので、学生だけでなくこれから独立したい人、独立して悩んでる人こそ読むべき一冊になっているが、本著がもうひとつ明らかにしているのは、現在形の“建築家の作家性”についての議論のベースとなるようなものだと感じる。
僕自身には4人の建築家の師匠がおり、それぞれの師がどういう方法論で自分の建築の考え方を世に出そうとしているか、常に学び取ろうしてきた。つまり従来の建築家の価値観で生きてきた人間だ。
だから独立する頃には漠然とこういうものを世に出したいなというイメージがあったように思う。
しかし実際独立して自分で仕事をしてみると、建築設計の仕事が面白いのは基本的には仕事を選べないところにある。まず選べない仕事があって、その仕事が建築家を育てるという、あたりまえの事実に直面する。
特に独立したての頃は、施主も誰だかよく分からない人間に頼むわけだから、自分のやりたいことにバイアスをかけ過ぎてきちんとそれをコミュニケーションできないとすぐに仕事を失う。しかし逆にそれが何もなくても長期的にはじゃあ君じゃなくてもいいかと仕事を失う。
施主のなんとなく出してきた条件の先に何があるかを丁寧に読み取って、その中に自分が面白いというものをいかに見つけて提案ができるか、探偵のような観察力とそれを施主に伝える説明力が常に求められている。そして仮にその提案に対して施主がとんでもないことを言い出したとしても、現場が全然図面通りにいかなくても、思い通りにいかない状況を半ば諦め的に楽しめる力。
これは大学の設計課題などで評価されやすい発想力や自分の世界観重視のあり方とかなり異なるので、学生は戸惑うかもしれない。
一方でこの事実が50年前と現代とで大きく変わったということでは全くない。
建築家の社会的地位の違い(施主と建築家の力関係)こそあれ、本著が明らかにしているのは、本当は裏では施主の要望とかコストの話とかいろいろあっても、カッコいい言説でそれを隠してしまう建築家に、僕らが長いあいだ騙されていたという事実である。
これを暴くかのように、本著は青木事務所出身の永山さんのインタビューに始まり、続いて最初のホテルインテリアの仕事で、計画的なトップダウンではなく、いきなりユーザーが使うアイテムをどうレイアウトするかという、使う側からの逆転的な発想(「テンプレートインクラスカ」2004年)で施主の気持ちを掴んでしまうトラフ鈴野さんのストーリーへと続いていく。
リテラシーの高い人は建築作品や言説から人間を読み取ることができてしまうけれど、そうでない大多数の人にとって建築家の言説が社会的に強い意味を持たず、経済の流れが優先される現代において、建築家がどのように、この人に頼まないとダメな理由(“作家性”)をつくれるか、それは山が好きな小堀さんの話のように、もしかするとこうした人間ごと掘り下げるインタビューでしか、もはや明らかにならないのかもしれない。
ここに本著が単なるインタビュー本ということを越えて建築界に投げかける大きなメッセージがある。従来的な建築家の強い作品性や言説が次の仕事を生み出しにくい時代に、何が建築家の“作家性”として浮かび上がっていくべきなのか。
選べない仕事をひとつひとつ丁寧に紐解いていく中に生まれる“作家性”は、五十嵐淳さんの言うような“癖”として、建築作品そのものに分かりやすく表れることもあれば、谷尻誠さんのように新しい仕事や新しい会社を生み出す行為そのものや、佐久間さんの違法建築が既存建築の9割だという事実から建築法規のプロになっていくという仕事のあり方そのものとして表れることもあり、その表れ方を変え始めている。
じゃあいったいどうしたらいいんだ、と混乱することはない。
決して建築学が廃れたということではなく、科学よりも物語の方が伝わりやすくなったということでしかない。建築家がやってきたことはずっと変わっていなくて、その表れ方、表し方が今変わりつつあるだけなのだ。これは、編者の一人であり、自ら建築のWEBメディアを仕掛ける後藤連平さんが『建築家のためのWEB発信講義』で訴えているメッセージとも通じるし、西田司さんの最近の“神奈川大学新国際学生寮”についてのWEB発信の実践や山﨑健太郎さんの日常のWEB発信の巧みさとも通じるように思う。
誰も目指していた建築家にはなれない
冒頭の話に戻ろうと思う。
僕が大学で建築の設計を能力的に分解して教えるようになったのは、そもそも今の学生があまりに正解を求めたがるからである。
設計行為をどう分解しているか簡単に説明すると、
今すでにあるもの、敷地条件や既往事例をよく観察して、
その観察から発想したものを、図面で検証しながら掘り下げては形にまとめ、
言語的に批評しながらまた観察する、
というサイクルを繰り返した上で、
考えをまとめて、プレゼンボードに自分らしく表現し説明する。
その結果として存在しない“正解らしい”ものに限りなく近づこうとする。
そういう作業だと伝えている。
たとえばこの先であなたがパートナーとどこで結婚式をやるか決めなきゃいけなくなった時、そこには正解がないでしょうと僕は言う。
だからあなたがやることはまず、今どういう結婚式のスタイルがあるか、近所あるいは縁のある場所にどういう式場があるか調べることに始まり、その中から自分にはこれが合っているというものを選んで、より自分たちらしい式にするためにこうしたいみたいな話を伝わりやすく翻訳(建築における図面化)してパートナーに伝え、それをもうひとつの視点から客観的に言語化されたら、じゃあこれもっとこうしようかとまたサイクルをもう一周繰り返すコミュニケーションを続けていくことになる。
多少の順序の違いなどはあるけれど、つまり正解のない問題に取り組む方法はいかなるケースにおいても、いつも一緒ですと。
改めて冒頭の問いに答えを出すと、僕が今後建築の設計を続けていくか全然違うことをするのか分からない学生たちに向けて送ろうとしているのは、この先の人生のほとんどが正解のない問いであり、それに取り組む方法を建築の設計を通じて学んで行ってほしいというメッセージである。
本著に出てくる建築家たちも人生における正解のない問いに、ゴールを想定せずに向き合った結果として、今建築家と呼ばれる存在になっているのであり、そもそも新しい建築家像を追求できる人だけが建築家と呼ばれ得るのかもしれない。誰も目指していた建築家そのままにはなれない時代である。そう思って読み返すと本著の7人の建築家の中に、最初からほとんどこうなりたいみたいな強い建築家像がないことに気づく。
自由であることと慣習的であることの間に
しかし世の中には一見すると正解らしい“みんなと同じ”方法が溢れている。
ある時間になると、多くの人が自分なりの正解に近づこうとする学びを突然停止して、みんなと同じリクルートスーツを着て、他の人よりいい給与待遇を求め、常に他の人との比較で生きなければいけなくなるシステムに簡単に巻き込まれてしまう。就活の話だけでなくそれはたとえば独立して建築の細かいディテールを書いている時でも一緒だ。正解らしい“みんなと同じ”方法は常に溢れている。
その選択が間違っているということではない。そこには蓄積された慣習的な知性が待っているかもしれない。しかし建築設計という門を開いてしまった後で、それは果たしてあなただけがたどり着ける本当に“正解らしい”選択だろうか。
学問というのは本来あなたを自由にするためのものだ。
本を読むこと事もまた同じである。非常に魅力的な7人の建築家の人生が教えてくれるものは、一見みんなバラバラで接点がないようだが根っこはシンプルだ。失敗を恐れずいろいろな状況を受け入れて挑み続ける先に、たくさんの慣習に囲まれた中、なおどう自由に考えることができるか。自分で考えて“正解らしい”答えを目指して行動し続ける先にのみ、自分にしか頼めない仕事が立ち現れるのだ。
そして、その仕事はまだ“建築家”という名で呼ばれている。
富永大毅(とみなが・ひろき)
建築家。1978年千葉県船橋市生まれ。2001年東京都立大学工学部建築学科卒業、2003年ミュンヘン工科大留学、2005年東京工業大学理工学研究科建築学専攻修了。2005-08年千葉学建築計画事務所、2008-12年隈研吾建築都市設計事務所を経て2012年富永大毅建築都市計画事務所設立、2019年に株式会社TATTAに改組。2017年~首都大学東京 非常勤講師、2018年~日本大学理工学部非常勤講師。
住まいの環境デザイン・アワード2019ベターリビングブルー&グリーン賞(「入母屋の離れ」)、JID AWARD2017インテリアスペース部門賞(「垂木の住宅」)、第6回木質建築空間デザインコンテスト住宅部門賞(「片流れの家」な)ど受賞多数
主な作品に、「四寸角の写真スタジオ(スタジオバジル)」(新建築2019年10月号掲載)、「ドーマー窓の家」(新建築住宅特集2016年7月号掲載)、「蔀戸のパレット」(商店建築2015年12月号掲載)など、住宅、共同住宅、クリニック、店舗など新築からインテリアまで主に無垢材利用を主題に幅広く手掛ける。
■書籍概要
『“山”と“谷”を楽しむ建築家の人生』
7人の建築家に人生で「人生で苦しかった時」「乗り越えた時」を尋ねたインタビュー集。自分の道を切り開くためのメッセージ。
ときにしたたかに、ときに子どものように純粋に建築と向き合った話は、建築の仕事を楽しむことをはるかに超えて、人生をいかに豊かで意義深いものにできるか、という広がりさえもっている。
その言葉たちは目の前にある不安を大きなワクワク感がうやむやにして、建築を目指す若者たちの背中をあっけらかんと押してくれる。
建築に臨む態度、経営思想も尋ねており、あらゆる世代の設計関係者にもお薦めできます。
【目次】
・始めに 人生を有意義なものとするために 山﨑健太郎
1、永山祐子 (永山祐子建築設計) /「やらなくていいこと探し」から道を切り開く
2、鈴野浩一(トラフ建築設計事務所) / 繋がりを大切に、熱中しながら進む
3、佐久間悠(建築再構企画) / ニーズとキャリアから戦略を立てる
4、谷尻誠(サポーズデザインオフィス) / 不安があるから、常に新しい一手を打つ
5、小堀哲夫(小堀哲夫建築設計事務所) / 探検家的スピリットで建築を探求する
6、五十嵐淳 (五十嵐淳建築設計事務所) / 琴線に触れるもの、違和感と選択
7、森田一弥(森田一弥建築設計事務所 ) / 旅と左官を通し、歴史と文化を血肉化する
・鼎談 いつの日か、マイナスもプラスに書き替わる / 山﨑健太郎・西田司・後藤連平
・“山”に登って振り返ると、“谷”だったと気づいた。/ 西田司
・後書き建築人生を切り開く開拓者たちへ / 後藤連平