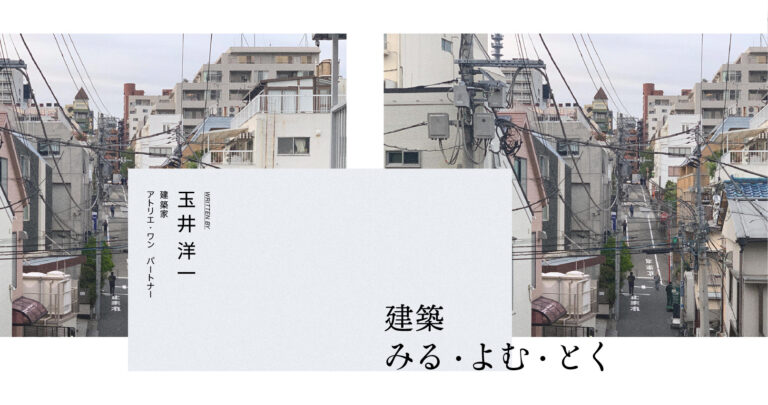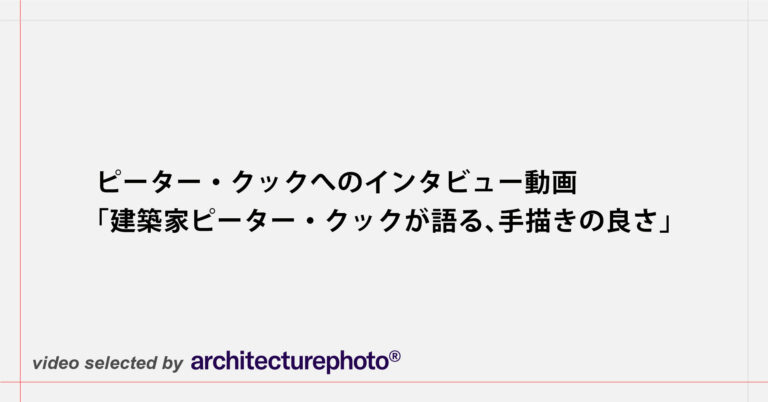カーシフ・チョウドリ / URBANAが設計した、バングラデシュの病院「フレンドシップ・ホスピタル」が2021年の王立英国建築家協会国際賞(RIBA International Prize 2021)を受賞しています。サイクロン被害を受けた地域に医療を提供する施設で、持続可能で低コストで建てられ、海面上昇の影響を受けた環境条件にも対応しました。
こちらはリリーステキストの翻訳
バングラデシュの病院が、世界で最も優れた新しい建築物に贈られる「2021年RIBA国際賞」を受賞
バングラデシュ南西部のベンガル地方の水を湛えた風景の中に建つ、カーシフ・チョウドリ(Kashef Chowdhury / URBANA)が設計した遠隔地コミュニティ病院が、優れたデザインと社会的影響に与えられる建築界の世界最高賞「RIBA国際賞2021」を受賞しました。
持続可能で低コストのこの病院は、バングラデシュ南部地域のサトキラの地域コミュニティに不可欠な医療サービスを提供し、2007年の大型サイクロンで大きな被害を受けた沿岸部の数千人の人々に医療ライフラインを提供しています。この建物は、海面上昇の影響を直接受け、壊れやすくダイナミックな環境であるベンガル地方の厳しい環境条件に革新的に対応するもので、設計の中心にある配慮と人間性が評価されました。
この病院は、長年のNGO・フレンドシップの協力のもと、遠隔地の農村地域を強化し、力を与えるという組織の使命の一環として建設されました。かつては穀物畑に囲まれていた農地は、海水面の上昇によりエビ漁に転用されています。そのため、この病院では水が設計の中心となっています。敷地内には運河が縦横に走り、入院患者と外来患者を分離しています。施設内のあらゆる場所で降った雨水を排水し、新設のタンクに貯めています。塩分を含んだ地下水は実用的な用途にはほとんど使用できず、絶え間なく降る雨で排水する必要があるため、不可欠な資源でありツールです。この水路は、耐え難い暑さの夏の微気候冷却にも役立ち、エネルギー消費の高いエアコンの必要性を回避することができます。
NGOの永続的な社会変革への取り組みを反映し、カーシフ・チョウドリのデザインは、訪問者や患者、医療従事者に高揚感と心地よい体験をもたらし、健康や癒しと一致する穏やかな環境を作り出しています。親密な中庭は、病棟に光と自然換気をもたらし、患者や訪問者が自然を眺めながら休息できる空間を提供しています。病院内の繊細なエリアは、遮蔽された廊下や二重のアーチによって熱帯の直射日光から保護されています。病院内は、耐久性とコストに優れた地元の煉瓦を使用し、煉瓦の開口部には日陰を作り、自然冷房を導入しています。
RIBA国際賞の審査委員長であるオディール・デックは、次のように述べています。
「フレンドシップ・ホスピタルは、社会的革新を通じてコミュニティに尊厳と希望を与えるというNGO・フレンドシップの慈善的使命を反映し、人間性と保護に満ちた建築を体現しています。カーシフ・チョウドリは、周囲の環境と巧みに融合し、地元の伝統的な工芸品を用いた人間味あふれるデザインの建物を実現しました。この病院は、医療への不平等なアクセスや、気候変動が脆弱なコミュニティに与える深刻な影響など、世界的に重要な課題に関連しています。この病院は、比較的低予算で、困難な状況下で、優れたデザインによって美しい建築を実現できることを証明しています。この病院は、人間に捧げられた建築物の祝典なのです。」
RIBA会長のサイモン・オールフォードは、次のように述べています。
「フレンドシップ・ホスピタルは、重要で大規模な建物を控えめな予算で建設し、地域社会や自然環境に配慮した、思慮深く創造的な設計の模範となるものです。カーシフ・チョウドリは、革新的で明快、洗練され、経済的で楽しい、社会的インパクトのある建築を創り出しました。地方に不可欠な医療サービスを提供し、増大する気候変動の緊急事態に対処しています。この作品が2021年の国際賞受賞者として祝われることを嬉しく思います。」
カーシフ・チョウドリは述べています。
「RIBAと審査員は、世界の周辺地域から、建築談義の中心へと導き、世界で最も重要な賞の対象となるプロジェクトを特定したのです。私は、このことが、資源や手段が限られているにもかかわらず、あるいは限られているからこそ、人類と自然の両方に配慮した建築に取り組み、今日我々が直面している惑星規模の緊急事態に集団で立ち向かおうとする、より多くの人々を鼓舞することになると確信しています。クライアントであるフレンドシップとその創設者であるルナ・カーン(Runa Khan)氏の絶え間ない支援と理解、そして、私たちの社会、文化、そして最も愛する自然へのコミットメントという厳しい四半世紀を共に過ごした多くの建築家、エンジニア、コンサルタントに、私は心から感謝しています。」