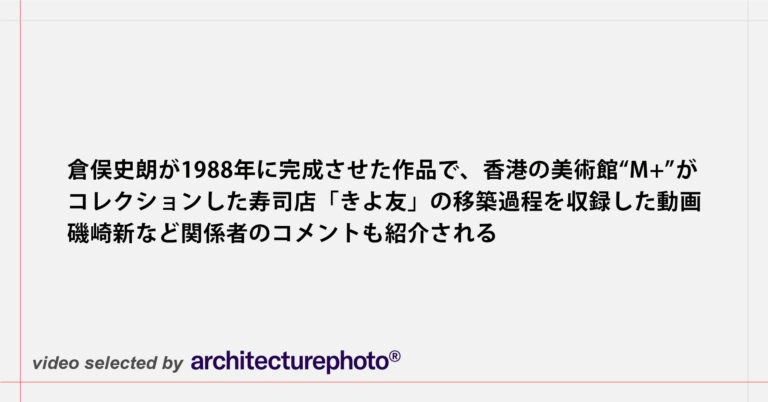アーキテクチャーフォトで、先週(期間:2021/12/20-12/26)注目を集めたトピックスをまとめてご紹介します。リアルタイムでの一週間の集計は、トップページの「Weekly Top Topics」よりご覧いただけます。
- 藤本壮介建築設計事務所による、京都の「アメノシタ・パビリオン」。ロームシアター京都の屋外空間を敷地に、世界文化交流祭“KYOTO STEAM”の為につくられた、120mm角で長さ4mの木材を積層した鳥の巣のような建築
- 畠山鉄生+吉野太基+アーキペラゴアーキテクツスタジオによる、神奈川・川崎市の住宅「河童の家」。建面と法規で縦動線が空間の全てを決めるような条件に、中央配置した階段に椅子等の機能と構造的役割も担わせ45mmの薄床を可能とし、立体的で回遊性のある連なりの空間をつくる
- 園田慎二 / SSAによる、群馬・高崎市の二世帯住宅「T / K邸」。物の多い賑やかな生活の想定に、予めの計画で空間の質が決定的になるのではない、彩色建具等の細やかな設計が集積し家具類と連なり部屋内に充満し一体となる建築を目指す
- 森清敏+川村奈津子 / MDSによる、東京の「立川ANNEX – 倉庫×家」。1階が写真スタジオ兼倉庫で2階が施主の別宅という建築で、90角斜材が母屋を支え双曲放物線面をつくる小屋組架構により、個性的で大らかな一室空間をつくりだす
- 川添純一郎建築設計事務所による、兵庫・洲本市の別荘「RIVER SEA」。周辺への影響を抑え機能整理のため建物を3棟に分離し配置、全体を横断して繋ぐ曲線の“path”が内外の境界を曖昧とし、移動する事で異なるシーンが連続する建築を構想
- 藤田時彦 / atelier umiによる、滋賀・高島市の、築100年の古民家を改修した「umi」。設計者の自邸と事務所とイベント空間を兼ねた建築で、景色の良い琵琶湖沿いを敷地とし、職住分離ではなく職住一体とすることで新たな出会いを期待し計画
- スノヘッタ+竹中工務店による、東京・渋谷の、コワーキングスペース「Pangea Digital Garage」。筆の跡から着想を得た“スーパーファニチャー”を中心に据え、この家具が施設の諸機能や個々の作業空間を包含、日常の交流を通じ大きなヴィジョンへとユーザーを導く
- 千葉学建築計画事務所が最優秀者に選ばれた、福島の「安積中高一貫校」設計プロポの提案書。2次審査に選ばれていた6組の提案書も公開
- 五十嵐敏恭 / STUDIO COCHI ARCHITECTSによる、沖縄・南城市の住宅兼工房「真謝原の家」。豊かな自然の中の開放的な住まいの要望に、必要諸室の機能と面積を決め“開放的な広間”と“シェルター”の空間に分け計画、自然から身を守り風土に寄り添い暮らせる建築をつくる
- TAKT PROJECTによる、宮城・仙台市の、自社のサテライトオフィス「TOHOKU Lab」。“つくる”と“考える”に専念し未知の“何か”にアプローチする空間として構想、素材と用途の境界線上に存在するオブジェクトを配置することで、利用する人間の創造性を引き出すことを意図
- ギゴン / ゴヤーによる、スイス・キュスナハトの集合住宅。1階に商業テナント上4層に住戸という構成で、施主の要望に応える突き出たバルコニーを外観の特徴とする、旧建物のキャラクターを反映したアルミニウム波板ファサードの建築
- 岡山泰士+森田修平+仲本兼一郎 / STUDIO MONAKAによる、京都市の、設計者の自邸「森田邸」。将来的に“小商い”を行いたいとの要望に、建物をほぼ中央配置することで敷地内に“余白”を確保、平面計画にも将来を見越した空間を組み込む
- ギゴン / ゴヤーによる、スイス・チューリッヒの、複合ビル「Hotel and Office Building Greencity」。工業団地の開発の一環として計画、ホテルとオフィスをプログラムとし、ファサードの構成要素の意匠で両方に適した印象を与える
- ヘルツォーグ&ド・ムーロンによる、サンフランシスコの20世紀初頭に完成した発電所を改修した複合施設「Power Station」。約12万㎡の湾岸地域の再開発計画の一部として計画
- 建築家のリチャード・ロジャース氏が亡くなりました
- フロリアン・ブッシュ建築設計事務所による、静岡・伊東市の「伊豆高原のI邸」。典型的な別荘用地と捉えた場所の茂みの中に建てられ、建築により風景を“濾過”し遠方の自然という資産を視界に取り込んだ、家族が週末を過ごす小さなシェルター
- ギゴン / ゴヤーによる、スイス・チューリッヒの「ローザウ・オフィスビル」と「ヴィラ・ローザウの改修」。隣接した二棟の建築で、新築オフィスビルは都市構造を意識した量塊と庭園の既存フェンスデザインを参照したファサードを特徴とし、19世紀築のヴィラは外観の保存修復と内部の刷新が行われる
- 長坂常 / スキーマ建築計画による、東京・銀座の、レストラン兼ショップ「ギンザ・イニット」。レトルト食品を食事として提供し販売もする店舗で、レトルトとの共通性をダイノックフィルムに見出し全面的に使用、内装制限もクリアしフィルムだからこその木目表現を追求
- SANAAの設計で2022年末の完成を目指す、オーストラリアの、美術館の増築計画「シドニー・モダン・プロジェクト」の2021年11月までの建設の様子を伝えるタイムラプス動画
- 今津康夫 / ninkipen!による、奈良市の、照明器具メーカー“NEW LIGHT POTTERY”のオフィス兼ファクトリー「trophy」。既存ペンシルビルを改修した施設で、小さな面積が積み重なる特徴を生かしフロア毎に用途と仕上げを変えた、ローカルで生まれ全国に広がる照明器具の製作発信拠点