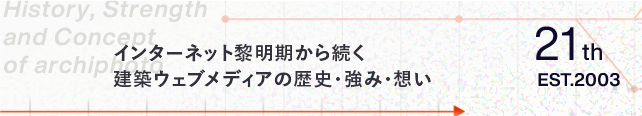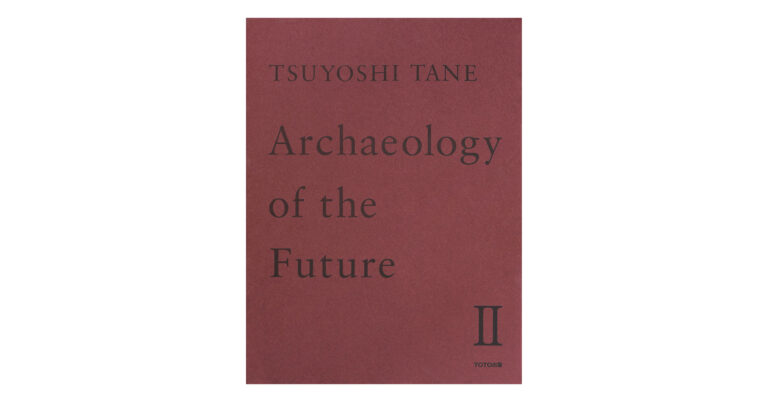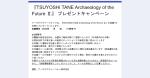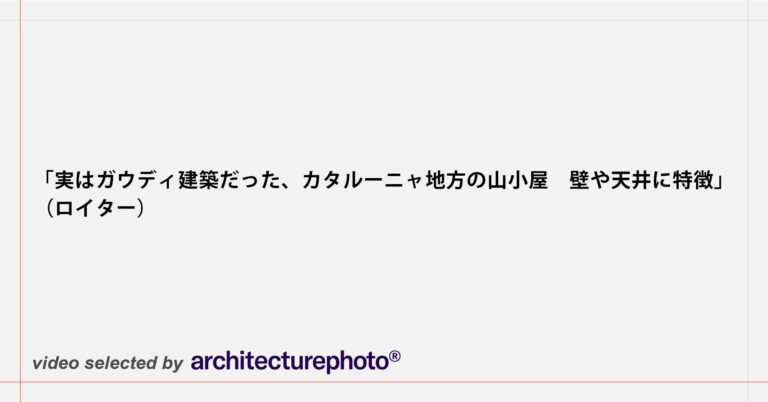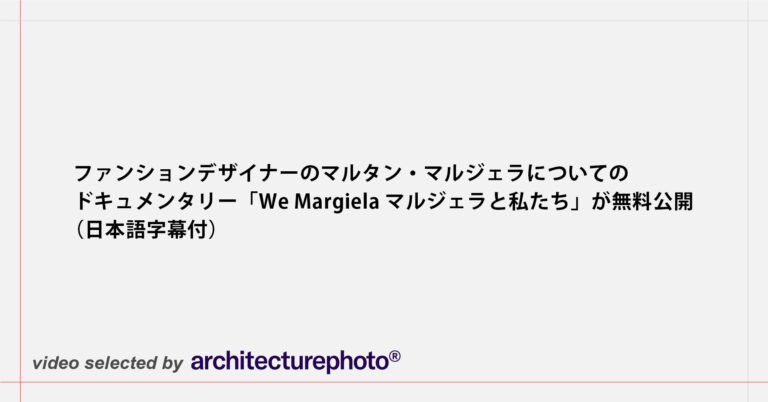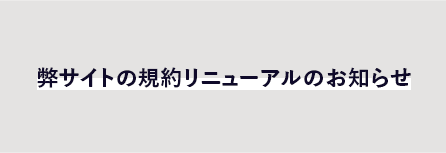スノヘッタによる、サウジアラビアの「カスール・アル・ホクム地下鉄駅」。新たな地下鉄網の主要ハブのひとつ。焦点としての機能に加えて内外を視覚的に繋げる為、鏡面のステンレスパネルで覆われたキャノピーを中央に据える計画を考案。テラゾー仕上げの広場は開かれた公共空間として機能 photo©Iwan Baan スノヘッタによる、サウジアラビアの「カスール・アル・ホクム地下鉄駅」。新たな地下鉄網の主要ハブのひとつ。焦点としての機能に加えて内外を視覚的に繋げる為、鏡面のステンレスパネルで覆われたキャノピーを中央に据える計画を考案。テラゾー仕上げの広場は開かれた公共空間として機能 photo©Iwan Baan スノヘッタによる、サウジアラビアの「カスール・アル・ホクム地下鉄駅」。新たな地下鉄網の主要ハブのひとつ。焦点としての機能に加えて内外を視覚的に繋げる為、鏡面のステンレスパネルで覆われたキャノピーを中央に据える計画を考案。テラゾー仕上げの広場は開かれた公共空間として機能 photo©Iwan Baan スノヘッタによる、サウジアラビアの「カスール・アル・ホクム地下鉄駅」。新たな地下鉄網の主要ハブのひとつ。焦点としての機能に加えて内外を視覚的に繋げる為、鏡面のステンレスパネルで覆われたキャノピーを中央に据える計画を考案。テラゾー仕上げの広場は開かれた公共空間として機能 photo©Iwan Baan スノヘッタによる、サウジアラビアの「カスール・アル・ホクム地下鉄駅」。新たな地下鉄網の主要ハブのひとつ。焦点としての機能に加えて内外を視覚的に繋げる為、鏡面のステンレスパネルで覆われたキャノピーを中央に据える計画を考案。テラゾー仕上げの広場は開かれた公共空間として機能 photo©Iwan Baan スノヘッタ による、サウジアラビアの「カスール・アル・ホクム地下鉄駅」です。
こちらはリリーステキストです(翻訳:アーキテクチャーフォト / 原文は末尾に掲載)
360度の反射キャノピーと緑豊かな地下庭園が、カスール・アル・ホクム駅を訪れる旅行者を迎える
サウジアラビアの首都の新しい地下鉄システムにおける4つの主要ハブの一つであり、主要な2路線を結ぶ歴史的なアル=キリ地区駅は、都市のペリスコープとして機能する大きなステンレス鋼製キャノピーを備えた、開放的な都市および歩行者広場として設計されています。
駅の各階層は、外部を内側へ、内側を外部へと反射する鏡のような張り出し構造によって視覚的に結び付けられており、同時に自然光を地下駅へ導き、周囲の公共空間に日陰を提供しています。
スノヘッタは2012年に、この駅のコンペで勝利したコンセプトを開発しました。この85駅から成る地下鉄システムは、1日あたり最大360万人の乗客を収容する能力を有しており、昨年1月から一般公開されています。
低排出の交通手段をすべての人に利用可能にすることに加えて、この新しい交通ネットワークは主要地区を結び、依然として全移動の約97%が自家用車によって行われている急速に成長する都市において、交通渋滞の緩和に貢献します。
周囲を映し出すこと
そのスチール製キャノピーは焦点として機能し、駅の主な入口を示しています。その光沢のある外側表面は、8mmの二重曲面ステンレス鋼パネルで構成されており、それらは完全に溶接され、滑らかで継ぎ目のない外観を生み出すために研磨されています。
支持するスチール製スペースフレーム、すなわちステンレス外皮との接続のための調整可能なタイロッドを備えた強固で軽量な鋼構造によって、キャノピーはその基部である巨大な円錐壁の上方および外側へと張り出すことが可能になっています。地上レベルの下では、傾斜した内壁は、その地域の伝統建築に着想を得た左官仕上げの表面で仕上げられています。
建築を統合する要素であると同時に建物内の方向付けのポイントとして機能するスチール製キャノピーは、その鏡のような表面から間接的な太陽光を下方へ反射します。エネルギー生産のためのPVパネルは、キャノピー屋根の上部に設置されています。
「列車を降りて見上げると、キャノピーの裏面に反射した都市の360度の景色が見えます。そのため、自分が都市のどこにいるのかを即座に把握できます。同様に、都市側から来る場合にはキャノピーを見上げると、それは下で起こっているすべてのことを映し出します」と、ロバート・グリーンウッド(Robert Greenwood)は述べています。スノヘッタのパートナー兼プロジェクトリード