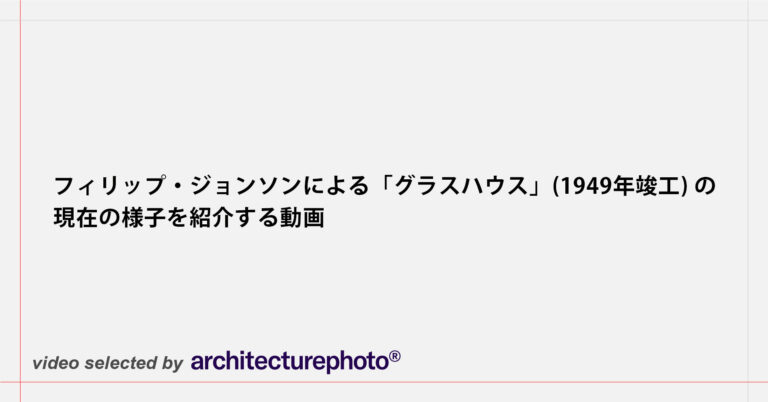ザハ・ハディド事務所による、中国・西安の「Daxia Tower」。新技術の主要拠点となる地域の開発地区に計画。高さ210m床面積12万㎡の建築でオフィスや店舗と付帯施設を内包。自然採光と通風の最適化に加えて最新技術で入居者の行動を解析して快適性を保つ image©ATCHAIN ザハ・ハディド事務所による、中国・西安の「Daxia Tower」。新技術の主要拠点となる地域の開発地区に計画。高さ210m床面積12万㎡の建築でオフィスや店舗と付帯施設を内包。自然採光と通風の最適化に加えて最新技術で入居者の行動を解析して快適性を保つ image©ATCHAIN ザハ・ハディド事務所による、中国・西安の「Daxia Tower」。新技術の主要拠点となる地域の開発地区に計画。高さ210m床面積12万㎡の建築でオフィスや店舗と付帯施設を内包。自然採光と通風の最適化に加えて最新技術で入居者の行動を解析して快適性を保つ image©ATCHAIN ザハ・ハディド・アーキテクツ による、中国・西安の「Daxia Tower」です。
こちらはリリーステキストの翻訳です
西安で行われたセレモニーで、Daxia Groupはザハ・ハディド・アーキテクツが西安の繁栄する開発区の中心に新しいDaxia Towerを建設することを発表しました。
人口900万人に迫る中国最大級の内陸都市のひとつである西安は、中国の古代の首都であり、シルクロードの歴史的な東の玄関口でした。近年、西安は国や地方自治体のイニシアティブ、そして西安にある多くの評価された大学や研究機関に支えられ、国内外のリーディング企業を惹きつける盛んなテクノロジー・エコシステムを発展させてきました。この都市は、半導体製造、ロボット工学、航空宇宙、バイオ医薬品を含む新技術の主要拠点となっています。
都市南西部に位置する西安ハイテク経済技術開発区は、西安の地下鉄6号線沿いにあり、フォーチュン500企業や多国籍企業100社以上が製造・研究開発の拠点を構えています。ザハ・ハディド・アーキテクツがDaxia GroupのためにJingye Roadに建設する新しいDaxia Towerは、西安の経済成長の重要な原動力となっているハイテクゾーンの中核に位置します。
市内Yanta地区のJingye RoadとZhangbawu Roadの交差点の南東角に位置する16,700㎡の敷地に位置する高さ210mのDaxia Towerには、127,220㎡のオフィス、店舗、付帯施設が組み込まれます。開発区周辺の街並みと一体化するDaxia Towerは、西安のビジネス街の中心に位置し、企業本社、商業オフィス、国際ホテル、住宅開発などの高層ビルが集積しています。
ビジネス街の中心部を区画するDaxia Towerの緩やかなカーブを描くシルエットは、幾重にも重なるパターン化された艶やかでドラマチックな吹き抜けのレイヤーによって強調され、自然光がフロア奥深くまで差し込みます。山肌の滝を彷彿とさせるような、植栽の施された滝のような室内テラスをつくる各アトリウムからは、北と東に広がる歴史的な街並みや、南と西に広がる成長著しいハイテク地帯を一望できます。
データ分析と行動モデリングを駆使して設計されたタワーの内装には、リアルタイム分析によってサポートされる将来を見据えた適応性の高いワークプレイスが含まれ、従業員の個人的・全体的な幸福度を高める健康的で楽しい環境を作り出します。