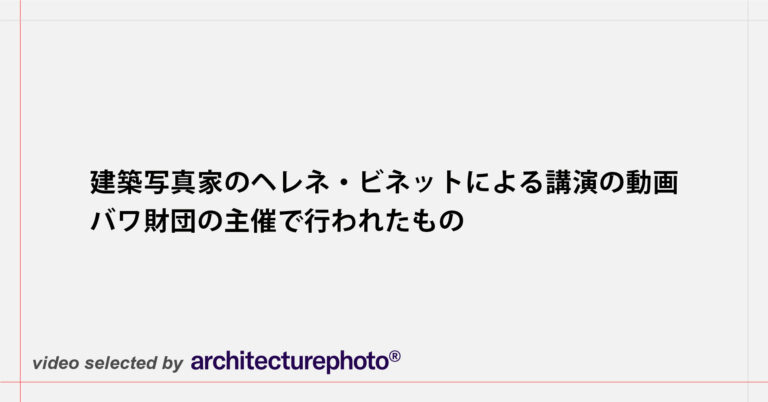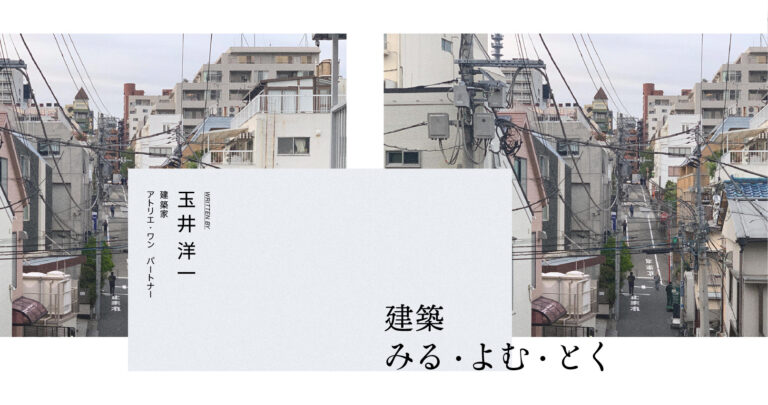組織設立30年を迎え、共同住宅・福祉施設・教育施設等を手掛ける「株式会社 野生司環境設計」の、建築設計監理スタッフ(新卒・経験者)募集のお知らせです。詳しくは、ジョブボードの当該ページにてご確認ください。アーキテクチャーフォトジョブボードには、その他にも、色々な事務所の求人情報が掲載されています。
新規の求人の投稿はこちらからお気軽にお問い合わせください。
※おかげさまで新卒の方は採用が決定しました。今回の延長掲載については、実務経験者の採用を希望しております!!
私たちは組織設立30年の意匠設計事務所です。共同住宅、福祉施設、教育施設をメインとしつつ、銀座久兵衛の数寄屋建築や京都の町家風商業施設まで多岐にわたる設計活動をしております。また、マンション・デザイン監修の依頼も多数あり、評価いただいております。BCS賞はじめグッドデザイン賞も多数受賞。その他数々の建築に関する賞もいただいております。
私たちは、建物単体のデザインではなく「使う方・周辺の方々の環境を作り出す使命がある」との理念の基、社名を「環境設計」とさせていただきました。
プロジェクトに対して企画から竣工まで一貫して携わっていただくことを基本とし、模型をたくさん作り、CGも多用しプレゼンを行い継続的に担当をしますので、多くを身に着けることができます。
最初は先輩スタッフとペアとなり一連の流れを覚えていただきます。慣れてきましたら、プロジェクトのスタートから竣工までを主担当として携わっていただきます。
昨年、事務所の改修をおこないました。見通しの良いオープン・スペースの中で、一人当たり1畳分のデスクを確保しております。フリーアドレスですので、その日の仕事内容に合わせて場所が選択できます。ガラス・スクリーンを通して竹林と数寄屋門の景色を眺めながら業務をしていただけます。
私たちと一緒に幅広い視野を養いながら、環境造りに取り組んでいきませんか!?
応募をお待ちしております。